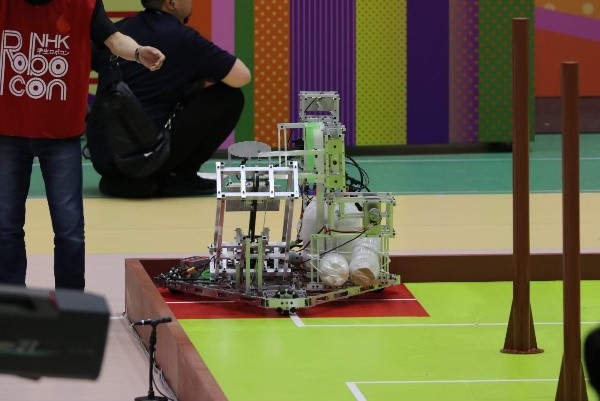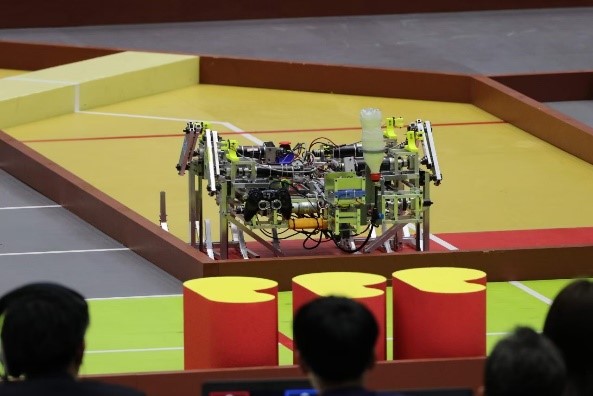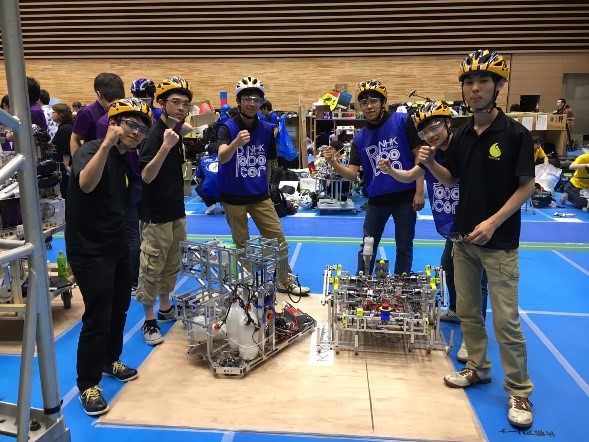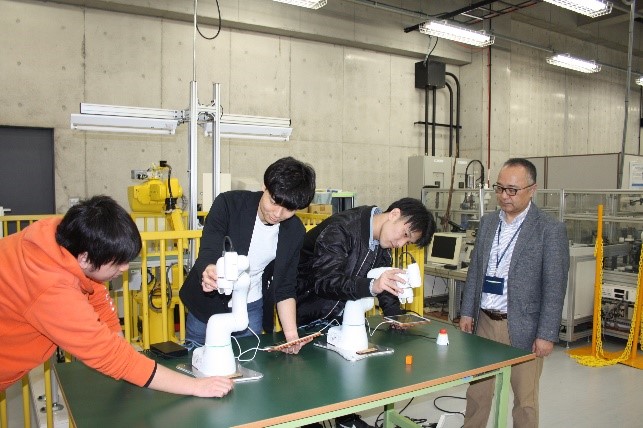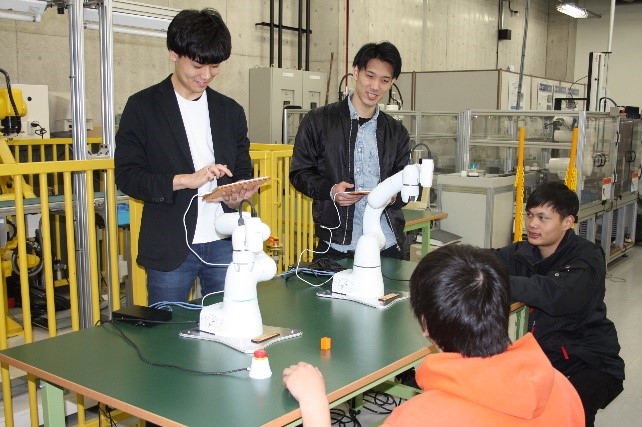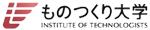


江戸時代に大衆化したからくり人形は、現代では『からくりサーカス』や『人形草紙あやつり左近』、『NARUTO』や『鬼滅の刃』等、数々の漫画やアニメに登場し、日本のカルチャーに深く根付いています。そして、「からくり」はカルチャーだけではなく、現在のものづくりにも通じています。からくり人形が目指す動きは人間と同じ動き。これはロボットの動きに通じています。また、からくりの技術を製造ラインに活用し、効率的にものづくりをする「からくり改善」が多くのメーカーで取り入れられています。
「からくり」は、日本における古い時代の機械的仕組みのことで、からくりに関する最古の記録は『日本書紀』に記述されています。
からくりが文化的に開花したのは江戸時代。1620年(元和6年)、尾張国名古屋の東照宮祭における山車に牛若弁慶のからくり人形が載せられ、中京圏を中心に「からくり人形を載せた祭礼の山車」が普及しました。そして、1662年(寛文2年)に大阪の道頓堀でからくり芝居が興行され大衆化していきました。
このように、古来から日本人にとって縁のある「からくり人形」について、江戸時代から続く、からくり人形師の家系の現当主、九代玉屋庄兵衛氏によるからくり人形の実演と解説を交え、からくり人形、江戸のモノづくりなどを研究している末松良一氏から江戸からくりの発展経緯や工場での「からくり改善」について講演いただきます。
| 講座名 | 「からくりは日本のものづくりの源流」 |
|---|---|
| 日時 | 2022年12月19日(月)14:30~16:30(14:00開場) |
| 場所 | TKPガーデンシティPREMIUM大宮 大ホール (埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-333-13 大同生命さいたま大宮ビル) |
| 参加費 | 無料 |
| 定員 | 先着150名 |
| 申込期間 | 受付を終了させていただきました |
| 申込方法 | 上記参加申込みボタンよりお申し込みください |

平成7年:九代目を襲名
平成10年:座敷からくり「弓曳き童子」を完全復元
平成27年:卓越した技能者「現代の名工」受賞

専門は、機械制御、流体関連振動、メカトロニクス、画像処理工学、最近では、からくり人形、江戸のモノづくりなど調査研究にも従事。