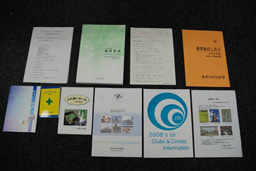もっくん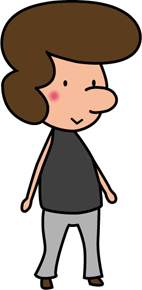 |
|||||||
|
|||||||
|
受付は9時45分からなんですけど、早めに家を出ました。30分前には大学に到着し、正門から大きな木製アーチをくぐって会場の体育館に向いました。ところが、びっくり。前には、新入生が、すでにたくさん集まっていました。みんなもヤル気満々なんだなあ、気合が入りました。 |
||
| それにしても、安全手帳はすごい。大学でこんな本格的な手帳を使う。「ものつくり大」らしさだよね。 | |||
 |
 |
||
ガイダンスは、学部長から教育方針や安全教育について、教務長から大学生活の留意点について、つづいて、各事務担当の方から、施設や学内情報システムの利用方法や、奨学金の紹介などがありました。さらに、クラブ・サークル活動紹介、学園祭の紹介については、先輩の「ものつくり大生」からお話がありました。僕は、高校までずっと運動部でしたけど、去年「ものつくり大」が全国準優勝したロボコンにも惹かれるし、できたら技能オリンピックにも出れたらいいなぁとも思うし、やりたいことがいっぱいで悩んじゃうな。 |
|||
|
そして、入学ガイダンスは、12時30分頃終了となりました。午後は何も予定が入っていないので、勇気を出して、隣に座っていた友達(友達になれるかなぁ)を誘ってランチに行きました。おにぎりを買って、近くのさきたま古墳群へ。ちょっとしたピクニック気分です。さきたま古墳群は、金文字の刻まれた鉄剣が出土したことで有名で、高校の日本史の教科書にも載っていたんで、一度来てみたいと思ってたんだ。でもやっぱり一番目立つのは、日本随一の円墳とされる丸墓山ですね。ここは、上杉謙信も石田三成も忍城攻めで陣をしいたと伝えられていて、最近は「のぼうの城」って小説でも出ていましたが、まさしく「のぼうの城」である忍城については、またの機会に行ってみたいと思います。 とにかく、写真のとおり、桜も満開で、お昼のちょっと一息には最高でした。「ものつくり大」を出発して、古墳公園のベンチでランチをとって帰ってきました。45分あれば行って来れちゃうんですよ。これからもたまには、こんな昼休みを過ごすのもいいんじゃないかな。
|
||
今日は入学式です。 |
 |
||
|
|
||
 |
 |
会場の体育館には、すでに大勢の新入生が集まっています。10時の開式を前に、地元行田市の声楽家田中先生による「ものつくり大校歌」の指導が始まりました。そりゃそうだよね、「ものつくり大校歌」はじめて歌うんだもん。練習しとかなきゃ。これは、梅原総長の作詞なんだよね。はずかしながら高校時代はあんまり知らなかったけど、梅原総長って、文化勲章も受章した有名な哲学者で、本屋さんにもたくさんの著作が並んでいるんだ。僕にはちょっと難しそうなんだけど。 | |
|
|||
でもね、校歌の歌詞は、「ものつくり大生」の僕には、ぐっと来るものがあったんだ。総長の熱い思い、「ものつくり大生」への大きな期待を、おもいっきり詰め込んだのが、 この校歌なんだって、僕なりに感じたんだよ。(校歌の歌詞はこちら) |
|||
 |
神本武征学長から「新入生に贈る言葉」をいただき(「新入生に贈る言葉(全文)」はこちら)、 つづいて「お祝いの言葉」を、梅原猛総長(哲学者、文化勲章受章者)、庄山悦彦会長(株式会社日立製作所取締役会長)、石岡慎太郎理事長(社団法人全国技能士連合会会長、職業訓練法人日本技能教育開発センター理事長)からいただきました。 | ||
| 『えっ、「ものつくり大」の会長って、あの日立の会長さんなの?』って初めて思った人もいるかも知れませんね。僕も、大学案内を見たときびっくりしたんだ。新入生の何人かは、お祝いの言葉を聴きながら、頭の中で『この木なんの木、気になる気になる、見たこともない木ですから、・・・』って音楽が流れていたかも知れないね。ちなみに、この歌、カラオケにもあるんだよね。4番まであって「木」は18回も出てくるんだ。 | |||
 |
|
||
|
次に、来賓祝辞として、厚生労働省舛添大臣のご祝辞と、埼玉県上田知事のご祝辞を、そして、地元行田市からは、工藤市長より直々にご祝辞をいただきました。 文部科学大臣よりの祝電が披露された後、「新入生誓いの言葉」が宣言されました。さすがに、新入生代表、緊張感が伝わってきます。(「新入生誓いの言葉(全文)」はこちら) |
||
| 2008年4月4日(金) | |||
| 今日、「ものつくり大生」は、体育館で定期健康診断です。また、各学科では、2年生以上の上級年次の学科ガイダンスが行われました。 | |||
|
写真は、健康診断を受診している「ものつくり大生」の様子です。やっぱり、けっこう混雑してますね。健康管理も重要だし、上級生は、就職活動なんかでも使えるしね。 | ||
中央棟では学科に分かれて、上級生の学科ガイダンスが行われていました。2日の入学ガイダンスとは雰囲気が違いますよね。やっぱり、上級生になると、大学生が板についてるというか、落ち着いた雰囲気がありますよね。 |
 |
||
 |
おっ、ガイダンスの終わった先輩たちが、先生といっしょに、キャンパス内の芝生の手入れをしています。この広場、「ものつくり大生」の設計で、施工も授業や先生方の尽力で行われているんだ。 |
||
 |
|||
| これまで、4月2日に入学ガイダンス、3日に入学式と1年生学科ガイダンス、4日に上級年次の学科ガイダンスと学生定期健康診断とつづき、なんと、7日(月)から授業開始です!こんな早くから授業が始まる大学って少ないよね。クォータ制の特徴でもあるんだろうけど、なんと言っても、「ものつくり大」の授業は濃密なんだと思う。これから、少しずつ授業風景なども紹介していきますので、楽しみにしていてくださいね。 | |||
| 2008年4月10日(木) | |||
今日、製造1年生は、Fゼミ(フレッシュマンゼミ)という授業がありました。第1回目なので、各クラスの担任の先生が紹介され、Fゼミの授業内容やスケジュールの説明がありました。 |
|
||
 |
 |
||
| チームに分かれ、各チームでルーブ・ゴールドバーグマシン(カラクリマシン)を製作して、大会を行います。その名も「MONOカラクリマシンコンテスト」。 | |||
テレビ東京の「TVチャンピオン」で先輩が製作したカラクリマシンの映像などを見ながら、なんとなくイメージが湧いてきました。チームみんなでアイデアを出し合い、7月24日のコンテストでは優勝したいな。 |
|||
| 2008年4月11日(金) | |||
建設のFゼミ(フレッシュマンゼミ)は、第1回目が今日あったそうです。全体説明、第8回までの概略説明、各担任の先生からお話があったとのこと。 |
|
||
(建設技能工芸学科ホームページはこちら) このページの先頭に戻る |
|||
| 2008年4月19日(土) | |||
今日は、製造1年生全員、さいたま市にある鉄道博物館の見学です。なんだか、楽しいイベントのようです。先生から「エンジニアの目で見るように」と言われ、ちょっと気合が入っています。 |
|
||
|
Fゼミで、これから製作していく、カラクリマシンのヒントをつかんで帰りたいと思っています。 鉄道博物館は、車両を中心とする展示のほかに、運転シミュレーションなどの体験コーナーもあり大盛況ですが、運転シミュレーションの機械はどういうしくみで作られているのか考えながら見学していくことで、「ものつくり大生」としての自覚が芽生えてきた気がします。 |
||