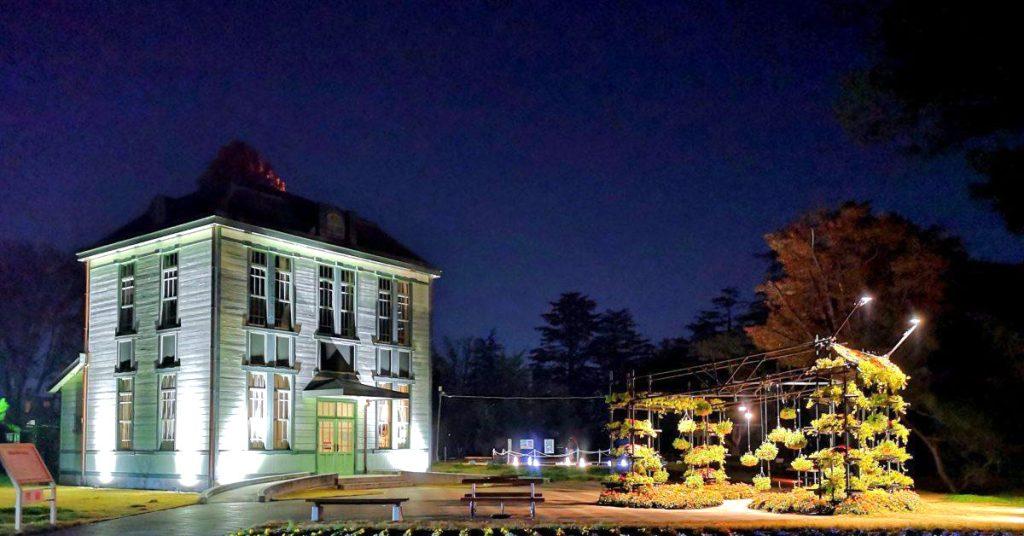#キャリア支援
- 新着順
- 人気順
-

建設学科の女子学生が、建設(土木建築)現場の最前線で働く女性技術者のリアルを『見る』・『聴く』
2023年10月20日、若築建設株式会社(本社目黒区)主催の女性技術者志望者対象の「工事現場見学会及び座談会」に、本学から、建設業に興味のある建設学科3年の女子学生5名が参加しました。この企画は、参加した女子学生が工事現場や女性技術者について理解を深め、建設業の魅力に触れることで、進路選択の一助になることを目的としています。本学では、長期インターンシップや企業訪問等の多様なキャリア支援施策を実施していますが、女性による女性のための女性だけのユニークな企画参加はおそらく初めて。参加した女子学生5名のリアルな感想を伺いました。 一瞬で打ち解けた若き女性技術者の明るさと元気さ 会場となったのは東京都葛飾区の新中川護岸耐震補強工事の現場。本事業は、東京都の女性活躍モデル工事となっているものです。まず若築建設から女性技術者9名の自己紹介があり、続いて4班に分かれた本学の女子学生がそれぞれ自己紹介を行いました。その後、全体スケジュールの説明があり、「女性技術者の目線から見た現場の現況や魅力を見て、今後の進路選択に役立ててほしい」と本日の目的を強調されました。学生たちは明るく元気な女性技術者の皆さんから積極的に話しかけていただきました。遠藤 夢さん(澤本研究室)は「女性技術者の皆さんが初対面の人同士でもフレンドリーでした」と第一印象について話してくれました。次に、いよいよリアルな工事現場見学に移動。現在進めている施工場所の長さは約150メートル。その移動の途中、学生たちは、気さくに説明をされる女性技術者に触れ、「現場で働く人に対して怖いイメージをもっていたけれど、実際は優しかったです」と河田 さゆりさん(田尻研究室)はイメージと現実の姿の違いを感じたようです。工事中の現場では、この工事の責任者である女性の監理技術者が「現在進行中の護岸工事は階段状に削ったところに新しい土を入れ、地滑りが起こらないように転圧(固める)をしています」と説明してくださいました。その姿を見たタマン・プナムさん(澤本研究室)は「現場に女子の監理技術者がいるのは面白い」と興味を持ちました。学生たちはフェンス越しに護岸の工事現場の様子を見て、メモを取ったり、女性技術者から具体的な説明を聞いたりするなどして現場でどのような工事を行っているのかを体感していました。説明してもらっていたカルキ・メヌカさん(澤本研究室)とプナムさんは「現場で働く女性技術者の方に、優しく、いろいろ教えてもらえて、とても勉強になりました」と話していました。 また工事現場での女性への配慮の一つとして、設置された仮設トイレや休憩所も見学しました。気になる仮設トイレは臭いを極力抑えるコーティングがされていることや休憩所では、電子レンジやWi-Fiが完備されている話などを伺いました。学生たちは現場でどのようにトイレを使用したり、休憩したりするかといったことにも関心もあり、工事現場の環境改善が進んでいることを実感しました。晴天でしたが、風が強めの見学であったため、女性技術者から現場の仕事は天候に左右される仕事でもある事情をお聞きし、現場の実情を知り、「現場を見られてよい経験になりました」と遠藤さん。また、工事現場見学を通し「現場のイメージが変わり、若い方も働いていて、働きやすい環境だと感じました」と河田さんは話してくれました。今回の工事現場見学では、日頃見聞きできない工事の進行状況や女性技術者がどんな環境でどのように仕事をしているのか直接教えていただきました。今回の工事現場見学を通して感じ、学んだことを他の学生とも情報共有し、本学での学習に活かすとともに建設業界の内情について理解を深めていってくれることを期待します。 4班それぞれに笑顔があふれた座談会 遠藤 夢さん 1班の遠藤さんは、監理技術者含む入社1年目と2年目の女性技術者3名との座談会。用意されたプロフィールを見ながらの現場での仕事の話になり、「女性技術者でも夜勤はあるけれど『滑走路から見る東京の夜景』や『早朝の富士山』は格別」といった現場あるある的なお話をしてくださいました。女性技術者と男性技術者の違いに関心があった遠藤さんは座談会で「現場で働く技術者は資格もある人もいれば、そうでない人もいて、男女に優劣はなく、その人次第ということを知りました」と話してくれました。 2班の金子 歩南さん(澤本研究室)は、入社8年目と1年目の2名の女性技術者との座談会。入社した経緯や自社の良いところについて熱弁してくださったお2人。話を聞いた金子さんは「土木・建築の技術者に進もうとする人は『インターンシップ』がきっかけだったり、土木や建築が元々好きだったりする人がいることを知りました」と。また、土木・建築の技術者にとってどんなことが大変だったかを知りたかった金子さんは「入社当初は、土木・建築の技術者としてなかなか実力が認められなかったけれど、経験を積んで、実績を見てもらったり、さまざまな立場の方との話をしたりして分かってもらえるようになった」という体験談を聞けたそうです。 3班のプナムさんとメヌカさんは、中途入社した4年目と8年目の2名とスリランカ出身で入社2年目の計3名の女性技術者との座談会。さまざまな経歴をもつ女性技術者たちからキャリアの活かし方について具体的なお話が聞けました。また、留学生である学生2人は外国人の女性技術者の働き方や文化の違いの対応について関心が高く、働く上で文化的な違いをどうやって理解し、日本の働き方に合わせるかを熱心に聞いていました。日本でアルバイトをしているからこそ同じ外国人として働く上での大変さについて共感も生まれていました。 タマン・プナムさん カルキ・メヌカさん さらに、日本企業と海外企業の仕事の進み具合の違いといった国際的な話も展開されていました。プナムさんは「スリランカ出身の方の話がためになりました。また、海外プロジェクトに参加したら、その経験が身につき、自分自身の実力になることを知りました」と。メヌカさんは「入社前に資格取得が必要ではないかと考えていましたが、土木・建築の分野の資格は入社してからでも大丈夫だと聞いて安心しました」と話してくれました。 4班の河田さんは、入社1年目と6年目の2名の女性技術者との座談会。日常生活について話を聞いたり、女性技術者が設計したものを直接タブレットで見せてもらったり、働く上で必要なことを伺いました。リアルな女性技術者の話を聞いた河田さんは「就職活動するにあたり、立派な志望理由が必要だと思っていましたが、『さまざまな角度や観点から考えてもいいんだ』といったことを考える良い機会になりました」と話してくれました。 視野を広げた貴重な体験 今回の座談会では、学生たちが若築建設の女性技術者の皆さんからさまざまな体験やアドバイスを聞くことができました。金子さんは「他の会社を見学した際、現場で働くのは男性が中心でしたが、今日は年齢が近い女性技術者にお会いできて、話が聞けてよかったです」と他の会社見学とは違った体験ができたと話してくれました。現場で働く女性技術者の年齢が近い方も多かったため親近感もわき、自分事して考えることができ、大きく印象が変わったようです。 金子 歩南さん また、今後の進路選択に当たり、若築建設のような建設会社を選択肢に入れたい思いが生まれたり、視野を広げたものの見方について学ぶ機会になったりと貴重な時間になりました。プナムさんは「女性技術者の皆さんの経験をお聞きし、皆さんがどれだけ頑張っているかを知り、私も頑張り、このような職業に就きたいと思いました」と熱い思いを語ってくれました。メヌカさんは「若築建設では英語も磨けると聞き、とても興味を持ちました」と意欲をわかせていました。最後に澤本武博教授(建設学科)からは、先生自身が若築建設の勤務経験があったことや卒業生が働いていることなどを踏まえ「今日の経験を今後の学生生活や就職活動に活かしてほしい」というお話をしてくださいました。そして女性技術者の皆さんからは熱いエールを送っていただき、座談会の幕を閉じました。工事現場見学会や座談会の進行を行っていただき、また熱心に説明をしてくださった若築建設の女性技術者の皆さまには心より感謝申し上げます。 参加者/1班:遠藤 夢 さん(建設学科3年、澤本研究室)2班:金子 歩南 さん(建設学科3年、澤本研究室)3班:カルキ・メヌカ さん(建設学科3年、澤本研究室)3班:タマン・プナム さん(建設学科3年、澤本研究室)4班:河田 さゆり さん(建設学科3年、田尻研究室) 関連リンク ・建設学科WEBページ・澤本研究室WEBサイト・田尻研究室WEBサイト・若築建設株式会社WEBサイト
-

現場体験で感じた林業に魅了されて・・・第二の故郷へ就く
林業の機械化が進んだことで、素材生産や森林調査等で女性が活躍する場が増えています。とはいえ、まだまだ3K(きつい、汚い、危険)のイメージは拭えません。その林業の現場に大きな夢を抱いて挑戦する女子学生がいます。 例えば、京都を代表する銘木「北山杉」。古くから北山林業では女性は重要な役割を担っていました。枝打ちや伐採は男性の仕事ですが、加工作業や運搬、苗木の植え付けは主に女性の仕事でした。では、現代の林業女子には仕事はないのでしょうか。近年は機械化が進むことで伐採等の林業現場へも女性が進出することが期待されています。その林業に挑戦する浅野 零さん(建設学科4年)。153㎝の華奢なカラダからは想像できないバイタリティーの源はなにか、感動のインタビューです。 浅野さんのチャレンジ魂を育てたものは何ですか 高校までものづくりとは縁がなかったです。茨城県の生まれですが、小学校4年から中学卒業まで長野県にある人口850人程の村へ山村留学していました。高校は山口県でした。田舎が好きで、今度は瀬戸内海の島でした。山から海へ、です。高校時代は、アーチェリー部に所属していました。強化指定を受けていたことで、3年生では選手として全国大会へ出場しています。強いてものづくりと縁があるなら、山村留学時に仲間と小屋を作ったことでしょうか。その楽しかった思い出は心のどこかにずっとあって、このエピソードはものつくり大学へ進学する時に大学の方にお話しました。大学からすると、私の志望動機が不思議に思えたようでした。 そもそも母の影響というか、子育て方針というか、兄も同じ村に先に山村留学していて、後にカナダへ海外留学をしました。私は茨城→長野→山口→埼玉と国内を巡っていますが、この度、就職で長野へ戻ります。それも山村留学でお世話になった同じ村に戻ります。何でしょうね、Uターンでもなく、Iターンでもなくて。 大学での4年間もパワフルだったのではないですか もちろん普通高校卒なので、ものづくりを学んだのは入学してからです。木に触れることは好きだったので、最初は木工家具の製作に憧れました。角材を加工する授業は楽しかったけれど、そのうち角材になる前の木自体に興味が湧いてきて、林業を意識するようになりました。 1年の秋に「林業体験」のイベントを探して個人で参加しました。木を切って、加工して、その凄さに憧れました。女性も参加しやすいイベントで、参加したのは大方女性でした。人生で初めてチェンソーを使って、木を切りました。そして、垂直に立てた木の幹に切り込みを入れて燃やし、手軽に焚き火が楽しめるスウェーデントーチでの料理を楽しみました。 これをきっかけに林業界への憧れが強くなり、将来仕事として就きたいと思うようになりました。2年次に実施される大学のインターンシップは、長野県飯山市のNPO法人で木材加工に従事しました。3年次では、進路を林業一本に絞ったため、個人的に様々な企業や現場を見学に行きました。そういう意味では決断も早く、行動力もありましたね。いま思えば大学の授業との両立もうまく対処していたように思います。 自らの進むべき道を見つけるまでに、どんな出会いがありましたか 大学では就活を意識した活動と共に、1年次で建築大工3級、2年次で左官2級、造園3級、3年次で造園2級と、とにかく木に関わる資格を取得していきました。生活全てを木に関わっていきたい思いが強かったです。 実は、高校時代に生活していた山口県の林業会社の方に「この世界、女性ではたいへんだけれど、男性とは違う視点で活躍している方がたくさんいるよ」と言われました。その林業会社の方にはオンラインで頻繁に相談に乗っていただきました。「山口においでよ」と何度もお誘いをいただきました。正直、山口へ移住しようという気持ちにもなりました。同時に長野とも連絡を取っていて、情報収集に努めていました。 林業は、国の重要な施策なので、どちらかと言えば昔ながらの堅苦しいイメージを持っていました。でも、民間の小さな林業会社では、自分の技術やスキルがついたらやりたいことをやらせてもらえるような新しい考え方も生まれてきていることを知りました。長野で林業を起業された社長さんと話していると、ぐいぐい引き込まれていきました。その将来を見据えた魅力たっぷりの内容に感激しました。 そして最終的に長野へ就職を決めたのですか もちろん企業方針を何度も聞いて、性格的に合っているなと思いましたし、私が内定をいただいた会社がある村は、小学生の山村留学でお世話になったところでした。この村は私にとって特別です。住むことができる、仕事をすることができるなら恩返しの気持ちを持って戻りたいと強く思いました。会社も林業としては2021年に法人化されたばかり。不思議な縁を感じて、お世話になった村へ帰ろうと思いました。 林業女子としての不安や期待はありますか 林業は3Kと言われます。きつい、汚い、危険ですね。それに林業の現場に出る女性としての問題は、まずトイレ。いまは自然保護の観点から、以前のような現地で処理するようなことは減ってきています。トイレの設置や、山を下って用を足すこともできます。それから力の強さですね。女性ですので、体力は男性と比べて見劣りします。でも機械化も進み、力の問題も徐々に解決してくれそうです。緑の雇用制度で3年間鍛えることができるので、いまはそれが楽しみでなりません。都会にある林業会社では、近年「かっこいい林業」をスローガンにして新しい「K」が生まれています。期待ということでは、いずれキャンプ場を作るという会社の重点方針があります。いまは力不足ですが、ぜひチャレンジしたいです。 林業を通して、森林と地域との新たな価値を創造する繋ぎになるということですね 日本は平野の少ない森林大国です。木があれば、火を起こせる。火を起こしたら、ごはんも炊ける、お風呂も沸かせる。家も建てられるし、生きていく上でのあらゆる繋がりがあります。花粉問題だって、木を切る人がいれば、むしろ空気の循環を良くしてくれる。林業は大切なんですよね。人間の生活の基盤になっていると思っています。 ですから林業を通して、そこに生活する方たちのほのぼのとした幸福感や満足感を充足したいですし、村おこしといった地域の活性化にも非常に興味があります。 大学では様々な検定試験に挑戦しましたが、授業では学べないところまで教えてもらいました。先生方の技術が素晴らしいので、安心して学べます。私はこうした知識や技能・技術は、いずれどこかの場面で役立つと思っています。自分と仕事、自分と社会を繋ぐ力です。その力がないと新たな価値の創造なんてできないです。 視野が広がり、自分の進むべき道を見つけた大学での4年間。いまは卒業制作に仲間と懸命に取り組んでいます。一般家庭のエントランスと庭づくりです。次のステップへ進むために!!! 関連リンク 建設学科WEBページ
-

建設学科の女子学生が、建設(土木建築)現場の最前線で働く女性技術者のリアルを『見る』・『聴く』
2023年10月20日、若築建設株式会社(本社目黒区)主催の女性技術者志望者対象の「工事現場見学会及び座談会」に、本学から、建設業に興味のある建設学科3年の女子学生5名が参加しました。この企画は、参加した女子学生が工事現場や女性技術者について理解を深め、建設業の魅力に触れることで、進路選択の一助になることを目的としています。本学では、長期インターンシップや企業訪問等の多様なキャリア支援施策を実施していますが、女性による女性のための女性だけのユニークな企画参加はおそらく初めて。参加した女子学生5名のリアルな感想を伺いました。 一瞬で打ち解けた若き女性技術者の明るさと元気さ 会場となったのは東京都葛飾区の新中川護岸耐震補強工事の現場。本事業は、東京都の女性活躍モデル工事となっているものです。まず若築建設から女性技術者9名の自己紹介があり、続いて4班に分かれた本学の女子学生がそれぞれ自己紹介を行いました。その後、全体スケジュールの説明があり、「女性技術者の目線から見た現場の現況や魅力を見て、今後の進路選択に役立ててほしい」と本日の目的を強調されました。学生たちは明るく元気な女性技術者の皆さんから積極的に話しかけていただきました。遠藤 夢さん(澤本研究室)は「女性技術者の皆さんが初対面の人同士でもフレンドリーでした」と第一印象について話してくれました。次に、いよいよリアルな工事現場見学に移動。現在進めている施工場所の長さは約150メートル。その移動の途中、学生たちは、気さくに説明をされる女性技術者に触れ、「現場で働く人に対して怖いイメージをもっていたけれど、実際は優しかったです」と河田 さゆりさん(田尻研究室)はイメージと現実の姿の違いを感じたようです。工事中の現場では、この工事の責任者である女性の監理技術者が「現在進行中の護岸工事は階段状に削ったところに新しい土を入れ、地滑りが起こらないように転圧(固める)をしています」と説明してくださいました。その姿を見たタマン・プナムさん(澤本研究室)は「現場に女子の監理技術者がいるのは面白い」と興味を持ちました。学生たちはフェンス越しに護岸の工事現場の様子を見て、メモを取ったり、女性技術者から具体的な説明を聞いたりするなどして現場でどのような工事を行っているのかを体感していました。説明してもらっていたカルキ・メヌカさん(澤本研究室)とプナムさんは「現場で働く女性技術者の方に、優しく、いろいろ教えてもらえて、とても勉強になりました」と話していました。 また工事現場での女性への配慮の一つとして、設置された仮設トイレや休憩所も見学しました。気になる仮設トイレは臭いを極力抑えるコーティングがされていることや休憩所では、電子レンジやWi-Fiが完備されている話などを伺いました。学生たちは現場でどのようにトイレを使用したり、休憩したりするかといったことにも関心もあり、工事現場の環境改善が進んでいることを実感しました。晴天でしたが、風が強めの見学であったため、女性技術者から現場の仕事は天候に左右される仕事でもある事情をお聞きし、現場の実情を知り、「現場を見られてよい経験になりました」と遠藤さん。また、工事現場見学を通し「現場のイメージが変わり、若い方も働いていて、働きやすい環境だと感じました」と河田さんは話してくれました。今回の工事現場見学では、日頃見聞きできない工事の進行状況や女性技術者がどんな環境でどのように仕事をしているのか直接教えていただきました。今回の工事現場見学を通して感じ、学んだことを他の学生とも情報共有し、本学での学習に活かすとともに建設業界の内情について理解を深めていってくれることを期待します。 4班それぞれに笑顔があふれた座談会 遠藤 夢さん 1班の遠藤さんは、監理技術者含む入社1年目と2年目の女性技術者3名との座談会。用意されたプロフィールを見ながらの現場での仕事の話になり、「女性技術者でも夜勤はあるけれど『滑走路から見る東京の夜景』や『早朝の富士山』は格別」といった現場あるある的なお話をしてくださいました。女性技術者と男性技術者の違いに関心があった遠藤さんは座談会で「現場で働く技術者は資格もある人もいれば、そうでない人もいて、男女に優劣はなく、その人次第ということを知りました」と話してくれました。 2班の金子 歩南さん(澤本研究室)は、入社8年目と1年目の2名の女性技術者との座談会。入社した経緯や自社の良いところについて熱弁してくださったお2人。話を聞いた金子さんは「土木・建築の技術者に進もうとする人は『インターンシップ』がきっかけだったり、土木や建築が元々好きだったりする人がいることを知りました」と。また、土木・建築の技術者にとってどんなことが大変だったかを知りたかった金子さんは「入社当初は、土木・建築の技術者としてなかなか実力が認められなかったけれど、経験を積んで、実績を見てもらったり、さまざまな立場の方との話をしたりして分かってもらえるようになった」という体験談を聞けたそうです。 3班のプナムさんとメヌカさんは、中途入社した4年目と8年目の2名とスリランカ出身で入社2年目の計3名の女性技術者との座談会。さまざまな経歴をもつ女性技術者たちからキャリアの活かし方について具体的なお話が聞けました。また、留学生である学生2人は外国人の女性技術者の働き方や文化の違いの対応について関心が高く、働く上で文化的な違いをどうやって理解し、日本の働き方に合わせるかを熱心に聞いていました。日本でアルバイトをしているからこそ同じ外国人として働く上での大変さについて共感も生まれていました。 タマン・プナムさん カルキ・メヌカさん さらに、日本企業と海外企業の仕事の進み具合の違いといった国際的な話も展開されていました。プナムさんは「スリランカ出身の方の話がためになりました。また、海外プロジェクトに参加したら、その経験が身につき、自分自身の実力になることを知りました」と。メヌカさんは「入社前に資格取得が必要ではないかと考えていましたが、土木・建築の分野の資格は入社してからでも大丈夫だと聞いて安心しました」と話してくれました。 4班の河田さんは、入社1年目と6年目の2名の女性技術者との座談会。日常生活について話を聞いたり、女性技術者が設計したものを直接タブレットで見せてもらったり、働く上で必要なことを伺いました。リアルな女性技術者の話を聞いた河田さんは「就職活動するにあたり、立派な志望理由が必要だと思っていましたが、『さまざまな角度や観点から考えてもいいんだ』といったことを考える良い機会になりました」と話してくれました。 視野を広げた貴重な体験 今回の座談会では、学生たちが若築建設の女性技術者の皆さんからさまざまな体験やアドバイスを聞くことができました。金子さんは「他の会社を見学した際、現場で働くのは男性が中心でしたが、今日は年齢が近い女性技術者にお会いできて、話が聞けてよかったです」と他の会社見学とは違った体験ができたと話してくれました。現場で働く女性技術者の年齢が近い方も多かったため親近感もわき、自分事して考えることができ、大きく印象が変わったようです。 金子 歩南さん また、今後の進路選択に当たり、若築建設のような建設会社を選択肢に入れたい思いが生まれたり、視野を広げたものの見方について学ぶ機会になったりと貴重な時間になりました。プナムさんは「女性技術者の皆さんの経験をお聞きし、皆さんがどれだけ頑張っているかを知り、私も頑張り、このような職業に就きたいと思いました」と熱い思いを語ってくれました。メヌカさんは「若築建設では英語も磨けると聞き、とても興味を持ちました」と意欲をわかせていました。最後に澤本武博教授(建設学科)からは、先生自身が若築建設の勤務経験があったことや卒業生が働いていることなどを踏まえ「今日の経験を今後の学生生活や就職活動に活かしてほしい」というお話をしてくださいました。そして女性技術者の皆さんからは熱いエールを送っていただき、座談会の幕を閉じました。工事現場見学会や座談会の進行を行っていただき、また熱心に説明をしてくださった若築建設の女性技術者の皆さまには心より感謝申し上げます。 参加者/1班:遠藤 夢 さん(建設学科3年、澤本研究室)2班:金子 歩南 さん(建設学科3年、澤本研究室)3班:カルキ・メヌカ さん(建設学科3年、澤本研究室)3班:タマン・プナム さん(建設学科3年、澤本研究室)4班:河田 さゆり さん(建設学科3年、田尻研究室) 関連リンク ・建設学科WEBページ・澤本研究室WEBサイト・田尻研究室WEBサイト・若築建設株式会社WEBサイト
-

現場体験で感じた林業に魅了されて・・・第二の故郷へ就く
林業の機械化が進んだことで、素材生産や森林調査等で女性が活躍する場が増えています。とはいえ、まだまだ3K(きつい、汚い、危険)のイメージは拭えません。その林業の現場に大きな夢を抱いて挑戦する女子学生がいます。 例えば、京都を代表する銘木「北山杉」。古くから北山林業では女性は重要な役割を担っていました。枝打ちや伐採は男性の仕事ですが、加工作業や運搬、苗木の植え付けは主に女性の仕事でした。では、現代の林業女子には仕事はないのでしょうか。近年は機械化が進むことで伐採等の林業現場へも女性が進出することが期待されています。その林業に挑戦する浅野 零さん(建設学科4年)。153㎝の華奢なカラダからは想像できないバイタリティーの源はなにか、感動のインタビューです。 浅野さんのチャレンジ魂を育てたものは何ですか 高校までものづくりとは縁がなかったです。茨城県の生まれですが、小学校4年から中学卒業まで長野県にある人口850人程の村へ山村留学していました。高校は山口県でした。田舎が好きで、今度は瀬戸内海の島でした。山から海へ、です。高校時代は、アーチェリー部に所属していました。強化指定を受けていたことで、3年生では選手として全国大会へ出場しています。強いてものづくりと縁があるなら、山村留学時に仲間と小屋を作ったことでしょうか。その楽しかった思い出は心のどこかにずっとあって、このエピソードはものつくり大学へ進学する時に大学の方にお話しました。大学からすると、私の志望動機が不思議に思えたようでした。 そもそも母の影響というか、子育て方針というか、兄も同じ村に先に山村留学していて、後にカナダへ海外留学をしました。私は茨城→長野→山口→埼玉と国内を巡っていますが、この度、就職で長野へ戻ります。それも山村留学でお世話になった同じ村に戻ります。何でしょうね、Uターンでもなく、Iターンでもなくて。 大学での4年間もパワフルだったのではないですか もちろん普通高校卒なので、ものづくりを学んだのは入学してからです。木に触れることは好きだったので、最初は木工家具の製作に憧れました。角材を加工する授業は楽しかったけれど、そのうち角材になる前の木自体に興味が湧いてきて、林業を意識するようになりました。 1年の秋に「林業体験」のイベントを探して個人で参加しました。木を切って、加工して、その凄さに憧れました。女性も参加しやすいイベントで、参加したのは大方女性でした。人生で初めてチェンソーを使って、木を切りました。そして、垂直に立てた木の幹に切り込みを入れて燃やし、手軽に焚き火が楽しめるスウェーデントーチでの料理を楽しみました。 これをきっかけに林業界への憧れが強くなり、将来仕事として就きたいと思うようになりました。2年次に実施される大学のインターンシップは、長野県飯山市のNPO法人で木材加工に従事しました。3年次では、進路を林業一本に絞ったため、個人的に様々な企業や現場を見学に行きました。そういう意味では決断も早く、行動力もありましたね。いま思えば大学の授業との両立もうまく対処していたように思います。 自らの進むべき道を見つけるまでに、どんな出会いがありましたか 大学では就活を意識した活動と共に、1年次で建築大工3級、2年次で左官2級、造園3級、3年次で造園2級と、とにかく木に関わる資格を取得していきました。生活全てを木に関わっていきたい思いが強かったです。 実は、高校時代に生活していた山口県の林業会社の方に「この世界、女性ではたいへんだけれど、男性とは違う視点で活躍している方がたくさんいるよ」と言われました。その林業会社の方にはオンラインで頻繁に相談に乗っていただきました。「山口においでよ」と何度もお誘いをいただきました。正直、山口へ移住しようという気持ちにもなりました。同時に長野とも連絡を取っていて、情報収集に努めていました。 林業は、国の重要な施策なので、どちらかと言えば昔ながらの堅苦しいイメージを持っていました。でも、民間の小さな林業会社では、自分の技術やスキルがついたらやりたいことをやらせてもらえるような新しい考え方も生まれてきていることを知りました。長野で林業を起業された社長さんと話していると、ぐいぐい引き込まれていきました。その将来を見据えた魅力たっぷりの内容に感激しました。 そして最終的に長野へ就職を決めたのですか もちろん企業方針を何度も聞いて、性格的に合っているなと思いましたし、私が内定をいただいた会社がある村は、小学生の山村留学でお世話になったところでした。この村は私にとって特別です。住むことができる、仕事をすることができるなら恩返しの気持ちを持って戻りたいと強く思いました。会社も林業としては2021年に法人化されたばかり。不思議な縁を感じて、お世話になった村へ帰ろうと思いました。 林業女子としての不安や期待はありますか 林業は3Kと言われます。きつい、汚い、危険ですね。それに林業の現場に出る女性としての問題は、まずトイレ。いまは自然保護の観点から、以前のような現地で処理するようなことは減ってきています。トイレの設置や、山を下って用を足すこともできます。それから力の強さですね。女性ですので、体力は男性と比べて見劣りします。でも機械化も進み、力の問題も徐々に解決してくれそうです。緑の雇用制度で3年間鍛えることができるので、いまはそれが楽しみでなりません。都会にある林業会社では、近年「かっこいい林業」をスローガンにして新しい「K」が生まれています。期待ということでは、いずれキャンプ場を作るという会社の重点方針があります。いまは力不足ですが、ぜひチャレンジしたいです。 林業を通して、森林と地域との新たな価値を創造する繋ぎになるということですね 日本は平野の少ない森林大国です。木があれば、火を起こせる。火を起こしたら、ごはんも炊ける、お風呂も沸かせる。家も建てられるし、生きていく上でのあらゆる繋がりがあります。花粉問題だって、木を切る人がいれば、むしろ空気の循環を良くしてくれる。林業は大切なんですよね。人間の生活の基盤になっていると思っています。 ですから林業を通して、そこに生活する方たちのほのぼのとした幸福感や満足感を充足したいですし、村おこしといった地域の活性化にも非常に興味があります。 大学では様々な検定試験に挑戦しましたが、授業では学べないところまで教えてもらいました。先生方の技術が素晴らしいので、安心して学べます。私はこうした知識や技能・技術は、いずれどこかの場面で役立つと思っています。自分と仕事、自分と社会を繋ぐ力です。その力がないと新たな価値の創造なんてできないです。 視野が広がり、自分の進むべき道を見つけた大学での4年間。いまは卒業制作に仲間と懸命に取り組んでいます。一般家庭のエントランスと庭づくりです。次のステップへ進むために!!! 関連リンク 建設学科WEBページ