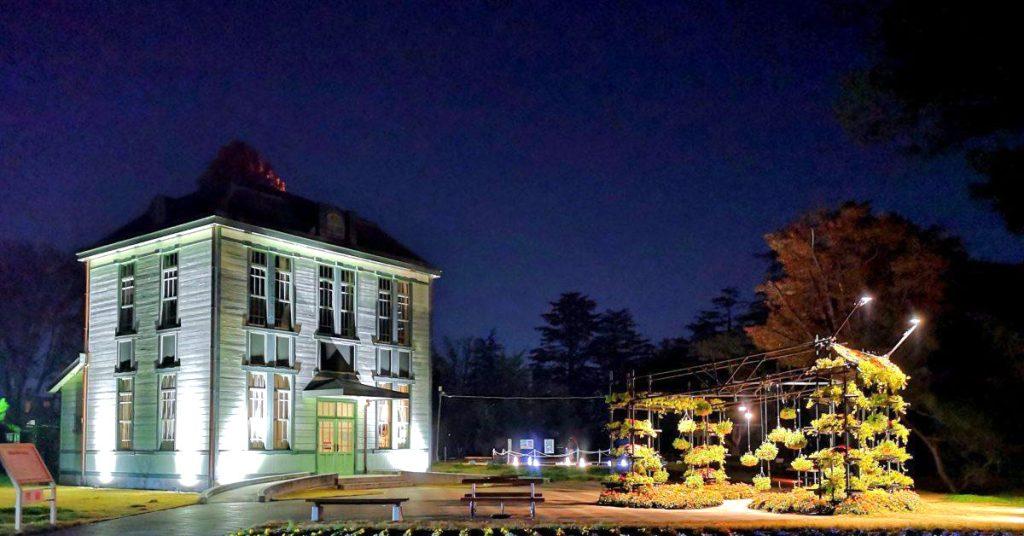#4年生
- 新着順
- 人気順
-
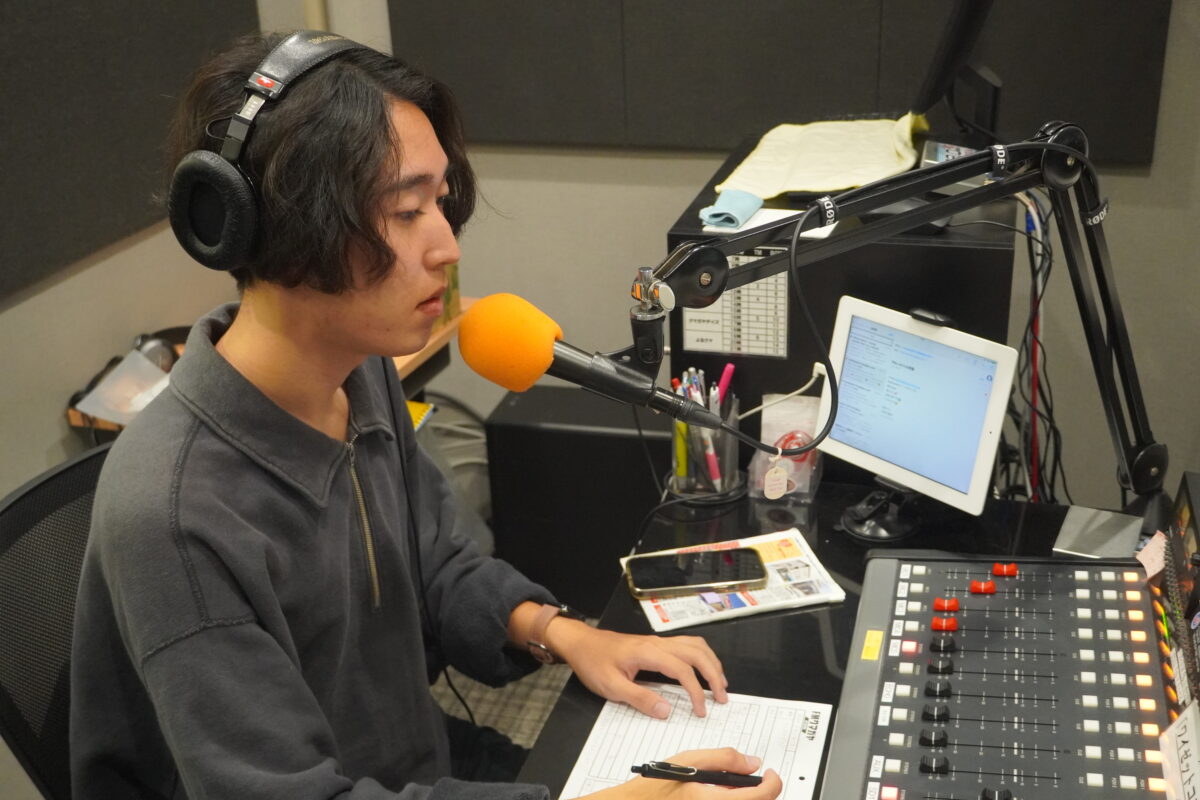
手を動かす「ものづくり」から、考える「仕組みづくり」に~料理研究サークル、ラジオパーソナリティー、そして商店街の活性化に取り組んで見えたこと~
Introduction 学内外で多岐にわたる活動に取り組んでいる和田燿(ひかる)さん(建設学科4年・田尻研究室)。ラジオパーソナリティーなど、ものつくり大学の学生として稀有な分野に挑戦してきた和田さんにインタビューしました。 やりたいことを実現できる環境があるものつくり大学 現在、田尻研究室でまちづくりの一環として商店街の活性化プロジェクトに取り組んでいるほか、料理研究サークルの代表やFMクマガヤのラジオパーソナリティーとして活動しています。この大学生活を通じ、ものつくり大学には「やりたいことを実現できる環境」が存在し、意欲と行動が伴えば、教職員の方から地域の方まで誰でも協力してくれると実感しています。もともと建築系を学びたい気持ちがあり、ものつくり大学を選びましたが、進学の決め手は、オープンキャンパスでの体験でした。特に響いたのは、田尻教授による建設学科の説明と、その後の先輩方によるキャンパスツアーです。先輩方が心から楽しそうに大学の魅力を語る姿は印象に残っています。特に「溶接のいいところ」を熱弁してくださった女性の先輩の姿からは、「本当に好きでやっているのだな」という情熱が伝わってきました。「この大学なら、真に楽しんで勉強できる」と確信し、進学を決めました。 碧蓮祭から誕生した「料理研究サークル」 大学1年で初めて学園祭である碧蓮(へきれん)祭に参加したとき、イベントとしての土台となるステージのイベントや出展物の面白さはずば抜けていると感じました。しかし、イベントに欠かせない飲食店があまり賑わっていない印象を受けました。人が並んでいるのは主に外部からの出店で、学生主体の飲食店の盛り上がりが欠けていたのです。そこで、「自分たちでその盛り上がりをつくろう」と思い、もともと料理が好きだったこともあり、1年生の12月にメンバーを集めて料理研究サークルを立ち上げました。「学祭で学生主体の飲食販売を盛り上げる」ことを目標に掲げました。料理研究サークルの活動を通して、好運な出会いもありました。サークル内でピザを作っていたところ、学生課の職員の方が、行田市内で特色あるピザ屋さんに連れて行ってくれたのです。これがきっかけで、私はそのピザ屋でアルバイトをすることになりました。「ピザが好き」「料理研究サークル」「ものつくり大学」という3つの要素を掛け合わせ、2年生の2023年6月にレンガで「移動式ピザ窯」をつくりました。レンガ1個が2.5㎏あり、合計で300~400個のレンガを買ったのですが、総重量が約1トンにも及び、かなり労働力を要しました。このピザ窯は常設できないため、組み立ててバラす形にしました。ピザ窯は30分ほどで組み立てられますが、建設棟の保管場所から運搬する作業を含めると2~3時間かかります。台車に載せられるだけのレンガを何度も往復して運び、みんなで数100個のレンガを頑張って積む作業をします。 レンガを積み上げて作ったピザ窯 このピザ窯は、碧蓮祭のほか、学内の留学生交流会やサークルの新入生歓迎会など様々なイベントで活躍し、碧蓮祭で飲食販売の盛り上がりをつくることができたと感じています。また、私がかかわっているFMクマガヤや商店街の活性化プロジェクトがきっかけで、大学外にピザを出店することもできました。私たちの出店により、ものつくり大学に興味を持っていただいたり、たくさんの方から純粋にピザの味を喜んでもらえたり、貴重な体験ができました。現在、料理研究サークルのメンバーは20人弱いて、一人ひとりパワーがあります。メンバーはみな決断や行動がスムーズで、課題が生じると自らで解決しようと動きます。対応力や行動力がある主体的なサークルだと感じています。 碧蓮祭でピザを販売する料理研究サークル(中央が和田さん) 碧蓮祭で販売したピザ ピザから繋がったFMクマガヤのパーソナリティー 2024年11月、アルバイト先のピザ屋が市内のお寺の縁日へ出店した際、学生である私のブースを設けてくださり、チャレンジメニューとしてオリジナルピザを販売しました。その時、FMクマガヤのパーソナリティーの方がピザ屋に取材に訪れていました。料理研究サークルを学外にもPRしたいと考えていたので、思い切ってサークルのPR方法について相談してみました。すると、「スタジオにおいでよ」と声をかけていただき、好運にも11月に「週刊フードラボ」という番組にサークルの仲間とゲスト出演することができました。初めてのラジオ出演は、シンプルに緊張しました。目の前にマイクがあるだけでこんなに話す内容が変わるんだという驚きがありました。マイクを前にすると普段の雑談や会話とは全く異なるベクトルが必要だと感じました。「週刊フードラボ」の番組内では、料理研究サークルの活動内容や今後の目標を多くの人に知ってもらえるよう意識して話をしました。翌月の12月には、クリスマスイベントの公開放送にも誘われ出演。そこでFMクマガヤの局長の宇野さんから「パーソナリティーをやってみないか?」と声をかけられました。自分がやれるものだとは思っていませんでしたが、「もらえるチャンスは全部取る」という衝動的な思いから、挑戦を決意。面接後に研修をFMクマガヤの代表の栗原さんから受けました。実際の放送中に受けたミキサー等の機械類の研修では、ミスが生放送に大きく影響してしまったのですが、ミスを受け止めつつ、生放送という場でどうつなげていくかの心構えを学びました。その後、2025年3月にパーソナリティーとなりました。 飾らない大学生の姿が魅力のパーソナリティーでありたい 現在、週2日ほど番組に携わっており、第3火曜日の19時から「りすチャン2025」という番組のナビゲーターも務めています。週に約6時間ものフリートークを行うため、日頃からネタを探し、メモを取るようにしています。思いついたことやあった出来事を箇条書きにし、そこから話を広げています。自分の中で思っているくだらないことを「こうなんですよね」とリスナーに語りかけることで、日常の中から何かをひねり出そうと努めています。夜の番組なので、多少の大学生らしいゆるさは許してほしいという気持ちがあります。大人になると忘れがちな気持ちや、「とりあえずやってみたい」という学生らしさをストレートに受け取ってもらいたいです。飾らない大学生の姿が魅力のパーソナリティーでありたいと思っています。私のように料理研究サークルの活動を外部に広げられたのは、たまたまだと思っています。発信できないだけで、ものつくり大学には木工や、機械いじりといった、各々が持つ個性が溢れています。ラジオという媒体を通じて、そうした学生の魅力を発信し、ものつくり大学の学生の「とがり」を出していきたいです。 学内にFMクマガヤのサテライトスタジオが 今月(2025年10月)からFMクマガヤのサテライトスタジオが学内の図書館・メディア情報センターに設置される予定です。碧蓮祭の1日目である10月25日に公開生放送が行われることになり、話が早く進んでいることに驚いています。私はサテライトスタジオ設置の話を知り、9月にメディア研究サークルを立ち上げ、図書館・メディア情報センター長の井坂教授に顧問をお願いしました。このサークルはラジオに限定せず、メディア全般を取り扱い、学生と地域のつながりを広げていく予定です。サテライトスタジオが実際にどう動くかは未知数ですが、行田とものつくり大学、そして学生の魅力を発信していきたいです。私以外に、主軸に立ってメインで動く学生も見つけていきたいです。こうした活動に前向きな学生が見つかれば、きちんと活動を継続していけると思います。10月25日の公開生放送では碧蓮祭に携わる人や団体の魅力を掘り下げていく予定です。 今までの活動で見えてきたもの 今後は、田尻研究室での取り組みに特に力を注いでいきたいと考えています。建築系を学びたくて進学したものの、サークル活動やラジオパーソナリティなどを通じ、実際に手を動かして「ものをつくる」よりも、いろいろ考えて「仕組みをつくる」ことに興味が移りました。田尻研究室は、物理的な「もの」をつくるような研究ではなく、「基盤の仕組みづくり」の研究室であり、考えることに重きを置いています。まちづくりや都市計画の分野が研究の中心です。私は、商店街の活性化に取り組んでおり、現在、先輩からプロジェクトを引き継ぎ、イベント等を運営する側となっています。この研究室で学ぶ中で、これからやるべきことも見つかりました。まずは学部卒と名乗るだけの能力を身に付けるために学びを深めたいです。また、以前は施工監理といった職種しか考えていませんでしたが、それ以外の可能性もあることを知りました。本当に自分がやりたいことを見つけるために、大学院へ進学し、より深く専門的な知識と考える力をつけたいと考えています。 挑戦や行動力の原点は「興味」 現在に至るまでの大学生活での挑戦や行動力の原点は、単純に「興味」です。「やったことのないこと」「簡単にやれないこと」をやってみる気持ちが強いです。料理研究サークルをつくったことが全てのはじまりでしたが、ラジオのパーソナリティーにしても、一つずつ行動したことに対して評価され、誘っていただく機会に恵まれました。一個ずつやったことに対して派生していった結果、今があります。これからは、今まで培った力や縁の一つ一つを大切にしつつ、田尻研究室の一員として研究活動を追求できればと思います。大学生活は「何もしないのはもったいない」と強く思います。なにかに興味をもち、やりたいと思ったら、まずはいったん口に出し、人に話してみることが大切です。たとえ無理そうでも、夢物語でも、話してみることで周囲の協力が集まり、話はどんどん広がっていくと実感しています。 関連リンク ・建設学科 まちづくり研究室(田尻研究室)・ものつくり大学料理研究サークル(@iot_oryouri)-Instagram
-

人と違うことをやってみる!伝統的な技法「扇垂木」への挑戦が自分自身の成長に
寺社建築の伝統的な技法「扇垂木(おうぎだるき)」と呼ばれる屋根架構を卒業制作のテーマにし、千葉県妙長寺の本堂建築に携わった桐山実久さん(建設学科4年・小野研究室)。 念願だった技能五輪全国大会にも2度出場した経験を持ち、「やってみたいことは挑戦する」がモットー。桐山さんに卒業制作を通して実感している4年間の大学生活での学びや成長、将来の目標などのついてインタビューしました。 木造建築への熱意がものつくり大学進学に 幼い頃から、温かみを感じる木造の家が好きで、木造建築に興味がありました。高校は地元の愛媛県立吉田高校の機械建築工学科に進み、木造建築の面白さに魅了され、高校生ものづくりコンテストにも出場しました。ものつくり大学に進学したのは、同校の先輩が進学していて「技能五輪全国大会に出場できるチャンスがある」と話を聞いたことが大きかったです。ものつくり大学では、アーク溶接などにも触れましたが、やはり木造建築が好きだということを確信し、木造建築コースに進みました。木材の魅力は一度切ると元に戻せないところだと感じます。ボンドで貼っても再生できないですよね。 1年生の頃はコロナ禍でオンライン授業が中心の学生生活に。2年生、3年生の時に連続して技能五輪全国大会に出場しました。出場職種は得意分野の大工ではなく、敢えて家具に挑戦しました。高校時代に先生から「細かいものも得意だね」と言われたことがあったからです。2年生の頃はまだ授業で家具づくりを学んでいなかったため、先輩方にいろいろ教えていただき、寝る間も惜しんで工房で技術を磨き大会に臨みました。3年生の時も家具職種に挑み、努力が実り敢闘賞を受賞することができました。ものつくり大学に進学し、念願だった技能五輪全国大会に挑戦できたことで、チャレンジ精神が旺盛になりました。 技能五輪全国大会に挑戦する桐山さん 伝統的な技法「扇垂木」を卒業制作に 私は小野研究室なのですが、今井研究室と仲が良く、交流が盛んな環境に身を置いています。4年生で卒業制作を迷っていた時、インターンシップでお世話になった今井先生から「千葉県館山市妙長寺の本堂新築の屋根架構を卒業制作として取り組んでみないか」と声をかけていただきました。今井先生から、本堂の屋根の形状は扇垂木(おうぎだるき)という唐傘をモチーフにした扇状に広がった垂木のことで、非常に手間がかかり、単純に配置することが難しいことや、現役の大工さんでも経験できないまれな技法であることなどの説明を受けました。 学生生活の中で木造建築を中心に学び、大会などにも挑戦してきた経緯もあり「人と違ったことをやってみたい」という思いが強い私は「滅多にない経験ができるのは面白そう」と伝統的な技法である扇垂木の制作に挑戦したいと思いました。そして「館山市妙長寺の屋根架構の制作ー扇垂木の墨付け、刻み、加工-」を卒業制作のテーマにすることで新たな自分の可能性を見出したいと思いました。 限られた作業時間が没頭するための集中力に 扇垂木の墨付けから加工の工程は、扇垂木の木材加工の施工経験がある非常勤講師の福島先生のご指導の下、埼玉県寄居の福島工務店で行いました。扇垂木の木材となるのは、垂木、隅木、蕪束(かぶらづか)。墨付けから加工は、一般的な垂木の断面より大きいため、加工に費やす時間が多くなりました。搬入や組み立てを考慮して行った鎌継ぎ(一方の木材に端部の広がった突起を作り、他方の木材にはめ込む継ぎ手)やくせ加工などの作業も何度も行いました。作業時間が限られていたこともあり、43日間(2023年10月27日から12月8日)1日も休まず取り組みました。限られた時間の中での作業だったからこそ、集中して一心に取り組めたのだと思います。加工した木材の仕口を数えてみたら136箇所ありました。 技術的な面は、福島先生のご指導に加え、学生生活を送る過程で様々な道具を使ったり、技術を磨いたりした経験や工程を頭に入れ作業する習慣がプラスに働きました。ある程度作業に慣れると、流れが分かり、段取りをつけながら1人で進めることもありました。精神面でのプレッシャーは地元の方との交流もあり、あまり感じませんでした。技能五輪全国大会に出場した時はかなり精神的にきつかったのですが、2度の出場経験により、精神的にも鍛えられたのかもしれません。しかし、肉体的には、かなりハードでした。今まで扱ってきた木材に比べて遥かに大きく、重かったので、運んだり、転がしたりするのは想像以上に身体に負荷がかかり、腰なども痛くなりました。 難易度の高い施工に挑み、目にした本物の建築 木材の加工が終了した翌日の12月9日に、埼玉県寄居町から千葉県館山市の現場に木材を搬入しました。現地の大工さんの力もお借りし、他の学生と一緒に12月13日から、施工に入りましたが、現地に入る前と後では、緊張感が違いました。まず、蕪束と隅木の取り付けを行いました。上段、中段、下段と隅木を継いでいきました。ここでは、ビス留めをし、しっかり止めました。次に、いよいよ垂木の取り付け作業に。隅木側から垂木を取り付ける工程はとても難しかったです。ひのきの垂木は全て寸法も異なり、木材だからこそ、ねじれや乾燥もあり、調整の繰り返しに。なかなか思うように作業が進まず、苦戦しつつも丁寧にかんなを使って微調整しながら組み立てを進めていきました。垂木の上段、下段の取り付けが進んでいくに従い、扇垂木が大きいことに驚きました。 扇垂木を下から見上げる 現場で施工する桐山さん 本物の建物の施工に関わるのは初めてで、しかも寺院の本堂は地域に根付き、歴史的にも価値をもつことになる建物です。いざ完成間近になった建物を目の前にし、「こんなにも大きな寺院をつくっているんだ」と言葉に表せない感情が湧きました。100年、200年と長期間、多くの人に親しんでもらえる建物にしたいと思っています。本堂の完成は2024年3月を予定しており、扇垂木の美しさが見える屋根になるように作業を進めています。 卒業制作を通して感じている自身の成長 卒業制作を通して特に2つほど自身の成長を感じています。1つは、今までは自分が納得いくためのものづくりだったのが、人に喜んでもらえるものづくりをしたいという思いが加わったことです。そもそも、ものつくり大学に進学した理由の1つに技能五輪全国大会への挑戦があったのですが、高校時代に高校生ものづくりコンテストに参加し、自分自身に対してやり残したという後悔がありました。「賞に入賞することよりも自分の納得するものづくりがやりたい」という思いが強く、1年目には納得できず、2年連続して挑戦。結果、3年生の時は敢闘賞を取ることもでき、自分なりに納得し、達成感が味わえました。しかし、今回、長い歳月建ち続けることになる寺院の施工に携わることで、多くの人が見たり、触れたりして大切にされていくことを想像する機会に恵まれ、ものづくりの喜びを倍に感じるようになりました。 もう1つは、自分に自信が持てたことです。大学生活の中でいろいろな大会にも出場し、賞ももらってきたのですが、実は自分に自信が持てず、ものづくりも上手いと思ったことがありませんでした。自己評価が低く、時に先生から叱られることも。自信がなかったからこそ、さまざまなことに挑戦もしてきました。しかし、今回、卒業制作で難易度の高い扇垂木の制作に挑戦し、その結果、檀家さん、工務店の先生、大学の先生や友人など関わってきた人から評価してもらい、自信が持てました。本堂新築における扇垂木のことが新聞に取り上げられたことで、自分が関わった建築物が多くの方から注目を浴びていることを聞き、嬉しいです。 建築が進む妙長寺本堂 将来は木造建築の教員に 大学卒業後は、まず、大工としてプレカットの仕事に就き、大工職人として腕を磨きたいです。社会経験を積んだ後は、木造建築の教員になりたいと考えています。私の家族はみな教員で、幼い頃から「将来は先生になりたい」と思っていました。人に教えることも好きです。ただ、学生生活の中で、自信がなかなかもてず、後輩に対してもどこか教えることに引き気味でした。しかし、卒業制作などに取り組む中で教えることに少しずつ前向きになり、4年生ではSA(Students Assistant)として先生のアシスタントをしながら後輩にさまざまなことを教える経験をしています。実際、鋸の使い方1つでも教える立場になってみて、みんながそれぞれ違う使い方をしていることが分かり、その違いを面白いと感じます。一方で、一緒にSAをしている学生の教え方から学ぶことも多く、勉強になります。最近、木造建築に進む学生が少なくなっていると感じるので、木造建築の魅力や面白さを伝えられる教員になりたいです。 自分を磨けるものつくり大学での学び ものつくり大学での学生生活は、規則に従いながら過ごしていた小中学校時代、まだ何がやりたいかが明確ではなかった高校時代とは異なり、自分が好きなことをできる環境が整っていました。自分が磨きたいところを磨け、いろいろなことにも挑戦できました。先生からは理論や実践で役に立つことを教えてもらい、さまざまな実習やインターンシップでは、自分で実際にやってみる機会を多く作ることができました。具体的に教えていただいたことに挑戦できた結果、多くのことを学んだり、技術や技能を身に付けたりすることができました。さらに、先輩から教えていただき、後輩に教えるものづくりを通し、人とコミュニケーションを持ったり、信頼関係を築いたりする機会にも多く恵まれました。挑戦することを続けた4年間の学生生活の中で、特に卒業制作は、今までの学びと実践が活き、自分自身の成長を感じる機会になっています。 関連リンク ・建設学科 木質構造・材料研究室(小野研究室) ・建設学科 建築技術デザイン研究室(今井研究室) ・技能五輪全国大会実績WEBページ ・建設学科WEBページ
-

【学生による授業レポート #2】受講後もSA(スチューデント・アシスタント)を通じて深める学び
第2回「学生による授業レポート」をお届けします。今回は建設学科4年の杉山一輝さんが「鋼構造物施工および実習」を紹介します。杉山さんは2年次に「鋼構造物施工および実習」を受講して、4年次ではSA(スチューデント・アシスタント)として実習の運営をサポートしました。学生とSAの両方の視点からのレポートをお届けします。(学年は記事執筆当時) 「鋼構造物施工および実習」について 「鋼構造物施工および実習」は、鋼構造の躯体モデルとして鉄骨部材で構成されたシステム建築を施工する工程を通じて、鋼構造部材の組み立てを中心とした施工管理を学びます。高力ボルトなどの締付け管理や母屋、胴縁などのボルトによる施工要領について学び、筋交いやサグロッドなどの2次部材の役目や施工方法を習得します。 システム建築の特徴 この実習は、株式会社横河システム建築から鉄骨などの部材を提供いただくとともに、社員の方に非常勤講師として来ていただき行われています。横河システム建築は、業界トップシェアを誇るシステム建築と、国内外の大型開閉スタジアムやハワイ天文台のすばる望遠鏡大型シャッター装置など、様々な用途の大型可動建築物を提供する建築製品のトップメーカーです。 システム建築とは、建物を構成する部材を「標準化」することにより、「建築生産プロセス」をシステム化し、商品化した建築です。工場・倉庫・物流施設・店舗・スポーツ施設・最終処分場等に適した建築工法で、建設のうえで想定される検討事項・仕様が予め標準化されているので高品質でありながら、短工期・低価格を実現しています。(株式会社横河システム建築HPより引用:https://www.yokogawa-yess.co.jp/yess01/feature) 完成写真 苦労した点、勉強になった点 2年生で受講した時は、システム建築、鉄骨造と聞いてもイメージが全然湧きませんでした。図面を見て理解するにも時間がかかって施工するにもいろいろ苦労しました。しかし、世の中の鉄骨造の建築物(特に工場・倉庫)はどのように施工されているのかを細かな部分まで実習を通して知ることができ、完成に近づくほど楽しく、面白く感じました。「システム建築」がどのような事なのかも学ぶことができました。 図面確認 3年生になり、SA(スチューデント・アシスタント、以下SA)になってからは、受講生に質問されてもしっかり答えられるように図面をよく確認したり、作業内容を熟知するようにして事前準備をしていました。現場は予定通りにいかないことが多いので臨機応変に対応していくのが大変でした。SAとして、また実習に参加することで、受講当時に分からなかったことが理解できるようになったり、新たな疑問点は見つかったり、毎回の実習が充実していたので参加できて良かったと思います。 SAとして工夫した点 就職活動では、株式会社横河システム建築から内定をいただいたということもあり、SAを2年間経験させてもらっています。一般的にSAという立場は、受講生のサポート役として参加しますが、この実習では規模が大きいということもあり、SAが率先して受講生をまとめています。受講生では危険な作業が少々あり、SAがやらなくてはいけない作業があったりするからです。 工夫したことは、その場その場でいろいろとあります。教授・非常勤講師の打ち合わせに参加して、実習で使用する工具類の確認、授業の流れを把握したりして受講生がスムーズに実習できるように環境づくりを行いました。また、複数人いるSAの中でリーダーでもあったので指示を出したり、自身の分からないことはすぐに非常勤講師に質問して対応できるようにしていました。 SAによる柱設置作業 原稿建設学科4年 杉山 一輝(すぎやま かずき) 関連リンク ・【学生による授業レポート】ジジジジッ、バチバチッ・・・五感で学ぶ溶接技術・建設学科WEBページ
-

目指すはベトナムと日本の架け橋。いつか強みを生かして、新たなキャリアにステップアップしたい
ベトナム出身のヴ―・ディン・ズーンさん(総合機械学科4年生)は、中学時代よりテレビで知った日本文化や日本社会に親しみを持ち、また有形の製品を扱い、「自身の仕事が形になっている」という実感を得られる日本の製造業に大きな期待や希望を抱いていました。 3年間の日本語学習を経て、ものつくり大学へ入学。2023年度4月からは日本での就業をスタートさせます。留学生だから感じる様々な課題を持ち前の明るさと好奇心で乗り越えてきたズーンさんの今後の目標や夢はなにか。後輩へのメッセージと共にお届けします。 ベトナム社会の発展に尽力されているホエ先生との出会い ベトナム、ホーチミン市にあるドンズー日本語学校のグエン・ドク・ホエ先生との出会いが、日本に留学するきっかけとなりました。ホエ先生は、国費留学生として1959年から74年まで、京都大学と東京大学大学院に在籍していた方で、帰国後、独自の日本語学習法をベトナム人向けに編み出し、約30年で2千人以上を日本に留学させてきた方です。一貫して日本語の普及に尽力してきた功績が認められて、2019年には日本政府から外務大臣表彰、2021年には外国人叙勲で旭日小綬章を受章されています。それほど素晴らしい先生です。 私の実家はハノイから約150キロ離れたところですが、ホエ先生は各地の高校を訪ねて優秀な学生にドンズーで日本語を勉強し留学しないかと進めていました。ベトナムでは農業が主で、大きな機械を使った製造業はハード&ソフト共に後れていました。テレビで見た日本の機械の優秀さや頑丈さに感心して、もともと中学時代に日本の歴史や文化に親しみがあり、製造業に興味があったので、いずれは留学したいと思っていました。それでホエ先生の学校で日本語を学んでから、来日して日本語学校で2年経過してから、ものつくり大学総合機械学科へ入学しました。 日本語を学んできたとはいえ、入学してから多くの日本の友人や知り合いを作ることで、ようやく日本語が堪能になっていきました。人見知りしない性格なので、どんどん興味あることに飛び込んでいったのです。しかし、筆記試験には苦戦しました。読み書きはもちろん出来るのですが、漢字圏の外国人の方に比べると不利かな・・・と。そこが苦労した点ですね。 とにかくモノをいじりまわし、作り上げることが好き 大学では、フライス盤、旋盤など工作機械を使えるようになり、資格を取得しながら学んできました。機械システムと電気システムおよび情報システムの搭載されているコンピュータシステムも学び、ハードウェアとソフトウェア、両面の開発も学んできました。卒業研究では『インピーダンスマッチングを考慮に入れた人力発電装置』という題目で取組み、成果発表を行いました。これはキックボードの普及に向けた充電器の需要が高まっている現状で、自分で自分のキックボードを充電できる設備があれば誰でも楽に発電することができると考えました。 インピーダンスとは、回路と回路を伝送路で結ぶとき、回路のインピーダンスが異なると、信号電流の一部が反射されてノイズとなったり、出力が低下したりします。この不整合を解消するのがインピーダンスマッチングです。そのことを考慮しながら、人力による発電機の開発に取り組みました。ペダル的なものを漕いで、発電させるもので、負荷もかけられるので軽い運動にも最適です。そのため強度が重要でした。また100ボルトのコンセントも設置して、スマホ充電器にも活用でき、アウトドアや災害時などでも運動を兼ねて使用することができるように開発しました。自分で言うのもなんですが、発想は面白いと思っています。 また学業以外の活動では、チューターをしていました。4年生ではスチューデントアシスタント(SA)。留学生のための国際交流サークルやバドミントンサークルに入っていました。 人が好き!出会った人との距離をもっともっと近くへ!! プライベートではスピーカーを製作したり、オートバイを改装したりして楽しんでいます。しかも完成はないので、永遠に作業をして常にアップロードしています。製作したスピーカーでは、母国ベトナムの音楽を聴いています。改装したオートバイに乗車して仲間たち4人と静岡へツーリングに行きました。ツーリングは楽しかったですが、残念ながら車検切れで今は乗っていません。思い返せば、「ものづくり」に励んできた4年間でした。性格なので、これからもきっとやめられないんでしょうね(笑)。 また、ベトナムフェスティバル in 神奈川の実行委員として活動。同じ川崎市で多文化共生推進事業活動やベトナム支援会で活動しています。神奈川県では県内に暮らすベトナム人や訪日ベトナム人観光客が増加していて、将来にわたる両地域の継続的な成長と発展を図っています。その一助になればと活動しています。 それから日本ボビナム協会の会員になって活動をしています。ボビナムとはベトナムで生まれ、世界60カ国に広がる総合武術です。加盟国はアジア各国はもちろん、ヨーロッパ、中東、オーストラリア、アフリカ、アメリカと全世界に広がりをみせています。創始者グェン・ロックさんにより1938年に設立。東洋の中国拳法、古武術などと西洋のレスリング、キックボクシングなどがベトナム人によって研究、分析され、練り上げられた、個性的かつ合理的な総合武術です。これまでに上野公園で行われたベトナムフェスティバルや靖国神社奉納演舞などに参加して、身に付けた技を見ていただいています。ドンチャンと呼ばれる美しい足技の数々も、ボビナムの特色です。日本でも技の名前や用語などはベトナム語を使い、ベトナムで培われた文化と精神を尊重しています。 このように性格はアクティブでアグレッシブです。とにかく人が好きです。人とかかわりを持つことが楽しいです。一対一でも複数でもOKです。出会ってからお互いの距離が縮まることが嬉しいです。もっともっと距離感を縮めて、一緒に人生を楽しみたい気持ちが強いです。人から向上心、好奇心が旺盛だね、とよく言われます。自分でもそう思いますし、素晴らしい長所だと思っています。これが個性ですね。他の人も、様々な素晴らしい個性をお持ちなので、そうした出会いをもっともっと、この日本で経験したいと思っています。 大好きだった日本―来日をきっかけに日本で働きたいと強く思った 卒業後は日本企業に従事します。いずれは母国と製造業の可能性を幅広く事業展開出来たら一番嬉しいですし、将来的にそこに関わりたいと思っています。ベトナムはとても成長していける国でもあるので、これから何年かかけて学ぶことを糧にして、母国のベトナムだけでなく、日本と海外の架け橋になりたいとも思っています。 まずは両国の橋渡しができる人物になりたいと大きな夢を抱いていますし、すごく自分に期待しています。そして自分のことだけでなく、社会のためを思うこと、そして未来の指導者として両国で頑張りたいです。ですので、ホームは日本でもベトナムでもどちらでもよいと思っています。諦めずに、いつか必ず乗り越えられる、今じゃなければ明日がある、ゴールとなる日が必ず来ると信じていれば乗り越えられると思っています。何が必要なのか、何をすべきなのか考えることも多くあり、いろいろな対応を求められると思いますが、逆にそれは嬉しいです。外国人だから、若いからとか一切関係なく、意見や考えを取り入れてもらえたり、毎日違うことをやることで成長できると信じています。 後輩たちには、目的を持って留学しないとダメと言いたいです。日本語を学ぶことも、大学の学修も、日本社会へ溶け込むことも、ぜんぶ夢や目的のためでないと続きません。色々な方のサポートを受けて、それを感謝し、成果でお応えする。そうした考えを持って、日々研鑽することがとても重要だと思います。 皆さん、私に続いてください。わからなければ、私に声かけてくださいね。それでは、 Anh đợi em( アン ドイ エン)! 関連リンク ・情報メカトロニクス学科WEBページ
-

震災復興の願いを実現した「集いの場」建設
村上 緑さん(建設学科4年・今井研究室)は、2022年3月下旬、ある決意を胸に父親と共に大学の実習で使用した木材をトラックに積み込み、ものつくり大学から故郷へ出発しました。それから季節は流れて、11月末。たくさんの人に支えられて、夢を叶えました。 故郷のために 村上さんは、岩手県陸前高田市の出身。陸前高田市は、2011年3月11日に発生した東日本大震災での津波により、大きな被害を受けた地域です。全国的にも有名な「奇跡の一本松」(モニュメント)は、震災遺構のひとつです。当時住んでいた地域は、600戸のうち592戸が全半壊するという壊滅的な被害を受けました。 奇跡の一本松 11歳で震災体験をし、その後、ものつくり大学に進学し、卒業制作に選んだテーマは、故郷の地に「皆で集まれる場所」を作ること。そもそも、ものつくり大学を進学先に選んだ理由も、「何もなくなったところから道路や橋が作られ、建物ができ、人々が戻ってくる光景を目の当たりにして、ものづくりの魅力に気づき、学びたい」と考えたからでした。 震災から9年が経過した2020年、津波浸水域であった市街地は10mのかさ上げが終わり、地権者へ引き渡されました。しかし、9年の間に多くの住民が別の場所に新たな生活拠点を持ってしまったため、かさ上げ地は、今も空き地が点在しています。実家も、すでに市内の別の地域に移転していました。 そこで、幼い頃にたくさんの人と関わり、たくさんの経験をし、たくさんの思い出が作られた大好きな故郷にコミュニティを復活させるため、元々住んでいた土地に、皆が集まれる「集いの場」を作ることを決めたのです。 陸前高田にある昔ながらの家には、「おかみ(お上座敷)」と呼ばれる多目的に使える部屋がありました。大切な人をもてなすためのその部屋は、冠婚葬祭や宴会の場所として使用され、遠方から親戚や友人が来た時には宿泊場所としても使われていました。この「おかみ」を再現することができれば、多くの人が集まってくると考えたのでした。 「集いの場」建設へ 「集いの場」は、村上さんにとって、ものつくり大学で学んできたことの集大成になりました。まず、建設に必要な確認申請は、今井教授や小野教授、内定先の設計事務所の方々などの力を借りながらも、全て自分で行いました。建設に使用する木材は、SDGsを考え、実習で毎年出てしまう使用済みの木材を構造材の一部に使ったほか、屋内の小物などに形を変え、資源を有効活用しています。 帰郷してから、工事に協力してくれる工務店を自分で探しました。古くから地元にあり、震災直後は瓦礫の撤去などに尽力していた工務店が快く協力してくれることになり、同級生の鈴木 岳大さん、高橋 光さん(2人とも建設学科4年・小野研究室)と一緒にインターンシップ生という形で、基礎のコンクリ打ちや建方《たてかた》に加わりました。 地鎮祭は、震災前に住んでいた地元の神社にお願いし、境内の竹を四方竹に使いました。また、地鎮祭には、大学から今井教授と小野教授の他に、内定先でもあり、構造計算の相談をしていた設計事務所の方も埼玉から駆けつけてくれました。 基礎工事が終わってからの建方工事は「あっという間」でした。建方は力仕事も多く、女性には重労働でしたが、一緒にインターンシップに行った鈴木さんと高橋さんが率先して動いてくれました。さらに、ものつくり大学で非常勤講師をしていた親戚の村上幸一さんも、当時使っていた大学のロゴが入ったヘルメットを被り、喜んで工事を手伝ってくれました。 建方工事の様子 大学のヘルメットで現場に立つ村上幸一さん 2022年6月には、たくさんの地元の人たちが集まる中で上棟式が行われました。最近は略式で行われることが多い上棟式ですが、伝統的な上棟式では鶴と亀が描かれた矢羽根を表鬼門(北東)と裏鬼門(南西)に配して氏神様を鎮めます。その絵は自身が描いたものです。また、矢羽根を結ぶ帯には、村上家の三姉妹が成人式で締めた着物の帯が使われました。上棟式で使われた竹は、思い出の品として、完成後も土間の仕切り兼インテリアとなり再利用されています。 震災後に自宅を再建した時はまだ自粛ムードがあり、上棟式をすることはできませんでした。しかし、「集いの場」は地元の活性化のために建てるのだから、「地元の人たちにも来てほしい」という思いから、今では珍しい昔ながらの上棟式を行いました。災いをはらうために行われる餅まきも自ら行い、そこには、子どもたちが喜んで掴もうと手を伸ばす姿がありました。 村上さんが描いた矢羽根 餅まきの様子 インテリアとして再利用した竹材 敷地内には、東屋も建っています。これは、自身が3年生の時に木造実習で制作したものを移築しています。この東屋は、地元の人たちが自由に休憩できるように敷地ギリギリの場所に配置されています。完成した今は、絵本『泣いた赤鬼』の一節「心の優しい鬼のうちです どなたでもおいでください…」を引用した看板が立てられています。 誰でも自由に休憩できる東屋 屋根、外壁、床工事も終わった11月末には、1年生から4年生まで総勢20名を超える学生たちが陸前高田に行き、4日間にわたって仕上の内装工事を行いました。天井や壁を珪藻土で塗り、居間・土間のトイレ・洗面所の3か所の建具は、技能五輪全国大会の家具職種に出場経験のある三明 杏さん(建設学科4年・佐々木研究室)が制作しました。 「皆には感謝です。それと、ものを作るのが好きだけど、何をしたらいいか分からない後輩たちには、ものづくりの場を提供できたことが嬉しい」と話します。そして、学生同士の縁だけではなく、和室には震災前の自宅で使っていた畳店に発注した畳を使い、地元とのつながりも深めています。 こうして、村上さんの夢だった建坪 約24坪の「集いの場」が完成しました。 故郷への思い 建設中は、施主であり施工業者でもあったので、全てを一人で背負い込んでしまい、責任感からプレッシャーに押しつぶされそうになった時もありました。それでも、たくさんの人の力を借りて、「集いの場」を完成させました。2年生の頃から図面を描き、構想していた「地元の人の役に立つ、家族のために形になるものを作る」という夢を叶えることができたのです。また、「集いの場」の建設は、「父の夢でもありました。震災で更地になった今泉に戻る」という強い思いがありました。「大好きな故郷のために、大好きな大学で学んだことを活かして、ものづくりが大好きな仲間と共に協力しあって『集いの場』を完成させることができ、本当に嬉しいです」。 「こんなにたくさんの人が協力してくれるとは思っていなかった」と言う村上さんの献身的で真っすぐで、そして情熱的な夢に触れた時、誰もが協力したくなるのは間違いないところです。 「大学から『集いの場』でゼミ合宿などを開きたいという要請には応えたいし、私自身が出張オープンキャンパスを開くことだってできます」と今後の活用についても夢は広がります。 大学を出発する前にこう言っていました。「私にとって、故郷はとても大切な場所で、多くの人が行きかう町並みや空気感、景色、におい、色すべてが大好きでした。今でもよく思い出しますし、これからも心の中で生き続けます。だけど、震災前の風景を知らない、覚えていない子どもたちが増えています。その子どもたちにとっての故郷が『自分にとって大切な町』になるように願っています」。 村上さんが作った「集いの場」は、これからきっと、地域のコミュニティに必要不可欠な場所となり、次世代へとつながる場になっていくでしょう。 関連リンク 建設学科WEBページ 建設学科 建築技術デザイン研究室(今井研究室)
-

ぼくが旅に出る理由 モバイルハウスで日本一周
ものつくり大学が2010年度から主催している「高校生建設設計競技」の2022年度の課題は「これからのモバイルハウス」です。「モバイルハウス」は、新型コロナウイルスがまん延し、人々の行動が制限されてしまった昨今、3密を避けられることからブームになったアウトドアと共に注目されている、「自由に移動できる家」です。設計ではなく、実際に軽トラックの荷台に居住空間を載せて作ったモバイルハウスで、日本一周に挑戦した学生がいます。渡邊 大也さん(建設学科4年・今井研究室)は、2022年の7月に盛暑の東日本を縦断。その後、9月から10月にかけて西日本を横断しました。渡邊さんは、どうしてモバイルハウスを作ったのか、なぜ日本一周の旅に出たのか、その理由に迫ります。 モバイルハウスを作ったきっかけ 運転免許取得時に、祖父から譲り受けた20年ものの軽トラックの荷台を何かに活かしたかったのが、そもそもの始まりです。最初は、大好きなヒマワリを皆に見てもらうために荷台で育てていましたが、大学1年の2月頃から新型コロナウイルスが拡大し始め、2年生の最初の頃は全ての授業がオンライン授業になりました。そこで、「オンラインならば全国を旅しながらでも授業を受けられるんじゃないか」と思い立ち、モバイルハウスの制作が始まりました。 子供の頃から旅行やキャンプが大好きで、高校生の時に、小口良平さんの「スマイル!笑顔と出会った自転車地球一周157カ国、155,502㎞」という本を読んでから、バックパッカーになるという夢を持っていました。そして、モバイルハウスを作った理由としてもう一つ、「元々、ものを作るのは好きだったけど、大きなものを完成させたことが無かったので、10代最後の挑戦にしたい」という思いがありました。 大学2年の夏からモバイルハウスの制作が始まりました。最初の頃は夢が膨らみすぎて、天井部分に芝生を植える等、完成した今となっては非現実的なアイデアもあり、納得のいくモバイルハウスが完成した時には大学4年生になっていました。 モバイルハウスの図面 制作中のモバイルハウス モバイルハウスのこだわり モバイルハウスは「海と船」をモチーフにして作られています。山梨出身で大学は埼玉。身近に海がない環境で育ったため、海に憧れを抱いていました。 モバイルハウスの助手席側の窓は、実際に船舶に使われている丸窓が入り、運転席側の窓は、旅先で海を眺めることを想定して、白く大きな窓を採用しています。また、屋根の部分は波をモチーフにして木材を加工しています。 制作にあたっては、大学の授業を応用して一人で制作を進めました。作り始めた頃は、モバイルハウスを作って旅に出ようとしている事を友人に話しても、皆から笑われたり、「やめときなよ」を言われました。しかし、完成が近くなってきて、本気さが伝わると、友人たちが最後の仕上げを手伝ってくれました。 旅での経験 完成したモバイルハウスで、いよいよ日本一周の旅に出発します。東日本に1か月、西日本に1か月半ほどの旅でしたが、どこに行くのか事前に計画は立てず、行先を決めるのは前日の夜。 世界遺産検定3級を持っていて、今回の旅には国内の世界遺産を巡るという目的がありました。日本を一周する中で、日本にある25件の世界遺産のうち10件を訪ねました。これで、未訪問の世界遺産は残り4つです。 大浦天主堂(長崎県) 白川郷(岐阜県) 他にも、旅にノルマ的なものを課していて、「建築・グルメ・文化」のうち、2つを堪能したと思えたら、次の場所に移るというものでした。 今回の旅で思い出に残っている場所は、モバイルハウスを作ったら絶対に行きたいと思っていた石川県の千里浜です。千里浜なぎさドライブウェイは、日本で唯一、一般の自動車やバイクでも砂浜の波打ち際を走れる道路です。海に憧れ、「海と船」をモチーフにしたモバイルハウスを作ったからには、是非とも写真に納めたい場所でした。ちなみに、石川県では、近江町市場の海鮮料理やターバンカレーを堪能して、兼六園や金沢21世紀美術館を訪ねました。 他にも、鹿児島県の桜島も印象に残る旅先でした。山梨で育ったため、山は見慣れていますが、山の形がまるで違っていて、ちょうど噴火していた桜島の雄大さが心に残っています。 旅の最中には、様々な人と出会い、繋がりもできました。特に、広島を旅していた時には、モバイルハウスを作りたいと考えている長崎から来た人に話しかけられ、ちょうど卒業研究用に作っていた資料を渡したことから意気投合しました。「今度、長崎に来る時は案内するよ」と言われたことで、実際に訪ねてみました。 また、千葉を旅している時は、所属する研究室の今井教授から「私の実家に行っていいよ」と連絡があり、実際にお風呂を借り、ご飯をごちそうになりました。 鳥取で台風に遭った時は、体育館に開設された避難所に行きました。避難しているのは一人だけでした。1か月という長い間、1.3畳ほどのモバイルハウスで生活していたため、広い体育館で一人になり、不意に寂しさを覚えました。寝れずにいたら、避難所の管理人の方が話しかけてきてくれて、夜遅くまで旅の話を聞いてくれました。 モバイルハウスの後方に「日本一周」と看板を掲げていたので、行く先々で話しかけてもらいました。長野の道の駅で同じように旅をしている方から素麺をごちそうになったり、途中で寄ったコンビニのオーナーから差し入れをいただいたりした事もあります。追い越していったバイクの方に手を振られる等、人の優しさに触れることができた旅でした。 モバイルハウス後方 長野でいただいた素麺 トラブルも数多くありました。一人旅だから何かあっても、自分で何とかするしかありません。佐賀の山を走っていた時に、エンジンオイルランプが点灯した上にガス欠になりかけていたところ、更にぬかるみでスタックした時は、山中に一人の状況に絶望して思わず叫びそうになりました(笑)。事前に、自動車部の友人から、オイルの入れ方やスタックした時の対処法を教えてもらっていたので何とかなりましたが、本当に怖かったです。 これからのモバイルハウス いつかモバイルハウスで海外に行き、高校生の時に留学していたアメリカのテネシー州まで旅をして、ホストファミリーを驚かせるという野望を持っています。 モバイルハウスで旅をする中で、「モバイルハウスがあれば家はいらない」と考えるようになりました。先日、モバイルハウスを所有している人たちの集まりがありました。夫婦二人と犬一匹でモバイルハウスに暮らしている方と出会い、モバイルハウスの可能性を感じました。軽トラックだと居住空間は狭いですが、1トントラックや2トントラックの荷台であれば、居住空間も広くすることができます。 実は、旅が終わった今も、ほとんどアパートで寝ることはなく、最後にアパートで寝たのはいつか分からないくらい、モバイルハウスか研究室に寝泊まりする日々が続いています。 日本ではモバイルハウスはかなり珍しい車ですが、車幅以内、高さ2.5m以内、350㎏以内であれば、自分の好きなように作れます。荷台に居住空間を荷物として載せているだけなので、特に手続きも必要ありません。制約があるからこそ、作っていて面白いと感じていて、モバイルハウスをもっと広めたいと考えています。 旅とは「生きがい」です。小さい頃から安定が好きではなく、刺激を求めていて、何をしても結局、旅に繋がります。就職先は、全国に支店がある内装工事の会社から内定をもらいましたが、転勤についても全国色々なところで建築に関われるので、今から楽しみです。 関連リンク 第12回ものつくり大学高校生建設設計競技 建設学科 建築技術デザイン研究室(今井研究室) 建設学科WEBページ
-

現場体験で感じた林業に魅了されて・・・第二の故郷へ就く
林業の機械化が進んだことで、素材生産や森林調査等で女性が活躍する場が増えています。とはいえ、まだまだ3K(きつい、汚い、危険)のイメージは拭えません。その林業の現場に大きな夢を抱いて挑戦する女子学生がいます。 例えば、京都を代表する銘木「北山杉」。古くから北山林業では女性は重要な役割を担っていました。枝打ちや伐採は男性の仕事ですが、加工作業や運搬、苗木の植え付けは主に女性の仕事でした。では、現代の林業女子には仕事はないのでしょうか。近年は機械化が進むことで伐採等の林業現場へも女性が進出することが期待されています。その林業に挑戦する浅野 零さん(建設学科4年)。153㎝の華奢なカラダからは想像できないバイタリティーの源はなにか、感動のインタビューです。 浅野さんのチャレンジ魂を育てたものは何ですか 高校までものづくりとは縁がなかったです。茨城県の生まれですが、小学校4年から中学卒業まで長野県にある人口850人程の村へ山村留学していました。高校は山口県でした。田舎が好きで、今度は瀬戸内海の島でした。山から海へ、です。高校時代は、アーチェリー部に所属していました。強化指定を受けていたことで、3年生では選手として全国大会へ出場しています。強いてものづくりと縁があるなら、山村留学時に仲間と小屋を作ったことでしょうか。その楽しかった思い出は心のどこかにずっとあって、このエピソードはものつくり大学へ進学する時に大学の方にお話しました。大学からすると、私の志望動機が不思議に思えたようでした。 そもそも母の影響というか、子育て方針というか、兄も同じ村に先に山村留学していて、後にカナダへ海外留学をしました。私は茨城→長野→山口→埼玉と国内を巡っていますが、この度、就職で長野へ戻ります。それも山村留学でお世話になった同じ村に戻ります。何でしょうね、Uターンでもなく、Iターンでもなくて。 大学での4年間もパワフルだったのではないですか もちろん普通高校卒なので、ものづくりを学んだのは入学してからです。木に触れることは好きだったので、最初は木工家具の製作に憧れました。角材を加工する授業は楽しかったけれど、そのうち角材になる前の木自体に興味が湧いてきて、林業を意識するようになりました。 1年の秋に「林業体験」のイベントを探して個人で参加しました。木を切って、加工して、その凄さに憧れました。女性も参加しやすいイベントで、参加したのは大方女性でした。人生で初めてチェンソーを使って、木を切りました。そして、垂直に立てた木の幹に切り込みを入れて燃やし、手軽に焚き火が楽しめるスウェーデントーチでの料理を楽しみました。 これをきっかけに林業界への憧れが強くなり、将来仕事として就きたいと思うようになりました。2年次に実施される大学のインターンシップは、長野県飯山市のNPO法人で木材加工に従事しました。3年次では、進路を林業一本に絞ったため、個人的に様々な企業や現場を見学に行きました。そういう意味では決断も早く、行動力もありましたね。いま思えば大学の授業との両立もうまく対処していたように思います。 自らの進むべき道を見つけるまでに、どんな出会いがありましたか 大学では就活を意識した活動と共に、1年次で建築大工3級、2年次で左官2級、造園3級、3年次で造園2級と、とにかく木に関わる資格を取得していきました。生活全てを木に関わっていきたい思いが強かったです。 実は、高校時代に生活していた山口県の林業会社の方に「この世界、女性ではたいへんだけれど、男性とは違う視点で活躍している方がたくさんいるよ」と言われました。その林業会社の方にはオンラインで頻繁に相談に乗っていただきました。「山口においでよ」と何度もお誘いをいただきました。正直、山口へ移住しようという気持ちにもなりました。同時に長野とも連絡を取っていて、情報収集に努めていました。 林業は、国の重要な施策なので、どちらかと言えば昔ながらの堅苦しいイメージを持っていました。でも、民間の小さな林業会社では、自分の技術やスキルがついたらやりたいことをやらせてもらえるような新しい考え方も生まれてきていることを知りました。長野で林業を起業された社長さんと話していると、ぐいぐい引き込まれていきました。その将来を見据えた魅力たっぷりの内容に感激しました。 そして最終的に長野へ就職を決めたのですか もちろん企業方針を何度も聞いて、性格的に合っているなと思いましたし、私が内定をいただいた会社がある村は、小学生の山村留学でお世話になったところでした。この村は私にとって特別です。住むことができる、仕事をすることができるなら恩返しの気持ちを持って戻りたいと強く思いました。会社も林業としては2021年に法人化されたばかり。不思議な縁を感じて、お世話になった村へ帰ろうと思いました。 林業女子としての不安や期待はありますか 林業は3Kと言われます。きつい、汚い、危険ですね。それに林業の現場に出る女性としての問題は、まずトイレ。いまは自然保護の観点から、以前のような現地で処理するようなことは減ってきています。トイレの設置や、山を下って用を足すこともできます。それから力の強さですね。女性ですので、体力は男性と比べて見劣りします。でも機械化も進み、力の問題も徐々に解決してくれそうです。緑の雇用制度で3年間鍛えることができるので、いまはそれが楽しみでなりません。都会にある林業会社では、近年「かっこいい林業」をスローガンにして新しい「K」が生まれています。期待ということでは、いずれキャンプ場を作るという会社の重点方針があります。いまは力不足ですが、ぜひチャレンジしたいです。 林業を通して、森林と地域との新たな価値を創造する繋ぎになるということですね 日本は平野の少ない森林大国です。木があれば、火を起こせる。火を起こしたら、ごはんも炊ける、お風呂も沸かせる。家も建てられるし、生きていく上でのあらゆる繋がりがあります。花粉問題だって、木を切る人がいれば、むしろ空気の循環を良くしてくれる。林業は大切なんですよね。人間の生活の基盤になっていると思っています。 ですから林業を通して、そこに生活する方たちのほのぼのとした幸福感や満足感を充足したいですし、村おこしといった地域の活性化にも非常に興味があります。 大学では様々な検定試験に挑戦しましたが、授業では学べないところまで教えてもらいました。先生方の技術が素晴らしいので、安心して学べます。私はこうした知識や技能・技術は、いずれどこかの場面で役立つと思っています。自分と仕事、自分と社会を繋ぐ力です。その力がないと新たな価値の創造なんてできないです。 視野が広がり、自分の進むべき道を見つけた大学での4年間。いまは卒業制作に仲間と懸命に取り組んでいます。一般家庭のエントランスと庭づくりです。次のステップへ進むために!!! 関連リンク 建設学科WEBページ
-
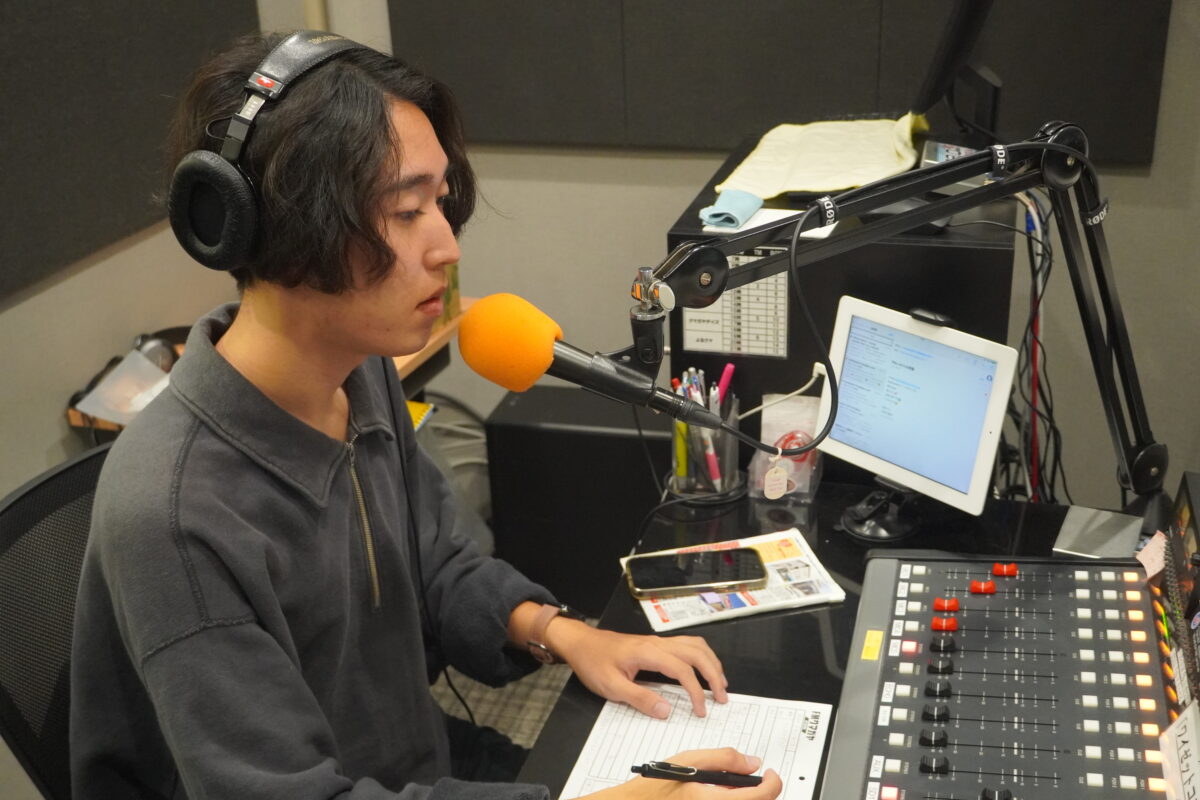
手を動かす「ものづくり」から、考える「仕組みづくり」に~料理研究サークル、ラジオパーソナリティー、そして商店街の活性化に取り組んで見えたこと~
Introduction 学内外で多岐にわたる活動に取り組んでいる和田燿(ひかる)さん(建設学科4年・田尻研究室)。ラジオパーソナリティーなど、ものつくり大学の学生として稀有な分野に挑戦してきた和田さんにインタビューしました。 やりたいことを実現できる環境があるものつくり大学 現在、田尻研究室でまちづくりの一環として商店街の活性化プロジェクトに取り組んでいるほか、料理研究サークルの代表やFMクマガヤのラジオパーソナリティーとして活動しています。この大学生活を通じ、ものつくり大学には「やりたいことを実現できる環境」が存在し、意欲と行動が伴えば、教職員の方から地域の方まで誰でも協力してくれると実感しています。もともと建築系を学びたい気持ちがあり、ものつくり大学を選びましたが、進学の決め手は、オープンキャンパスでの体験でした。特に響いたのは、田尻教授による建設学科の説明と、その後の先輩方によるキャンパスツアーです。先輩方が心から楽しそうに大学の魅力を語る姿は印象に残っています。特に「溶接のいいところ」を熱弁してくださった女性の先輩の姿からは、「本当に好きでやっているのだな」という情熱が伝わってきました。「この大学なら、真に楽しんで勉強できる」と確信し、進学を決めました。 碧蓮祭から誕生した「料理研究サークル」 大学1年で初めて学園祭である碧蓮(へきれん)祭に参加したとき、イベントとしての土台となるステージのイベントや出展物の面白さはずば抜けていると感じました。しかし、イベントに欠かせない飲食店があまり賑わっていない印象を受けました。人が並んでいるのは主に外部からの出店で、学生主体の飲食店の盛り上がりが欠けていたのです。そこで、「自分たちでその盛り上がりをつくろう」と思い、もともと料理が好きだったこともあり、1年生の12月にメンバーを集めて料理研究サークルを立ち上げました。「学祭で学生主体の飲食販売を盛り上げる」ことを目標に掲げました。料理研究サークルの活動を通して、好運な出会いもありました。サークル内でピザを作っていたところ、学生課の職員の方が、行田市内で特色あるピザ屋さんに連れて行ってくれたのです。これがきっかけで、私はそのピザ屋でアルバイトをすることになりました。「ピザが好き」「料理研究サークル」「ものつくり大学」という3つの要素を掛け合わせ、2年生の2023年6月にレンガで「移動式ピザ窯」をつくりました。レンガ1個が2.5㎏あり、合計で300~400個のレンガを買ったのですが、総重量が約1トンにも及び、かなり労働力を要しました。このピザ窯は常設できないため、組み立ててバラす形にしました。ピザ窯は30分ほどで組み立てられますが、建設棟の保管場所から運搬する作業を含めると2~3時間かかります。台車に載せられるだけのレンガを何度も往復して運び、みんなで数100個のレンガを頑張って積む作業をします。 レンガを積み上げて作ったピザ窯 このピザ窯は、碧蓮祭のほか、学内の留学生交流会やサークルの新入生歓迎会など様々なイベントで活躍し、碧蓮祭で飲食販売の盛り上がりをつくることができたと感じています。また、私がかかわっているFMクマガヤや商店街の活性化プロジェクトがきっかけで、大学外にピザを出店することもできました。私たちの出店により、ものつくり大学に興味を持っていただいたり、たくさんの方から純粋にピザの味を喜んでもらえたり、貴重な体験ができました。現在、料理研究サークルのメンバーは20人弱いて、一人ひとりパワーがあります。メンバーはみな決断や行動がスムーズで、課題が生じると自らで解決しようと動きます。対応力や行動力がある主体的なサークルだと感じています。 碧蓮祭でピザを販売する料理研究サークル(中央が和田さん) 碧蓮祭で販売したピザ ピザから繋がったFMクマガヤのパーソナリティー 2024年11月、アルバイト先のピザ屋が市内のお寺の縁日へ出店した際、学生である私のブースを設けてくださり、チャレンジメニューとしてオリジナルピザを販売しました。その時、FMクマガヤのパーソナリティーの方がピザ屋に取材に訪れていました。料理研究サークルを学外にもPRしたいと考えていたので、思い切ってサークルのPR方法について相談してみました。すると、「スタジオにおいでよ」と声をかけていただき、好運にも11月に「週刊フードラボ」という番組にサークルの仲間とゲスト出演することができました。初めてのラジオ出演は、シンプルに緊張しました。目の前にマイクがあるだけでこんなに話す内容が変わるんだという驚きがありました。マイクを前にすると普段の雑談や会話とは全く異なるベクトルが必要だと感じました。「週刊フードラボ」の番組内では、料理研究サークルの活動内容や今後の目標を多くの人に知ってもらえるよう意識して話をしました。翌月の12月には、クリスマスイベントの公開放送にも誘われ出演。そこでFMクマガヤの局長の宇野さんから「パーソナリティーをやってみないか?」と声をかけられました。自分がやれるものだとは思っていませんでしたが、「もらえるチャンスは全部取る」という衝動的な思いから、挑戦を決意。面接後に研修をFMクマガヤの代表の栗原さんから受けました。実際の放送中に受けたミキサー等の機械類の研修では、ミスが生放送に大きく影響してしまったのですが、ミスを受け止めつつ、生放送という場でどうつなげていくかの心構えを学びました。その後、2025年3月にパーソナリティーとなりました。 飾らない大学生の姿が魅力のパーソナリティーでありたい 現在、週2日ほど番組に携わっており、第3火曜日の19時から「りすチャン2025」という番組のナビゲーターも務めています。週に約6時間ものフリートークを行うため、日頃からネタを探し、メモを取るようにしています。思いついたことやあった出来事を箇条書きにし、そこから話を広げています。自分の中で思っているくだらないことを「こうなんですよね」とリスナーに語りかけることで、日常の中から何かをひねり出そうと努めています。夜の番組なので、多少の大学生らしいゆるさは許してほしいという気持ちがあります。大人になると忘れがちな気持ちや、「とりあえずやってみたい」という学生らしさをストレートに受け取ってもらいたいです。飾らない大学生の姿が魅力のパーソナリティーでありたいと思っています。私のように料理研究サークルの活動を外部に広げられたのは、たまたまだと思っています。発信できないだけで、ものつくり大学には木工や、機械いじりといった、各々が持つ個性が溢れています。ラジオという媒体を通じて、そうした学生の魅力を発信し、ものつくり大学の学生の「とがり」を出していきたいです。 学内にFMクマガヤのサテライトスタジオが 今月(2025年10月)からFMクマガヤのサテライトスタジオが学内の図書館・メディア情報センターに設置される予定です。碧蓮祭の1日目である10月25日に公開生放送が行われることになり、話が早く進んでいることに驚いています。私はサテライトスタジオ設置の話を知り、9月にメディア研究サークルを立ち上げ、図書館・メディア情報センター長の井坂教授に顧問をお願いしました。このサークルはラジオに限定せず、メディア全般を取り扱い、学生と地域のつながりを広げていく予定です。サテライトスタジオが実際にどう動くかは未知数ですが、行田とものつくり大学、そして学生の魅力を発信していきたいです。私以外に、主軸に立ってメインで動く学生も見つけていきたいです。こうした活動に前向きな学生が見つかれば、きちんと活動を継続していけると思います。10月25日の公開生放送では碧蓮祭に携わる人や団体の魅力を掘り下げていく予定です。 今までの活動で見えてきたもの 今後は、田尻研究室での取り組みに特に力を注いでいきたいと考えています。建築系を学びたくて進学したものの、サークル活動やラジオパーソナリティなどを通じ、実際に手を動かして「ものをつくる」よりも、いろいろ考えて「仕組みをつくる」ことに興味が移りました。田尻研究室は、物理的な「もの」をつくるような研究ではなく、「基盤の仕組みづくり」の研究室であり、考えることに重きを置いています。まちづくりや都市計画の分野が研究の中心です。私は、商店街の活性化に取り組んでおり、現在、先輩からプロジェクトを引き継ぎ、イベント等を運営する側となっています。この研究室で学ぶ中で、これからやるべきことも見つかりました。まずは学部卒と名乗るだけの能力を身に付けるために学びを深めたいです。また、以前は施工監理といった職種しか考えていませんでしたが、それ以外の可能性もあることを知りました。本当に自分がやりたいことを見つけるために、大学院へ進学し、より深く専門的な知識と考える力をつけたいと考えています。 挑戦や行動力の原点は「興味」 現在に至るまでの大学生活での挑戦や行動力の原点は、単純に「興味」です。「やったことのないこと」「簡単にやれないこと」をやってみる気持ちが強いです。料理研究サークルをつくったことが全てのはじまりでしたが、ラジオのパーソナリティーにしても、一つずつ行動したことに対して評価され、誘っていただく機会に恵まれました。一個ずつやったことに対して派生していった結果、今があります。これからは、今まで培った力や縁の一つ一つを大切にしつつ、田尻研究室の一員として研究活動を追求できればと思います。大学生活は「何もしないのはもったいない」と強く思います。なにかに興味をもち、やりたいと思ったら、まずはいったん口に出し、人に話してみることが大切です。たとえ無理そうでも、夢物語でも、話してみることで周囲の協力が集まり、話はどんどん広がっていくと実感しています。 関連リンク ・建設学科 まちづくり研究室(田尻研究室)・ものつくり大学料理研究サークル(@iot_oryouri)-Instagram
-

人と違うことをやってみる!伝統的な技法「扇垂木」への挑戦が自分自身の成長に
寺社建築の伝統的な技法「扇垂木(おうぎだるき)」と呼ばれる屋根架構を卒業制作のテーマにし、千葉県妙長寺の本堂建築に携わった桐山実久さん(建設学科4年・小野研究室)。 念願だった技能五輪全国大会にも2度出場した経験を持ち、「やってみたいことは挑戦する」がモットー。桐山さんに卒業制作を通して実感している4年間の大学生活での学びや成長、将来の目標などのついてインタビューしました。 木造建築への熱意がものつくり大学進学に 幼い頃から、温かみを感じる木造の家が好きで、木造建築に興味がありました。高校は地元の愛媛県立吉田高校の機械建築工学科に進み、木造建築の面白さに魅了され、高校生ものづくりコンテストにも出場しました。ものつくり大学に進学したのは、同校の先輩が進学していて「技能五輪全国大会に出場できるチャンスがある」と話を聞いたことが大きかったです。ものつくり大学では、アーク溶接などにも触れましたが、やはり木造建築が好きだということを確信し、木造建築コースに進みました。木材の魅力は一度切ると元に戻せないところだと感じます。ボンドで貼っても再生できないですよね。 1年生の頃はコロナ禍でオンライン授業が中心の学生生活に。2年生、3年生の時に連続して技能五輪全国大会に出場しました。出場職種は得意分野の大工ではなく、敢えて家具に挑戦しました。高校時代に先生から「細かいものも得意だね」と言われたことがあったからです。2年生の頃はまだ授業で家具づくりを学んでいなかったため、先輩方にいろいろ教えていただき、寝る間も惜しんで工房で技術を磨き大会に臨みました。3年生の時も家具職種に挑み、努力が実り敢闘賞を受賞することができました。ものつくり大学に進学し、念願だった技能五輪全国大会に挑戦できたことで、チャレンジ精神が旺盛になりました。 技能五輪全国大会に挑戦する桐山さん 伝統的な技法「扇垂木」を卒業制作に 私は小野研究室なのですが、今井研究室と仲が良く、交流が盛んな環境に身を置いています。4年生で卒業制作を迷っていた時、インターンシップでお世話になった今井先生から「千葉県館山市妙長寺の本堂新築の屋根架構を卒業制作として取り組んでみないか」と声をかけていただきました。今井先生から、本堂の屋根の形状は扇垂木(おうぎだるき)という唐傘をモチーフにした扇状に広がった垂木のことで、非常に手間がかかり、単純に配置することが難しいことや、現役の大工さんでも経験できないまれな技法であることなどの説明を受けました。 学生生活の中で木造建築を中心に学び、大会などにも挑戦してきた経緯もあり「人と違ったことをやってみたい」という思いが強い私は「滅多にない経験ができるのは面白そう」と伝統的な技法である扇垂木の制作に挑戦したいと思いました。そして「館山市妙長寺の屋根架構の制作ー扇垂木の墨付け、刻み、加工-」を卒業制作のテーマにすることで新たな自分の可能性を見出したいと思いました。 限られた作業時間が没頭するための集中力に 扇垂木の墨付けから加工の工程は、扇垂木の木材加工の施工経験がある非常勤講師の福島先生のご指導の下、埼玉県寄居の福島工務店で行いました。扇垂木の木材となるのは、垂木、隅木、蕪束(かぶらづか)。墨付けから加工は、一般的な垂木の断面より大きいため、加工に費やす時間が多くなりました。搬入や組み立てを考慮して行った鎌継ぎ(一方の木材に端部の広がった突起を作り、他方の木材にはめ込む継ぎ手)やくせ加工などの作業も何度も行いました。作業時間が限られていたこともあり、43日間(2023年10月27日から12月8日)1日も休まず取り組みました。限られた時間の中での作業だったからこそ、集中して一心に取り組めたのだと思います。加工した木材の仕口を数えてみたら136箇所ありました。 技術的な面は、福島先生のご指導に加え、学生生活を送る過程で様々な道具を使ったり、技術を磨いたりした経験や工程を頭に入れ作業する習慣がプラスに働きました。ある程度作業に慣れると、流れが分かり、段取りをつけながら1人で進めることもありました。精神面でのプレッシャーは地元の方との交流もあり、あまり感じませんでした。技能五輪全国大会に出場した時はかなり精神的にきつかったのですが、2度の出場経験により、精神的にも鍛えられたのかもしれません。しかし、肉体的には、かなりハードでした。今まで扱ってきた木材に比べて遥かに大きく、重かったので、運んだり、転がしたりするのは想像以上に身体に負荷がかかり、腰なども痛くなりました。 難易度の高い施工に挑み、目にした本物の建築 木材の加工が終了した翌日の12月9日に、埼玉県寄居町から千葉県館山市の現場に木材を搬入しました。現地の大工さんの力もお借りし、他の学生と一緒に12月13日から、施工に入りましたが、現地に入る前と後では、緊張感が違いました。まず、蕪束と隅木の取り付けを行いました。上段、中段、下段と隅木を継いでいきました。ここでは、ビス留めをし、しっかり止めました。次に、いよいよ垂木の取り付け作業に。隅木側から垂木を取り付ける工程はとても難しかったです。ひのきの垂木は全て寸法も異なり、木材だからこそ、ねじれや乾燥もあり、調整の繰り返しに。なかなか思うように作業が進まず、苦戦しつつも丁寧にかんなを使って微調整しながら組み立てを進めていきました。垂木の上段、下段の取り付けが進んでいくに従い、扇垂木が大きいことに驚きました。 扇垂木を下から見上げる 現場で施工する桐山さん 本物の建物の施工に関わるのは初めてで、しかも寺院の本堂は地域に根付き、歴史的にも価値をもつことになる建物です。いざ完成間近になった建物を目の前にし、「こんなにも大きな寺院をつくっているんだ」と言葉に表せない感情が湧きました。100年、200年と長期間、多くの人に親しんでもらえる建物にしたいと思っています。本堂の完成は2024年3月を予定しており、扇垂木の美しさが見える屋根になるように作業を進めています。 卒業制作を通して感じている自身の成長 卒業制作を通して特に2つほど自身の成長を感じています。1つは、今までは自分が納得いくためのものづくりだったのが、人に喜んでもらえるものづくりをしたいという思いが加わったことです。そもそも、ものつくり大学に進学した理由の1つに技能五輪全国大会への挑戦があったのですが、高校時代に高校生ものづくりコンテストに参加し、自分自身に対してやり残したという後悔がありました。「賞に入賞することよりも自分の納得するものづくりがやりたい」という思いが強く、1年目には納得できず、2年連続して挑戦。結果、3年生の時は敢闘賞を取ることもでき、自分なりに納得し、達成感が味わえました。しかし、今回、長い歳月建ち続けることになる寺院の施工に携わることで、多くの人が見たり、触れたりして大切にされていくことを想像する機会に恵まれ、ものづくりの喜びを倍に感じるようになりました。 もう1つは、自分に自信が持てたことです。大学生活の中でいろいろな大会にも出場し、賞ももらってきたのですが、実は自分に自信が持てず、ものづくりも上手いと思ったことがありませんでした。自己評価が低く、時に先生から叱られることも。自信がなかったからこそ、さまざまなことに挑戦もしてきました。しかし、今回、卒業制作で難易度の高い扇垂木の制作に挑戦し、その結果、檀家さん、工務店の先生、大学の先生や友人など関わってきた人から評価してもらい、自信が持てました。本堂新築における扇垂木のことが新聞に取り上げられたことで、自分が関わった建築物が多くの方から注目を浴びていることを聞き、嬉しいです。 建築が進む妙長寺本堂 将来は木造建築の教員に 大学卒業後は、まず、大工としてプレカットの仕事に就き、大工職人として腕を磨きたいです。社会経験を積んだ後は、木造建築の教員になりたいと考えています。私の家族はみな教員で、幼い頃から「将来は先生になりたい」と思っていました。人に教えることも好きです。ただ、学生生活の中で、自信がなかなかもてず、後輩に対してもどこか教えることに引き気味でした。しかし、卒業制作などに取り組む中で教えることに少しずつ前向きになり、4年生ではSA(Students Assistant)として先生のアシスタントをしながら後輩にさまざまなことを教える経験をしています。実際、鋸の使い方1つでも教える立場になってみて、みんながそれぞれ違う使い方をしていることが分かり、その違いを面白いと感じます。一方で、一緒にSAをしている学生の教え方から学ぶことも多く、勉強になります。最近、木造建築に進む学生が少なくなっていると感じるので、木造建築の魅力や面白さを伝えられる教員になりたいです。 自分を磨けるものつくり大学での学び ものつくり大学での学生生活は、規則に従いながら過ごしていた小中学校時代、まだ何がやりたいかが明確ではなかった高校時代とは異なり、自分が好きなことをできる環境が整っていました。自分が磨きたいところを磨け、いろいろなことにも挑戦できました。先生からは理論や実践で役に立つことを教えてもらい、さまざまな実習やインターンシップでは、自分で実際にやってみる機会を多く作ることができました。具体的に教えていただいたことに挑戦できた結果、多くのことを学んだり、技術や技能を身に付けたりすることができました。さらに、先輩から教えていただき、後輩に教えるものづくりを通し、人とコミュニケーションを持ったり、信頼関係を築いたりする機会にも多く恵まれました。挑戦することを続けた4年間の学生生活の中で、特に卒業制作は、今までの学びと実践が活き、自分自身の成長を感じる機会になっています。 関連リンク ・建設学科 木質構造・材料研究室(小野研究室) ・建設学科 建築技術デザイン研究室(今井研究室) ・技能五輪全国大会実績WEBページ ・建設学科WEBページ
-

【学生による授業レポート #2】受講後もSA(スチューデント・アシスタント)を通じて深める学び
第2回「学生による授業レポート」をお届けします。今回は建設学科4年の杉山一輝さんが「鋼構造物施工および実習」を紹介します。杉山さんは2年次に「鋼構造物施工および実習」を受講して、4年次ではSA(スチューデント・アシスタント)として実習の運営をサポートしました。学生とSAの両方の視点からのレポートをお届けします。(学年は記事執筆当時) 「鋼構造物施工および実習」について 「鋼構造物施工および実習」は、鋼構造の躯体モデルとして鉄骨部材で構成されたシステム建築を施工する工程を通じて、鋼構造部材の組み立てを中心とした施工管理を学びます。高力ボルトなどの締付け管理や母屋、胴縁などのボルトによる施工要領について学び、筋交いやサグロッドなどの2次部材の役目や施工方法を習得します。 システム建築の特徴 この実習は、株式会社横河システム建築から鉄骨などの部材を提供いただくとともに、社員の方に非常勤講師として来ていただき行われています。横河システム建築は、業界トップシェアを誇るシステム建築と、国内外の大型開閉スタジアムやハワイ天文台のすばる望遠鏡大型シャッター装置など、様々な用途の大型可動建築物を提供する建築製品のトップメーカーです。 システム建築とは、建物を構成する部材を「標準化」することにより、「建築生産プロセス」をシステム化し、商品化した建築です。工場・倉庫・物流施設・店舗・スポーツ施設・最終処分場等に適した建築工法で、建設のうえで想定される検討事項・仕様が予め標準化されているので高品質でありながら、短工期・低価格を実現しています。(株式会社横河システム建築HPより引用:https://www.yokogawa-yess.co.jp/yess01/feature) 完成写真 苦労した点、勉強になった点 2年生で受講した時は、システム建築、鉄骨造と聞いてもイメージが全然湧きませんでした。図面を見て理解するにも時間がかかって施工するにもいろいろ苦労しました。しかし、世の中の鉄骨造の建築物(特に工場・倉庫)はどのように施工されているのかを細かな部分まで実習を通して知ることができ、完成に近づくほど楽しく、面白く感じました。「システム建築」がどのような事なのかも学ぶことができました。 図面確認 3年生になり、SA(スチューデント・アシスタント、以下SA)になってからは、受講生に質問されてもしっかり答えられるように図面をよく確認したり、作業内容を熟知するようにして事前準備をしていました。現場は予定通りにいかないことが多いので臨機応変に対応していくのが大変でした。SAとして、また実習に参加することで、受講当時に分からなかったことが理解できるようになったり、新たな疑問点は見つかったり、毎回の実習が充実していたので参加できて良かったと思います。 SAとして工夫した点 就職活動では、株式会社横河システム建築から内定をいただいたということもあり、SAを2年間経験させてもらっています。一般的にSAという立場は、受講生のサポート役として参加しますが、この実習では規模が大きいということもあり、SAが率先して受講生をまとめています。受講生では危険な作業が少々あり、SAがやらなくてはいけない作業があったりするからです。 工夫したことは、その場その場でいろいろとあります。教授・非常勤講師の打ち合わせに参加して、実習で使用する工具類の確認、授業の流れを把握したりして受講生がスムーズに実習できるように環境づくりを行いました。また、複数人いるSAの中でリーダーでもあったので指示を出したり、自身の分からないことはすぐに非常勤講師に質問して対応できるようにしていました。 SAによる柱設置作業 原稿建設学科4年 杉山 一輝(すぎやま かずき) 関連リンク ・【学生による授業レポート】ジジジジッ、バチバチッ・・・五感で学ぶ溶接技術・建設学科WEBページ
-

目指すはベトナムと日本の架け橋。いつか強みを生かして、新たなキャリアにステップアップしたい
ベトナム出身のヴ―・ディン・ズーンさん(総合機械学科4年生)は、中学時代よりテレビで知った日本文化や日本社会に親しみを持ち、また有形の製品を扱い、「自身の仕事が形になっている」という実感を得られる日本の製造業に大きな期待や希望を抱いていました。 3年間の日本語学習を経て、ものつくり大学へ入学。2023年度4月からは日本での就業をスタートさせます。留学生だから感じる様々な課題を持ち前の明るさと好奇心で乗り越えてきたズーンさんの今後の目標や夢はなにか。後輩へのメッセージと共にお届けします。 ベトナム社会の発展に尽力されているホエ先生との出会い ベトナム、ホーチミン市にあるドンズー日本語学校のグエン・ドク・ホエ先生との出会いが、日本に留学するきっかけとなりました。ホエ先生は、国費留学生として1959年から74年まで、京都大学と東京大学大学院に在籍していた方で、帰国後、独自の日本語学習法をベトナム人向けに編み出し、約30年で2千人以上を日本に留学させてきた方です。一貫して日本語の普及に尽力してきた功績が認められて、2019年には日本政府から外務大臣表彰、2021年には外国人叙勲で旭日小綬章を受章されています。それほど素晴らしい先生です。 私の実家はハノイから約150キロ離れたところですが、ホエ先生は各地の高校を訪ねて優秀な学生にドンズーで日本語を勉強し留学しないかと進めていました。ベトナムでは農業が主で、大きな機械を使った製造業はハード&ソフト共に後れていました。テレビで見た日本の機械の優秀さや頑丈さに感心して、もともと中学時代に日本の歴史や文化に親しみがあり、製造業に興味があったので、いずれは留学したいと思っていました。それでホエ先生の学校で日本語を学んでから、来日して日本語学校で2年経過してから、ものつくり大学総合機械学科へ入学しました。 日本語を学んできたとはいえ、入学してから多くの日本の友人や知り合いを作ることで、ようやく日本語が堪能になっていきました。人見知りしない性格なので、どんどん興味あることに飛び込んでいったのです。しかし、筆記試験には苦戦しました。読み書きはもちろん出来るのですが、漢字圏の外国人の方に比べると不利かな・・・と。そこが苦労した点ですね。 とにかくモノをいじりまわし、作り上げることが好き 大学では、フライス盤、旋盤など工作機械を使えるようになり、資格を取得しながら学んできました。機械システムと電気システムおよび情報システムの搭載されているコンピュータシステムも学び、ハードウェアとソフトウェア、両面の開発も学んできました。卒業研究では『インピーダンスマッチングを考慮に入れた人力発電装置』という題目で取組み、成果発表を行いました。これはキックボードの普及に向けた充電器の需要が高まっている現状で、自分で自分のキックボードを充電できる設備があれば誰でも楽に発電することができると考えました。 インピーダンスとは、回路と回路を伝送路で結ぶとき、回路のインピーダンスが異なると、信号電流の一部が反射されてノイズとなったり、出力が低下したりします。この不整合を解消するのがインピーダンスマッチングです。そのことを考慮しながら、人力による発電機の開発に取り組みました。ペダル的なものを漕いで、発電させるもので、負荷もかけられるので軽い運動にも最適です。そのため強度が重要でした。また100ボルトのコンセントも設置して、スマホ充電器にも活用でき、アウトドアや災害時などでも運動を兼ねて使用することができるように開発しました。自分で言うのもなんですが、発想は面白いと思っています。 また学業以外の活動では、チューターをしていました。4年生ではスチューデントアシスタント(SA)。留学生のための国際交流サークルやバドミントンサークルに入っていました。 人が好き!出会った人との距離をもっともっと近くへ!! プライベートではスピーカーを製作したり、オートバイを改装したりして楽しんでいます。しかも完成はないので、永遠に作業をして常にアップロードしています。製作したスピーカーでは、母国ベトナムの音楽を聴いています。改装したオートバイに乗車して仲間たち4人と静岡へツーリングに行きました。ツーリングは楽しかったですが、残念ながら車検切れで今は乗っていません。思い返せば、「ものづくり」に励んできた4年間でした。性格なので、これからもきっとやめられないんでしょうね(笑)。 また、ベトナムフェスティバル in 神奈川の実行委員として活動。同じ川崎市で多文化共生推進事業活動やベトナム支援会で活動しています。神奈川県では県内に暮らすベトナム人や訪日ベトナム人観光客が増加していて、将来にわたる両地域の継続的な成長と発展を図っています。その一助になればと活動しています。 それから日本ボビナム協会の会員になって活動をしています。ボビナムとはベトナムで生まれ、世界60カ国に広がる総合武術です。加盟国はアジア各国はもちろん、ヨーロッパ、中東、オーストラリア、アフリカ、アメリカと全世界に広がりをみせています。創始者グェン・ロックさんにより1938年に設立。東洋の中国拳法、古武術などと西洋のレスリング、キックボクシングなどがベトナム人によって研究、分析され、練り上げられた、個性的かつ合理的な総合武術です。これまでに上野公園で行われたベトナムフェスティバルや靖国神社奉納演舞などに参加して、身に付けた技を見ていただいています。ドンチャンと呼ばれる美しい足技の数々も、ボビナムの特色です。日本でも技の名前や用語などはベトナム語を使い、ベトナムで培われた文化と精神を尊重しています。 このように性格はアクティブでアグレッシブです。とにかく人が好きです。人とかかわりを持つことが楽しいです。一対一でも複数でもOKです。出会ってからお互いの距離が縮まることが嬉しいです。もっともっと距離感を縮めて、一緒に人生を楽しみたい気持ちが強いです。人から向上心、好奇心が旺盛だね、とよく言われます。自分でもそう思いますし、素晴らしい長所だと思っています。これが個性ですね。他の人も、様々な素晴らしい個性をお持ちなので、そうした出会いをもっともっと、この日本で経験したいと思っています。 大好きだった日本―来日をきっかけに日本で働きたいと強く思った 卒業後は日本企業に従事します。いずれは母国と製造業の可能性を幅広く事業展開出来たら一番嬉しいですし、将来的にそこに関わりたいと思っています。ベトナムはとても成長していける国でもあるので、これから何年かかけて学ぶことを糧にして、母国のベトナムだけでなく、日本と海外の架け橋になりたいとも思っています。 まずは両国の橋渡しができる人物になりたいと大きな夢を抱いていますし、すごく自分に期待しています。そして自分のことだけでなく、社会のためを思うこと、そして未来の指導者として両国で頑張りたいです。ですので、ホームは日本でもベトナムでもどちらでもよいと思っています。諦めずに、いつか必ず乗り越えられる、今じゃなければ明日がある、ゴールとなる日が必ず来ると信じていれば乗り越えられると思っています。何が必要なのか、何をすべきなのか考えることも多くあり、いろいろな対応を求められると思いますが、逆にそれは嬉しいです。外国人だから、若いからとか一切関係なく、意見や考えを取り入れてもらえたり、毎日違うことをやることで成長できると信じています。 後輩たちには、目的を持って留学しないとダメと言いたいです。日本語を学ぶことも、大学の学修も、日本社会へ溶け込むことも、ぜんぶ夢や目的のためでないと続きません。色々な方のサポートを受けて、それを感謝し、成果でお応えする。そうした考えを持って、日々研鑽することがとても重要だと思います。 皆さん、私に続いてください。わからなければ、私に声かけてくださいね。それでは、 Anh đợi em( アン ドイ エン)! 関連リンク ・情報メカトロニクス学科WEBページ
-

震災復興の願いを実現した「集いの場」建設
村上 緑さん(建設学科4年・今井研究室)は、2022年3月下旬、ある決意を胸に父親と共に大学の実習で使用した木材をトラックに積み込み、ものつくり大学から故郷へ出発しました。それから季節は流れて、11月末。たくさんの人に支えられて、夢を叶えました。 故郷のために 村上さんは、岩手県陸前高田市の出身。陸前高田市は、2011年3月11日に発生した東日本大震災での津波により、大きな被害を受けた地域です。全国的にも有名な「奇跡の一本松」(モニュメント)は、震災遺構のひとつです。当時住んでいた地域は、600戸のうち592戸が全半壊するという壊滅的な被害を受けました。 奇跡の一本松 11歳で震災体験をし、その後、ものつくり大学に進学し、卒業制作に選んだテーマは、故郷の地に「皆で集まれる場所」を作ること。そもそも、ものつくり大学を進学先に選んだ理由も、「何もなくなったところから道路や橋が作られ、建物ができ、人々が戻ってくる光景を目の当たりにして、ものづくりの魅力に気づき、学びたい」と考えたからでした。 震災から9年が経過した2020年、津波浸水域であった市街地は10mのかさ上げが終わり、地権者へ引き渡されました。しかし、9年の間に多くの住民が別の場所に新たな生活拠点を持ってしまったため、かさ上げ地は、今も空き地が点在しています。実家も、すでに市内の別の地域に移転していました。 そこで、幼い頃にたくさんの人と関わり、たくさんの経験をし、たくさんの思い出が作られた大好きな故郷にコミュニティを復活させるため、元々住んでいた土地に、皆が集まれる「集いの場」を作ることを決めたのです。 陸前高田にある昔ながらの家には、「おかみ(お上座敷)」と呼ばれる多目的に使える部屋がありました。大切な人をもてなすためのその部屋は、冠婚葬祭や宴会の場所として使用され、遠方から親戚や友人が来た時には宿泊場所としても使われていました。この「おかみ」を再現することができれば、多くの人が集まってくると考えたのでした。 「集いの場」建設へ 「集いの場」は、村上さんにとって、ものつくり大学で学んできたことの集大成になりました。まず、建設に必要な確認申請は、今井教授や小野教授、内定先の設計事務所の方々などの力を借りながらも、全て自分で行いました。建設に使用する木材は、SDGsを考え、実習で毎年出てしまう使用済みの木材を構造材の一部に使ったほか、屋内の小物などに形を変え、資源を有効活用しています。 帰郷してから、工事に協力してくれる工務店を自分で探しました。古くから地元にあり、震災直後は瓦礫の撤去などに尽力していた工務店が快く協力してくれることになり、同級生の鈴木 岳大さん、高橋 光さん(2人とも建設学科4年・小野研究室)と一緒にインターンシップ生という形で、基礎のコンクリ打ちや建方《たてかた》に加わりました。 地鎮祭は、震災前に住んでいた地元の神社にお願いし、境内の竹を四方竹に使いました。また、地鎮祭には、大学から今井教授と小野教授の他に、内定先でもあり、構造計算の相談をしていた設計事務所の方も埼玉から駆けつけてくれました。 基礎工事が終わってからの建方工事は「あっという間」でした。建方は力仕事も多く、女性には重労働でしたが、一緒にインターンシップに行った鈴木さんと高橋さんが率先して動いてくれました。さらに、ものつくり大学で非常勤講師をしていた親戚の村上幸一さんも、当時使っていた大学のロゴが入ったヘルメットを被り、喜んで工事を手伝ってくれました。 建方工事の様子 大学のヘルメットで現場に立つ村上幸一さん 2022年6月には、たくさんの地元の人たちが集まる中で上棟式が行われました。最近は略式で行われることが多い上棟式ですが、伝統的な上棟式では鶴と亀が描かれた矢羽根を表鬼門(北東)と裏鬼門(南西)に配して氏神様を鎮めます。その絵は自身が描いたものです。また、矢羽根を結ぶ帯には、村上家の三姉妹が成人式で締めた着物の帯が使われました。上棟式で使われた竹は、思い出の品として、完成後も土間の仕切り兼インテリアとなり再利用されています。 震災後に自宅を再建した時はまだ自粛ムードがあり、上棟式をすることはできませんでした。しかし、「集いの場」は地元の活性化のために建てるのだから、「地元の人たちにも来てほしい」という思いから、今では珍しい昔ながらの上棟式を行いました。災いをはらうために行われる餅まきも自ら行い、そこには、子どもたちが喜んで掴もうと手を伸ばす姿がありました。 村上さんが描いた矢羽根 餅まきの様子 インテリアとして再利用した竹材 敷地内には、東屋も建っています。これは、自身が3年生の時に木造実習で制作したものを移築しています。この東屋は、地元の人たちが自由に休憩できるように敷地ギリギリの場所に配置されています。完成した今は、絵本『泣いた赤鬼』の一節「心の優しい鬼のうちです どなたでもおいでください…」を引用した看板が立てられています。 誰でも自由に休憩できる東屋 屋根、外壁、床工事も終わった11月末には、1年生から4年生まで総勢20名を超える学生たちが陸前高田に行き、4日間にわたって仕上の内装工事を行いました。天井や壁を珪藻土で塗り、居間・土間のトイレ・洗面所の3か所の建具は、技能五輪全国大会の家具職種に出場経験のある三明 杏さん(建設学科4年・佐々木研究室)が制作しました。 「皆には感謝です。それと、ものを作るのが好きだけど、何をしたらいいか分からない後輩たちには、ものづくりの場を提供できたことが嬉しい」と話します。そして、学生同士の縁だけではなく、和室には震災前の自宅で使っていた畳店に発注した畳を使い、地元とのつながりも深めています。 こうして、村上さんの夢だった建坪 約24坪の「集いの場」が完成しました。 故郷への思い 建設中は、施主であり施工業者でもあったので、全てを一人で背負い込んでしまい、責任感からプレッシャーに押しつぶされそうになった時もありました。それでも、たくさんの人の力を借りて、「集いの場」を完成させました。2年生の頃から図面を描き、構想していた「地元の人の役に立つ、家族のために形になるものを作る」という夢を叶えることができたのです。また、「集いの場」の建設は、「父の夢でもありました。震災で更地になった今泉に戻る」という強い思いがありました。「大好きな故郷のために、大好きな大学で学んだことを活かして、ものづくりが大好きな仲間と共に協力しあって『集いの場』を完成させることができ、本当に嬉しいです」。 「こんなにたくさんの人が協力してくれるとは思っていなかった」と言う村上さんの献身的で真っすぐで、そして情熱的な夢に触れた時、誰もが協力したくなるのは間違いないところです。 「大学から『集いの場』でゼミ合宿などを開きたいという要請には応えたいし、私自身が出張オープンキャンパスを開くことだってできます」と今後の活用についても夢は広がります。 大学を出発する前にこう言っていました。「私にとって、故郷はとても大切な場所で、多くの人が行きかう町並みや空気感、景色、におい、色すべてが大好きでした。今でもよく思い出しますし、これからも心の中で生き続けます。だけど、震災前の風景を知らない、覚えていない子どもたちが増えています。その子どもたちにとっての故郷が『自分にとって大切な町』になるように願っています」。 村上さんが作った「集いの場」は、これからきっと、地域のコミュニティに必要不可欠な場所となり、次世代へとつながる場になっていくでしょう。 関連リンク 建設学科WEBページ 建設学科 建築技術デザイン研究室(今井研究室)
-

ぼくが旅に出る理由 モバイルハウスで日本一周
ものつくり大学が2010年度から主催している「高校生建設設計競技」の2022年度の課題は「これからのモバイルハウス」です。「モバイルハウス」は、新型コロナウイルスがまん延し、人々の行動が制限されてしまった昨今、3密を避けられることからブームになったアウトドアと共に注目されている、「自由に移動できる家」です。設計ではなく、実際に軽トラックの荷台に居住空間を載せて作ったモバイルハウスで、日本一周に挑戦した学生がいます。渡邊 大也さん(建設学科4年・今井研究室)は、2022年の7月に盛暑の東日本を縦断。その後、9月から10月にかけて西日本を横断しました。渡邊さんは、どうしてモバイルハウスを作ったのか、なぜ日本一周の旅に出たのか、その理由に迫ります。 モバイルハウスを作ったきっかけ 運転免許取得時に、祖父から譲り受けた20年ものの軽トラックの荷台を何かに活かしたかったのが、そもそもの始まりです。最初は、大好きなヒマワリを皆に見てもらうために荷台で育てていましたが、大学1年の2月頃から新型コロナウイルスが拡大し始め、2年生の最初の頃は全ての授業がオンライン授業になりました。そこで、「オンラインならば全国を旅しながらでも授業を受けられるんじゃないか」と思い立ち、モバイルハウスの制作が始まりました。 子供の頃から旅行やキャンプが大好きで、高校生の時に、小口良平さんの「スマイル!笑顔と出会った自転車地球一周157カ国、155,502㎞」という本を読んでから、バックパッカーになるという夢を持っていました。そして、モバイルハウスを作った理由としてもう一つ、「元々、ものを作るのは好きだったけど、大きなものを完成させたことが無かったので、10代最後の挑戦にしたい」という思いがありました。 大学2年の夏からモバイルハウスの制作が始まりました。最初の頃は夢が膨らみすぎて、天井部分に芝生を植える等、完成した今となっては非現実的なアイデアもあり、納得のいくモバイルハウスが完成した時には大学4年生になっていました。 モバイルハウスの図面 制作中のモバイルハウス モバイルハウスのこだわり モバイルハウスは「海と船」をモチーフにして作られています。山梨出身で大学は埼玉。身近に海がない環境で育ったため、海に憧れを抱いていました。 モバイルハウスの助手席側の窓は、実際に船舶に使われている丸窓が入り、運転席側の窓は、旅先で海を眺めることを想定して、白く大きな窓を採用しています。また、屋根の部分は波をモチーフにして木材を加工しています。 制作にあたっては、大学の授業を応用して一人で制作を進めました。作り始めた頃は、モバイルハウスを作って旅に出ようとしている事を友人に話しても、皆から笑われたり、「やめときなよ」を言われました。しかし、完成が近くなってきて、本気さが伝わると、友人たちが最後の仕上げを手伝ってくれました。 旅での経験 完成したモバイルハウスで、いよいよ日本一周の旅に出発します。東日本に1か月、西日本に1か月半ほどの旅でしたが、どこに行くのか事前に計画は立てず、行先を決めるのは前日の夜。 世界遺産検定3級を持っていて、今回の旅には国内の世界遺産を巡るという目的がありました。日本を一周する中で、日本にある25件の世界遺産のうち10件を訪ねました。これで、未訪問の世界遺産は残り4つです。 大浦天主堂(長崎県) 白川郷(岐阜県) 他にも、旅にノルマ的なものを課していて、「建築・グルメ・文化」のうち、2つを堪能したと思えたら、次の場所に移るというものでした。 今回の旅で思い出に残っている場所は、モバイルハウスを作ったら絶対に行きたいと思っていた石川県の千里浜です。千里浜なぎさドライブウェイは、日本で唯一、一般の自動車やバイクでも砂浜の波打ち際を走れる道路です。海に憧れ、「海と船」をモチーフにしたモバイルハウスを作ったからには、是非とも写真に納めたい場所でした。ちなみに、石川県では、近江町市場の海鮮料理やターバンカレーを堪能して、兼六園や金沢21世紀美術館を訪ねました。 他にも、鹿児島県の桜島も印象に残る旅先でした。山梨で育ったため、山は見慣れていますが、山の形がまるで違っていて、ちょうど噴火していた桜島の雄大さが心に残っています。 旅の最中には、様々な人と出会い、繋がりもできました。特に、広島を旅していた時には、モバイルハウスを作りたいと考えている長崎から来た人に話しかけられ、ちょうど卒業研究用に作っていた資料を渡したことから意気投合しました。「今度、長崎に来る時は案内するよ」と言われたことで、実際に訪ねてみました。 また、千葉を旅している時は、所属する研究室の今井教授から「私の実家に行っていいよ」と連絡があり、実際にお風呂を借り、ご飯をごちそうになりました。 鳥取で台風に遭った時は、体育館に開設された避難所に行きました。避難しているのは一人だけでした。1か月という長い間、1.3畳ほどのモバイルハウスで生活していたため、広い体育館で一人になり、不意に寂しさを覚えました。寝れずにいたら、避難所の管理人の方が話しかけてきてくれて、夜遅くまで旅の話を聞いてくれました。 モバイルハウスの後方に「日本一周」と看板を掲げていたので、行く先々で話しかけてもらいました。長野の道の駅で同じように旅をしている方から素麺をごちそうになったり、途中で寄ったコンビニのオーナーから差し入れをいただいたりした事もあります。追い越していったバイクの方に手を振られる等、人の優しさに触れることができた旅でした。 モバイルハウス後方 長野でいただいた素麺 トラブルも数多くありました。一人旅だから何かあっても、自分で何とかするしかありません。佐賀の山を走っていた時に、エンジンオイルランプが点灯した上にガス欠になりかけていたところ、更にぬかるみでスタックした時は、山中に一人の状況に絶望して思わず叫びそうになりました(笑)。事前に、自動車部の友人から、オイルの入れ方やスタックした時の対処法を教えてもらっていたので何とかなりましたが、本当に怖かったです。 これからのモバイルハウス いつかモバイルハウスで海外に行き、高校生の時に留学していたアメリカのテネシー州まで旅をして、ホストファミリーを驚かせるという野望を持っています。 モバイルハウスで旅をする中で、「モバイルハウスがあれば家はいらない」と考えるようになりました。先日、モバイルハウスを所有している人たちの集まりがありました。夫婦二人と犬一匹でモバイルハウスに暮らしている方と出会い、モバイルハウスの可能性を感じました。軽トラックだと居住空間は狭いですが、1トントラックや2トントラックの荷台であれば、居住空間も広くすることができます。 実は、旅が終わった今も、ほとんどアパートで寝ることはなく、最後にアパートで寝たのはいつか分からないくらい、モバイルハウスか研究室に寝泊まりする日々が続いています。 日本ではモバイルハウスはかなり珍しい車ですが、車幅以内、高さ2.5m以内、350㎏以内であれば、自分の好きなように作れます。荷台に居住空間を荷物として載せているだけなので、特に手続きも必要ありません。制約があるからこそ、作っていて面白いと感じていて、モバイルハウスをもっと広めたいと考えています。 旅とは「生きがい」です。小さい頃から安定が好きではなく、刺激を求めていて、何をしても結局、旅に繋がります。就職先は、全国に支店がある内装工事の会社から内定をもらいましたが、転勤についても全国色々なところで建築に関われるので、今から楽しみです。 関連リンク 第12回ものつくり大学高校生建設設計競技 建設学科 建築技術デザイン研究室(今井研究室) 建設学科WEBページ
-

現場体験で感じた林業に魅了されて・・・第二の故郷へ就く
林業の機械化が進んだことで、素材生産や森林調査等で女性が活躍する場が増えています。とはいえ、まだまだ3K(きつい、汚い、危険)のイメージは拭えません。その林業の現場に大きな夢を抱いて挑戦する女子学生がいます。 例えば、京都を代表する銘木「北山杉」。古くから北山林業では女性は重要な役割を担っていました。枝打ちや伐採は男性の仕事ですが、加工作業や運搬、苗木の植え付けは主に女性の仕事でした。では、現代の林業女子には仕事はないのでしょうか。近年は機械化が進むことで伐採等の林業現場へも女性が進出することが期待されています。その林業に挑戦する浅野 零さん(建設学科4年)。153㎝の華奢なカラダからは想像できないバイタリティーの源はなにか、感動のインタビューです。 浅野さんのチャレンジ魂を育てたものは何ですか 高校までものづくりとは縁がなかったです。茨城県の生まれですが、小学校4年から中学卒業まで長野県にある人口850人程の村へ山村留学していました。高校は山口県でした。田舎が好きで、今度は瀬戸内海の島でした。山から海へ、です。高校時代は、アーチェリー部に所属していました。強化指定を受けていたことで、3年生では選手として全国大会へ出場しています。強いてものづくりと縁があるなら、山村留学時に仲間と小屋を作ったことでしょうか。その楽しかった思い出は心のどこかにずっとあって、このエピソードはものつくり大学へ進学する時に大学の方にお話しました。大学からすると、私の志望動機が不思議に思えたようでした。 そもそも母の影響というか、子育て方針というか、兄も同じ村に先に山村留学していて、後にカナダへ海外留学をしました。私は茨城→長野→山口→埼玉と国内を巡っていますが、この度、就職で長野へ戻ります。それも山村留学でお世話になった同じ村に戻ります。何でしょうね、Uターンでもなく、Iターンでもなくて。 大学での4年間もパワフルだったのではないですか もちろん普通高校卒なので、ものづくりを学んだのは入学してからです。木に触れることは好きだったので、最初は木工家具の製作に憧れました。角材を加工する授業は楽しかったけれど、そのうち角材になる前の木自体に興味が湧いてきて、林業を意識するようになりました。 1年の秋に「林業体験」のイベントを探して個人で参加しました。木を切って、加工して、その凄さに憧れました。女性も参加しやすいイベントで、参加したのは大方女性でした。人生で初めてチェンソーを使って、木を切りました。そして、垂直に立てた木の幹に切り込みを入れて燃やし、手軽に焚き火が楽しめるスウェーデントーチでの料理を楽しみました。 これをきっかけに林業界への憧れが強くなり、将来仕事として就きたいと思うようになりました。2年次に実施される大学のインターンシップは、長野県飯山市のNPO法人で木材加工に従事しました。3年次では、進路を林業一本に絞ったため、個人的に様々な企業や現場を見学に行きました。そういう意味では決断も早く、行動力もありましたね。いま思えば大学の授業との両立もうまく対処していたように思います。 自らの進むべき道を見つけるまでに、どんな出会いがありましたか 大学では就活を意識した活動と共に、1年次で建築大工3級、2年次で左官2級、造園3級、3年次で造園2級と、とにかく木に関わる資格を取得していきました。生活全てを木に関わっていきたい思いが強かったです。 実は、高校時代に生活していた山口県の林業会社の方に「この世界、女性ではたいへんだけれど、男性とは違う視点で活躍している方がたくさんいるよ」と言われました。その林業会社の方にはオンラインで頻繁に相談に乗っていただきました。「山口においでよ」と何度もお誘いをいただきました。正直、山口へ移住しようという気持ちにもなりました。同時に長野とも連絡を取っていて、情報収集に努めていました。 林業は、国の重要な施策なので、どちらかと言えば昔ながらの堅苦しいイメージを持っていました。でも、民間の小さな林業会社では、自分の技術やスキルがついたらやりたいことをやらせてもらえるような新しい考え方も生まれてきていることを知りました。長野で林業を起業された社長さんと話していると、ぐいぐい引き込まれていきました。その将来を見据えた魅力たっぷりの内容に感激しました。 そして最終的に長野へ就職を決めたのですか もちろん企業方針を何度も聞いて、性格的に合っているなと思いましたし、私が内定をいただいた会社がある村は、小学生の山村留学でお世話になったところでした。この村は私にとって特別です。住むことができる、仕事をすることができるなら恩返しの気持ちを持って戻りたいと強く思いました。会社も林業としては2021年に法人化されたばかり。不思議な縁を感じて、お世話になった村へ帰ろうと思いました。 林業女子としての不安や期待はありますか 林業は3Kと言われます。きつい、汚い、危険ですね。それに林業の現場に出る女性としての問題は、まずトイレ。いまは自然保護の観点から、以前のような現地で処理するようなことは減ってきています。トイレの設置や、山を下って用を足すこともできます。それから力の強さですね。女性ですので、体力は男性と比べて見劣りします。でも機械化も進み、力の問題も徐々に解決してくれそうです。緑の雇用制度で3年間鍛えることができるので、いまはそれが楽しみでなりません。都会にある林業会社では、近年「かっこいい林業」をスローガンにして新しい「K」が生まれています。期待ということでは、いずれキャンプ場を作るという会社の重点方針があります。いまは力不足ですが、ぜひチャレンジしたいです。 林業を通して、森林と地域との新たな価値を創造する繋ぎになるということですね 日本は平野の少ない森林大国です。木があれば、火を起こせる。火を起こしたら、ごはんも炊ける、お風呂も沸かせる。家も建てられるし、生きていく上でのあらゆる繋がりがあります。花粉問題だって、木を切る人がいれば、むしろ空気の循環を良くしてくれる。林業は大切なんですよね。人間の生活の基盤になっていると思っています。 ですから林業を通して、そこに生活する方たちのほのぼのとした幸福感や満足感を充足したいですし、村おこしといった地域の活性化にも非常に興味があります。 大学では様々な検定試験に挑戦しましたが、授業では学べないところまで教えてもらいました。先生方の技術が素晴らしいので、安心して学べます。私はこうした知識や技能・技術は、いずれどこかの場面で役立つと思っています。自分と仕事、自分と社会を繋ぐ力です。その力がないと新たな価値の創造なんてできないです。 視野が広がり、自分の進むべき道を見つけた大学での4年間。いまは卒業制作に仲間と懸命に取り組んでいます。一般家庭のエントランスと庭づくりです。次のステップへ進むために!!! 関連リンク 建設学科WEBページ