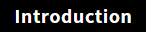
「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載を始めました。
今回は、秩父の土地に宿る精神に思いを馳せます。
秩父がある
「埼玉県に何があるのですか?」--
あなたはこう問うかもしれない(あるいは問わないかもしれない)。私ならこう答えるだろう。
「埼玉には秩父がある」と。
秩父というと誰でも思い出す、巡礼。そうと聞くと、これという理由もなしに、心の深層にかすかなさざ波が立つ。なぜだろう。なぜ秩父。なぜ巡礼。
東京に隣接した埼玉からすれば、秩父はその無意識に沈む無音の精神空間を表現しているように見える。
だがそれはごく最近、近代以後の現象である。なぜなら埼玉はその空間的存在論からすれば、初めから巡礼の地だったからである。
これはうかつにも注意されていないように思える。
秩父は、その意味で土地というより、霊性をそのまま差し出してくれる、埼玉の奥の院だ。巡礼は、元来霊的な情報システムである。それは現代人工的に編み上げられた新しい情報システムを突き破ってしばしばその顔を表す。
高度な情報の時代といっても、霊性が土地ときっぱりと切り離されてしまうことはないし、また霊性を伴って初めて土地の特性は人々の意識に入ってくる。
もともと埼玉のみならず、技術と霊性とはいわば二重写しをなしている。埼玉では常にそれらは密接不離の絡み合いとして現在に至っている。言い方を変えれば、日常の陰に潜んで裏側から埼玉県民の認識作用に参画し、微妙な重心として作用している。そのことを今年の夏に足を運んで得心した。

霊道としての秩父線
秩父に至る巡礼路は今は鉄路である。
熊谷から秩父線に乗ると、人と自然の取り扱われ方が、まるで違っていることに気づく。訪れる者の頭脳に訴えるとともに、感覚として、ほとんど生理的に働きかけてくる。平たく言えば、「びりびりくる」のだ。秩父線ホームには意外に乗客がいる。空は曇っているけど、紫外線はかなり強そうである。
初めはまばらに住宅街やショッピングモールが目に入るが、いつしか寄居を越える頃にもなれば山の中を鉄路は走る。時々貨物列車とすれ違う。ただの列車ではない。異様に長く、貨車には石灰石がぎりぎりまで小器用に積み上げられている。それは精密で美しい。武甲山から採掘されたのだろう。
やがて長瀞に到着する。
鉄道と言ったところで、近代以後の枠にはめられた埼玉の生態を決して表現し尽くせるものではない。
ところで埼玉と鉄道の関係はほとんど信じられないくらい深い。いや、深すぎて、埼玉に住む多くの人の頭脳の地図を完全に書き換えてしまってさえいる。現在の埼玉イメージのほとんどは鉄道によって重たいローラーをかけられて、完全にすりつぶされてしまったと言ってもいいだろう。地理感覚を鉄道と混同しながら育ってきたのだ。鉄道駅で表現すれば、たちまちその土地がわかった気になるのは、そのまま怠惰な鉄道脳のしわざである。
そんな簡単な事柄も、巡礼と重なってくるといささか話が違ってくる。秩父線は埼玉の鉄道の中ではむしろ唯一といってよい例外だ。この精神史と鉄路の重複は、肉眼には映らないが、長瀞に到達してはじめて、心眼に映ずる古人の確信に思いをいたすことができた気がする。
こんなに気ぜわしい世の中に生きているのだから、たまには旧習がいかに土地に深く根ざしたものであるか、現地に足を運んで思いをいたしてもばちは当たらないだろう。そこには埼玉県の日常意識からぽっかり抜けた真空がそのまま横たわっていたからだ。

長瀞駅から徒歩10分程度のところに宝登山神社がある。参道を登っていく先からは太鼓が遠く聞こえる。それが次第に近づいてくる。この神聖性の土台を外してしまっては、土地の神秘に触れることはできない。どれほど都市文化と切り結ぼうとも、最深部では歴史からの叫びがなければ文化というものは成り立たないからだ。それらは住む人々がめいめい期せずして持ち寄り差し出しあうことで現在まで永らえている何かでもある。
それがどうだろう。現在の「埼玉」という長持ちに収まると、何か別のイメージに変質してしまう。そこにしまい込まれているのは、このような素朴な信仰や習俗であるに違いない。
奥の稲荷を抜け、古寺の境内にいつしか立ち入ると、そこは清新な空気に支配された静謐な一画である。赤い鳥居はほとんど均等に山の奥まで配分されている。古代の神々の寓居にばったり立ち入ってしまったかのようだ。
どんなに慌ただしい生活をしていたとしても、ときには果てしない歴史や人の生き死にについて問うくらいの用意は誰にでもあるだろう。埼玉の中心と考えられている東京都の隣接地域では、こんな山深いエリアが埼玉に存在していることなどまず念頭に上らないのがふつうである。いわば埼玉県の東半分は生と動の支配する世界であるが、西半分からは死と静の支配する世界から日々内省を迫られていると考えてみたらどうか。モーツァルトの『魔笛』のような夜と昼の世界--。
生と動もこの世にあるしばらくの間である。しかし、死と静はほとんど永遠である。このような基本的な意識の枠組みが、すでに埼玉県には歴史地理的に表現されている。
荒川源流
徒歩で駅まで戻って、今度は反対側の小道を下りてみた。商店には笛やぞうりなどの土産が並ぶ。
坂の突き当りで、長瀞の岩畳をはじめて見た。そのとき、荒川という名称の由来を肌で感じた気がした。ふだん赤羽と川口の間の鉄橋下を流れる荒川は見たところ決して荒くれた川ではない。きちんとコントロールされ、取り立てて屈託もなしにたゆたっているように見える。
源流に近い秩父の荒川を目にしたとき、古代の人たちが何を求めていたか、何を恐れていたかがはっきりした気がした。私は源流にほど近い荒川の実物を前にして、人間の精神と自然の精神との純粋な対話、近代の人工的な観念の介入を許さぬ瞑想に似た感覚に否応なく行き着いた。
気づけば、私は広い岩の上に横になっていた。どうも土地の神々の胎内にいるような気分になる。それは土地の育んできた「夢」なのではないか。そんな風にも思いたくなる。少なくともそこには都市部の明瞭判然たる人間の怜悧な観念は存在しなかった。おそらく土地の精神とは比喩でも観念でもない。それは勝手にひねり出されたものではなかった。古代人の中では、主体と客体などという二元論はなかっただろう。ただ荒く呼吸して大地から湧出する滔々たる水流と一体になっていただけだろう。それを知るのに学問もいらないし、書物もいらない。古人の生活に直接問いかけるだけの素朴な心があれば十分だ。
きっと昔の人は、現実と観念の対立をまるで感じていなかったに違いない。自然全体のうちに人はいるのだし、人の全体のうちに自然はあるというのが、彼らの生きていく意味だったのだ。彼らは、自然が差し出してくる何かを受け取るポイントを特別な場所として認知した。このような自己を取り巻く自然が十分に内面化された場所、自己とはかくのごときのものであり、かくあるべきものであるという場所で、彼らはあえて祭祀を行ったに違いない。
寝転んで川風に吹かれてみれば、土地の精神を支えているのは、存在と切り結ぶ自然感情であることは、明らかなように思える。
秩父にあるのは論理ではない。言葉でさえない。あえて言えばそれはとてつもなく古い体験である。それがうまく言葉にならないというそのことが、かえって一種の表現を求めてやまない、どこかくぐもった呼び声として内面にこだましてくる。
「埼玉には何もない」などと気楽に自嘲し、ごく最近つくられた観念に戯れることしかできないのはあまりにさびしいことだ。
何もないのではない。正体を見極めがたいほどに果てしなく、あまりに何かが「あり過ぎる」のだ。
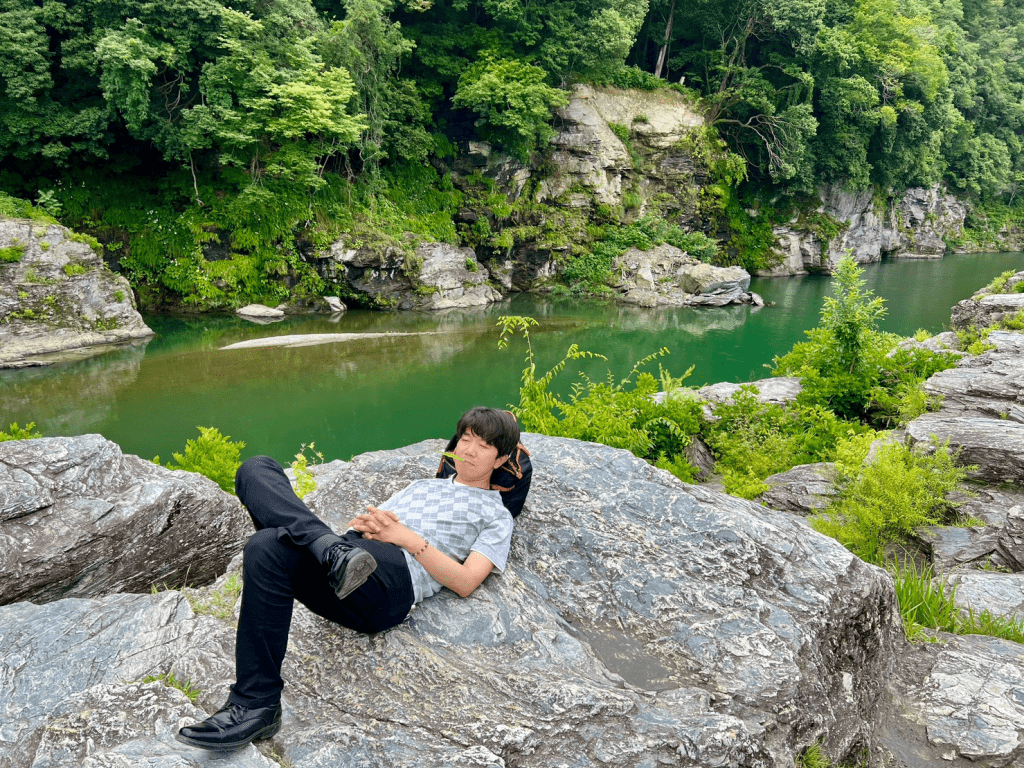

井坂 康志(いさか やすし)
ものつくり大学教養教育センター教授
1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。











