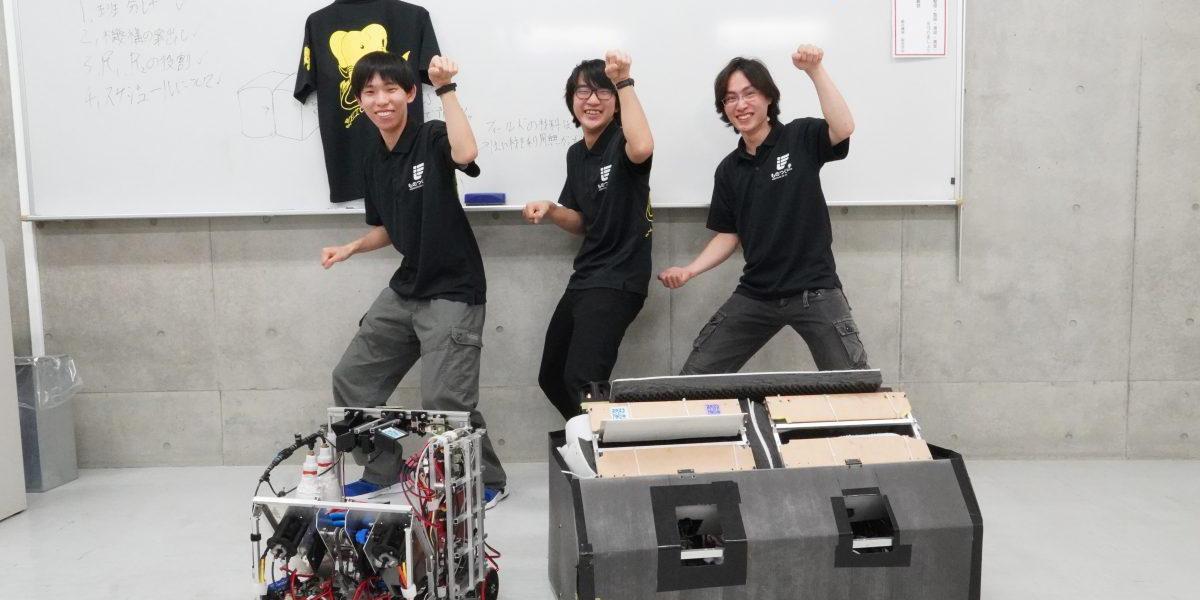隙間風のあれこれ
私は主に住宅の省エネ・快適・耐久性(防露・乾燥)の向上について研究しており、その一つに、住宅の気密性能(隙間の大きさ)に関する研究があります。住宅外表面の隙間が大きいと、その隙間からの外気の出入りによって、暖冷房エネルギーの増大を招き、冬期には足元に冷たい気流が生じて不快になります。これは外部風がない時でも生じます。冬期は室内の温度が外気に比べて高いので、住宅上方の隙間から室内空気が流出し、1階下方の隙間から外気が流出します。
隙間風の寒さに困っている方、またはより省エネにしたいけど、費用面で改修に躊躇されている方は、例えば1階の幅木下だけでも塞ぐ、あるいは床下に潜って壁下の手の届くところだけでも隙間を塞ぐ工事を行ってみてください。暖かくなったとの実感が得られるかを保証するのは難しいですが、暖房エネルギーは確実に減ります。

気密測定と建物の関係性
この住宅全体の隙間面積を測定する方法(気密測定)はJISで制定されています。室内の空気をファンで排気することを思い浮かべてください。気密性が良い(密閉性が高い)建物では少量の排気で、内外の気圧差(差圧)が大きくなり、気密性の悪い建物では、大量に排気しても、各所の隙間からどんどん外気が入ってくるので、あまり差圧がつかないことが想像できるかと思います。
この性質を利用したものが気密測定で、ファンの流量を3段階以上変えて、それぞれで得られる排気量と差圧の関係の累乗関数から、隙間面積に換算します。ただ、この測定には大きな排気ファンも含めて、それなりに高額な専用の器材が必要です。そこで、排気に台所のレンジファンを利用して簡易化できるのではと考えて、昨年、ある企業の支援を得て特許を取得し、廉価で販売し始めました。これには、測定器そのもののコストダウンだけでなく、コンパクト・簡易化したことで測定の人件費も大幅に下げられると見込んでいます。

建築は耐久性や断熱性など、実際に出来たものが設計の通りの性能なのかを確認することが難しい分野です。その中で、気密性能は完成後の現場測定で分かる性能です。また、木造住宅の場合は(吹付け断熱工法の場合を除くと)、工事全般の丁寧な施工が気密性能に影響するので、それを測る目安にもなると考えています。それゆえ、私は今後の全ての住宅で建築者が気密性能を確認してから住まい手に引き渡してほしいと思っています。今回開発した測定器がその一助になれば良いと思っています。
埼玉新聞「知・技の創造」(2025年7月8日号)掲載

松岡 大介(まつおか だいすけ)
建設学科教授
東洋大学大学院博士前期課程修了。京都大学大学院博士後期課程修了。博士(工学)・一級建築士。2017年4月より現職。
専門は建築の温熱環境分野。