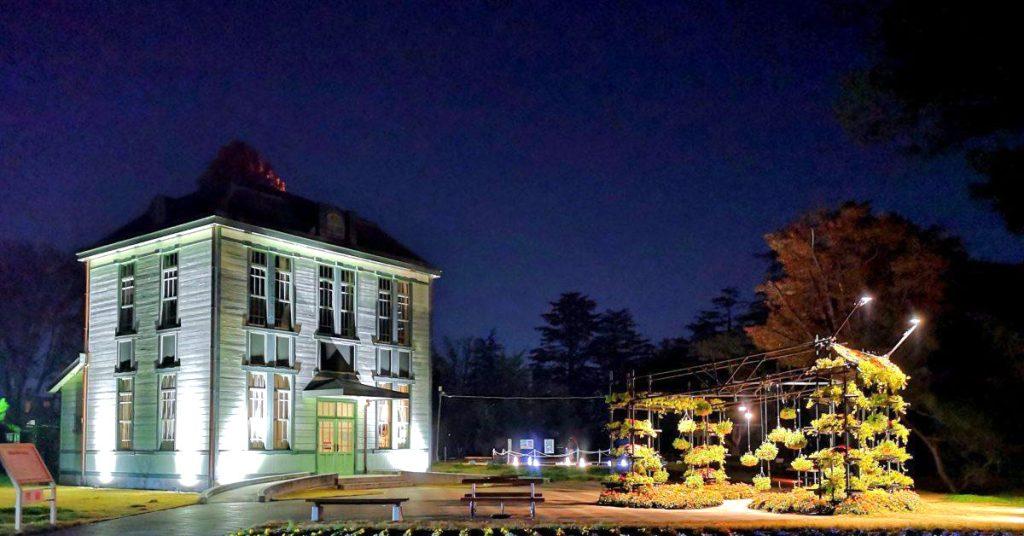#1年生
- 新着順
- 人気順
-

先輩たちへの感謝を胸に大会へ ~第18回若年者ものづくり競技大会②~
2023年8月1日から2日にかけて静岡県で第18回若年者ものづくり競技大会が開催されました。本学では建設学科から2名(建築大工職種1名、木材加工職種1名)の学生が出場し、建築大工職種で金賞、木材加工職種で銀賞という好成績を残すことができました。今回は木材加工職種で銀賞を受賞した入江 蛍さん(建設学科1年・静岡 科学技術高等学校出身)に、大会に出場した感想を伺いました。※木材加工職種の競技は、「小いす」を製作します。原寸図の作成、ホゾ(木材を接合する部分の突起)、ダボ(部材をつなぎ合わせる小片)による接合の加工、接合部の組み立てなどを行います。 慣れない作業に苦戦する毎日 入学当初から技能五輪全国大会に出たいと思っていました。友人から若年者ものづくり競技大会には1年生から出場できる事を聞き、早速、学内の掲示板を探しました。ものづくりに興味を持ったきっかけは、手先が器用な祖父が趣味で水車や離れを作っているのを見てきたからです。その後、大工仕事を学んでみたいと思って、高校で建築大工の技能検定を受けたり、高校生ものづくりコンテストの木材加工部門に出場しました。大工や家具、左官など色々なことに興味があって、ものつくり大学に入学したので、若年者ものづくり競技大会ではどの職種に挑戦するか迷いましたが、やったことがなかった家具に挑戦したいという思いから出場しました。練習は入学してすぐに始めました。大会出場を目指している新入生5人で先輩方に教えてもらいながら、毎日毎日練習をしました。先輩方は、日付が変わるくらいの時間まで常に教えてくださったのでびっくりしました。「まだ23時だからこれからノコやろう」とか日付をまたぐこともあったりして、時間の感覚がおかしくなっていました(笑)。授業もあって大変でしたが、昼夜を問わず練習できるのは良かったなって思います。それに、高校ではいつも一人で練習していたので、予選を受ける友人たちと一緒に、先輩方の指導を受けることができ、頑張ることができる環境はありがたいと思いましたし、だからこそ成長できたのかなって思います。 先輩との練習の様子 大工と家具では木材の大きさも道具も違いますが、少しは大工の経験があるから上手くできるかと思っていました。でも、予想以上に違いがありました。最初は、木材を切るにしても縦引き横引きが真っすぐできなくて、ぴったり合いませんでした。また、家具では白柿(しらがき)という罫書き線を引くための道具を使います。大工では墨差しや差し金を使って墨付けをするので、白柿を使ったことがありませんでした。持ち方もコツが必要で、垂直に線を引くのも難しかったので持ち方から慣れる必要がありました。家具の作業は考えることがすごく多かったです。刃には、しのぎ面という斜めになっているところがあって、そこが加工する側にくるようにとか、線を引くのもどの向きにとかスコヤをどこに当てるのかなど、ただの墨付けではあるんですけど、考えながらやる必要がありました。上手くできるようになったのは5月の学内予選の頃です。予選の時に、縦引きも横引きも最初に比べて真っすぐ切れるようになりましたし、ノミでの作業も綺麗にできるようになってきました。 わずかな隙間 高校生の時は、検定を受ける時も大会に出る時も自信を持てるまでずっと練習をしていたので、あまりプレッシャーを感じることはありませんでした。だけど今回は、本番一週間前までは何回やっても標準時間内に完成できませんでした。やればやるほど課題が見つかって、上手くいかないことがどんどん増えて焦っていました。練習で最後の最後まで納得がいく作品を作れなかったので、緊張していました。それに、本当に多くの方に教えていただいたので、期待に応えたいという気持ちがあったけど不安でした。練習では、標準時間にプラス30分程度かかって完成していましたが、それでは減点になってしまいます。金賞を狙うからには、時間内に作って減点を抑えようと思って大会に臨みました。午前中は思いのほかペースが良くて予定外のところまで作業が進んでしまいました。残りの5分は何をしたらいいのかというくらい余裕が出てしまい、掃除などをしていました(笑)。今にして思えば、ここでもうちょっと考えて進めておけば良かったなと思います。午前は驚くほど調子が良かったのですが、午後になり、最後の一番大事なところを綺麗に切れなかったことを後悔しています。練習の時も上手くいかなくて改善策を見つけて挑みましたが、今一つ上手くいかず隙間がわずかにできてしまいました。仕上げの時に、やすりをかけたり、ボンドで埋めたりして隙間を少しでも埋めるために調整して何とか仕上げました。不安だった作業時間は、標準時間よりプラス10分かかりました。プラス5分ごとに1点減点されてしまうので、出来栄えと減点を秤にかけて作業を終了することを目安にしていました。 完成した課題は、1か所隙間があり納得のいくものではなかったので「金賞は難しいかな」と思いました。でも、やってきたことに後悔はないのでその時の最大限の作品は作れたと思っています。今回、銀賞を受賞することができましたが、「やっぱり金賞取りたかったなぁ」って残念な思いです。でも、作品の出来栄えからすると入賞できて、先輩方の期待に少しは応えることができてほっとしています。先輩方には本当に毎晩遅くまでたくさん教えていただいたので感謝の気持ちでいっぱいです。 やりたい事がいっぱい 色々興味はありますが、建築士になりたいという目標があります。設計する上で、大工や左官のことも分かっていたほうが良いと思うので、まずは、1年生2年生のうちに左官や設計、資格取得など色々なことを経験したいと思います。実習が豊富だから仕上げや木造の実習も頑張りたいです。もうすぐインターンシップ先を決める時期ですが、どの分野に行くかすごく迷っています。本当は、これと決めた分野を究めていったほうがいいとは思っているんですけど、やっぱり色々なことに挑戦して経験を積んでいきたいです。 関連リンク ・練習で磨いた100%の技術を ~第18回若年者ものづくり競技大会①~・若年者ものづくり競技大会 大会後インタビュー・若年者ものづくり競技大会実績WEBページ・建設学科WEBページ
-
.jpg)
【Fゼミ】私の仕事 #4--歌手としての歩みとライフワーク
1年次のFゼミは、新入生が大学生活を円滑に進められるように、基本的な心構えや、ものづくりを担う人材としての基礎的素養を修得する授業です。このFゼミにおいて各界で活躍するプロフェッショナルを招へいし、「現場に宿る教養」とその迫力を体感し、自身の生き方やキャリアに役立ててもらうことを目的として、プロゼミ(プロフェッショナル・ゼミ)を実施しました。今回は、歌手として都内のオペラ劇場を中心に活躍する他、作曲家、台本作家、指揮者、演出家の顔を持つ舞台の総合クリエイター、阿瀬見貴光氏を講師に迎えたプロゼミをお届けします。 肉声の魅力-声楽とは 私の職業は歌手です。声楽家です。主にオペラや舞台のクラシックコンサートに出演します。それと同時に故郷の加須市で市民ミュージカルのプロデュースも行っています。まずは歌手としての仕事についてお話したいと思います。 声楽家と現代的な歌手の大きな違いは何でしょう? そうです、マイクを使うか否かです。2,000人規模の大ホールでも60人以上のオーケストラと共演する場合も、基本的に声楽家はマイクを使いません。すなわち、肉声の魅力で音楽を表現します。肉声だからといって声はただ大きければよいというわけではありません。特にオペラは「声の芸術」とも言われていて、大事なのはよく響いて遠くまで通る声です。たとえば、「ストラディバリウス」というヴァイオリンの名器をご存知の方はいますか? ストラディバリウスの音色は実に繊細で密度が高い。そして近くで聴いているとそれほど大きな音に聞こえないのに、不思議と遠くの方まで響きが飛んでいくという特性があります。声楽家はそのような魅力的な音色をお手本にして技を身につけます。楽器である身体を鍛えたり、音声学を学びます。日々の発声練習も欠かしません。世界にはたくさんの種類の楽器がありますが、人間の声こそが最も美しく表現力豊かな楽器であると私は考えています。皆さんにはアコースティックサウンド、生の響きの醍醐味を感じていただきたいですし、そのようなコンサートに是非とも足を運んで欲しいと思います。 さて、ここで実演の意味も込めて歌ってみたいと思います。オペラ発祥の国イタリアから「オー ソレ ミーオ」というナポリの民謡です。高校1年の教科書に載っていますからご存知の方も多いかもしれませんね。私はイタリアに勉強に行ったことがあるのですが、イタリア南部の方の気質はとにかく陽気でおおらかです。この曲もまたそのような気質が現れていて、活きていることが素晴らしいと感じさせてくれます。 『オー ソレ ミーオ』 新国立劇場オペラの13年間 私は渋谷区初台にあるオペラ専用劇場を有する新国立劇場に所属し、約13年間インターナショナルな活動をしてまいりました。この劇場は、オペラのほか、舞踊と劇場の部門がありまして、どれも大変クオリティの高い公演が行われています。とくにオペラ部門は『ニューヨーク・タイムズ』のオペラ番付でも上位にランキングする実力があり、世界中のトップレベルの演奏家や演出家を招へいしています。 私はこの劇場の13年間オペラ公演で、延べ156演目、780のステージに立ちました。世界トップレベルの芸術家と一緒に舞台を創ること、それが私にとって何より刺激の源になりました。彼らとの日々のリハーサルや公演を通して、彼らの美の根底にある感性、思考、宗教観に触れることができたからです。近年ではウェブ上に舞台の情報が溢れる時代になりましたが、現場でしか味わえない貴重な経験をさせていただきました。日本にいながらにして、まるで海外留学をしているかのような気分です。 さて、オペラと言えばイタリア、ドイツ、フランス、イギリスなどヨーロッパを中心とした国々の芸術家との交流が多いのですが、「オペラ界のアジア」という視点で世界を見たとき、生涯忘れられないエピソードが2つありますのでご紹介したいと思います。 日中共同プロジェクト「アイーダ」と韓国人テノール ひとつ目は2012年の日中共同制作公演『アイーダ』です。日中国交正常化40周年の節目に日中の友好の象徴として共同制作されました。この前代未聞のプロダクションは、歌手およそ100名を新国立劇場と中国国家大劇院から集め、東京と北京で公演するというものです。国家大劇院は北京の中心部にありまして、国の威厳をかけて創設された大変立派な建築物です。近くには人民大会堂(日本の国会議事堂に相当する)があります。当時、中国の反日教育はよく知られていたので、劇場内でも日本人スタッフへのあたりが厳しいのではと心配したものでしたが、まったくの杞憂でした。むしろ国家大劇院の皆さんはとても友好的で、日本の音楽事情に興味津々といった様子でした。休日には関係者が北京市内を案内してくれもしました。リハーサルの後に、若いテノール歌手に食事に誘われ「遠くから来た要人には徹底的にもてなすのが中国人の流儀だ」と言って、約一カ月分のお給料に相当する額のご馳走を用意してくれたこともありました。そして肝心のオペラ公演も大成功を収めました。隣国同士の東洋人が心をひとつにして、西洋文化の象徴であるオペラに挑戦する。満席6,000人の巨大オペラ劇場が大いに湧きました。国家間の歴史認識の違いはあれど、芸術の世界に酔いしれるとき、国境が存在しないのだと感じました。しかし大変残念なことに、東京公演の一週間後、日中両国の外交関係が急速に悪化していきました。もし、このプロジェクトがあとひと月も遅ければ公演中止となっていたでしょう。 ふたつ目のエピソードは韓国です。皆さんは韓国アイドルの「推し」はありますか? 現在ではK-pop が大人気ですし、化粧品、美容グッズ、ファッションなど韓国のトレンドには力があります。若い皆さんは驚くかもしれませんが、2013年頃の日本では韓国に対する嫌悪感、いわゆる「嫌韓」の風潮が非常に高まっていました。その年の流行語のひとつは「ヘイト・スピーチ」でした。新宿区大久保などではデモがあり、激しいバッシングも見られました。そんな社会状況の中、新国立劇場ではオペラ『リゴレット』が公演されました。主役は韓国人の若手テノール歌手、ウーキュン・キム。それまで新国立劇場で韓国人が主役を張ることはほとんどなかったこともあり、過激な世論の中で彼がどんな評価をされるのか、私は興味深く見守っていました。彼の歌声は実に素晴らしいもので、客席は大きな拍手で彼を称えました。「日本の聴衆よ、よく公平な目で評価した!」隔たりを越えた美の世界を感じ、私はステージ上で静かに胸を熱くしました。 インターナショナルな活動の中で私がいつも思うことは、舞台製作の環境は常に政治の影響を受けていますが、政治に侵されない自由な領域を持つのもまた芸術の世界であるということです。だからこそ我々芸術家は、人間の普遍的な価値観や幅広い視点をもって世界の平和に貢献すべきだと考えています。 テクノロジーと古典芸能の融合-オペラ劇場の構造 今日は建設学科の講義ですので、オペラ劇場の構造について少し触れてみたいと思います。まず特徴的なのはステージと客席に挟まれた大きな窪みです。これは「オーケストラ・ピット」と言います。 ここにオーケストラ団員最大100名と指揮者が入り演奏します。ピットの床は上下に動きます。床が下がってピットが深くなるとオーケストラの音量が小さくなり、逆に床が上がると音量は大きくなります。これによって歌手の声量とバランスを取りながら、深さを調節するわけです。ピットの上には大きな反響板があります。オペラやクラシック音楽においては、いかに生の響きを客席に届けるかが大切ですから、音響工学の専門家が材質や形状にこだわり抜いてホール全体を設計しています。 これは劇場平面図です。客席から見える本舞台の左右と奥に同じ面積のスペースがありまして、これを四面舞台と言います。大きな床ごとスライドさせることができます。これによって、巨大な舞台セットを伴う場面転換がスムーズにできますし、場合によってはふたつの演目を日替わりで公演することも可能です。この機構をもつオペラ劇場は日本ではほんのいくつかしかありません。次は劇場断面図を見てみましょう。舞台の上には大きな空間がありまして、これは照明機材や舞台美術などを吊るためのものです。下側はというと「セリ」といって、舞台面の一部もしくは全体を昇降させることができます。そして、これらの機構の多くはコンピューターによって制御されています。最新のテクノロジーは古典芸能であるオペラ(400年の歴史)に新たな表現方法をもたらし続けているのです。 私のライフワーク-ミュージカルかぞ総監督として 「多世代交流の温かい心の居場所をつくろう」と思いついたのは約30年前のことです。私が大学3年生の夏に読んだ新聞記事がきっかけとなりました。若者の意思伝達能力の低下や家庭内暴力は、家庭問題というより社会の歪みに原因があるだろうと考えていました。「自分にできること、自分にしかできないこと」音楽や舞台表現を手段として、人間が人間に興味をもって、大いに笑い、平和を謳う。そんなコミュニティをつくろう!自分がオペラ歌手になるための勉強と並行して、文化団体の運営のイメージを実践方法を温め続けました。 2012年の夏に故郷である加須市で、市民劇団「ミュージカルかぞ」を立ち上げました。ありがたいことに、市長、教育長をはじめ、地元の実力派有志たちが私の掲げる活動理念に賛同、協力してくださいました。さらに嬉しいことに、一年目からすべての年代がバランスよく揃った『三世代ミュージカル』を実現したのです。また、ダンス講師、ピアニスト、照明家などプロの第一線で活躍する業界の仲間も加須に駆けつけてくれました。市民が主役の劇団ですから入団資格は『プロの舞台人でないこと』、以上。技と魂を兼ね備えたプロの舞台スタッフが環境を整え、地元のアマチュア俳優をステージで輝かせるのが私の手法です。団員たちが燃えるような魂で舞台に立つとき、キャラクター描写の奥に個々の圧倒的な生き様が放たれます。そこには見る者の魂を震えさせるほどの「人間の美しさ」があるのです。 しかし、そこにたどり着くまでには膨大な時間と労力、技術を要します。ほとんどの団員は演技や歌唱の経験がないからです。舞台での身体表現、呼吸法、発声法、楽曲分析、台本の読解法、そして舞台創りの精神など、私が日々舞台で実践していることを43名の団員たちに解りやすく愉快に伝えています。 ミュージカルかぞは年に2演目を10年間公演し続け(コロナ禍の中止はありましたが)、着実にレベルアップしています。いつも満員御礼の客席からは割れんばかりの拍手と「ブラボー!」が飛び交います。涙を流しながら客席を立つお客様の姿が増えました。県外からのファンや、教育や文化に携わる方も多くいらっしゃるようになりました。 『大人が笑えば子供も笑う』…劇団の稽古場は笑い声が絶えません。しかし、団員個々の心の事情には静かに話を聞いて、一緒に考えます。不登校、引きこもり、健康上の悩みなど事情は様々ですが、そこから社会の歪みが見えることは少なくないです。しかし、舞台表現を磨き続け、少しずつ自分の声と言葉で素直な自分を語れるようになった団員を見たとき、私も生きていて良かったと感じます。特に子どもや若者には、人と繋がって喜びを感じる『真実の時間』を過ごしてほしいと考えています。それは誰かを愛するための心の糧になると思うからです。 時空を超えるメッセージ-ミュージカル『いち』 さて皆さん、「愛」って何でしょうね? こういった漠然とした質問が一番困るんですよね。そのような抽象的なイメージを閃きに導かれながら具象化できるのが芸術文化のいいところです。愛をいかに表現するか、私も日々悩み続けています。 私の劇作家としての代表作にミュージカル『いち』があります。作品のもととなった加須古来からの伝承『いちっ子地蔵』を読んだ瞬間、作品のインスピレーションが稲妻のように降りてきました。眠るのを忘れるくらい無我夢中で台本と楽曲を書き留めました。全2幕8景、26曲、公演2時間と、なかなかのボリュームです。ドラマの舞台は天明6年(1786年)の加須です。水害などの度重なる困難に屈することなく、助け合って前を向いて生きるお百姓さんたちの姿を描いています。現代のような科学技術はなく、物質も情報も豊かではない村落共同体の人々は何に価値を感じて生きていたのか? 現代人が忘れかけた大切な「何か」を思い起こさせてくれるのです。そして、いつも忘れはならないのは「土地に生きた先人たちの努力、犠牲、愛があったからこそ、現在の我々がある」をいうことです。脈々とつながる命、先人からの愛に感謝することが、光ある未来を導くと『いち』は教えてくれます。 「大きな社会は変えられない、まずは小さな社会から」-。土壌づくりに20年。故郷で愛の種を蒔き始めて約10年。それらが今、芽吹きはじめました。埼玉の小さな街から田畑を越えて、時空を超えて、これから新たな愛の連鎖が広がっていくのだと思います。 『野菊』 『翼をください』 『帰れソレントへ』 Profile 阿瀬見 貴光(あせみ・たかみつ)昭和音楽大学声楽科卒業。日本オペラ振興会オペラ歌手育成部18期修了。声楽を峰茂樹、L.Bertagnollio の各氏に師事。歌手としては都内のオペラ劇場を中心に活躍し、定期的なトークコンサート《あせみんシリーズ》では客席を笑いと涙の渦に巻く。その他、作曲家、台本作家、指揮者、演出家の顔を持つ部隊の総合クリエイター。完全オリジナル作品の代表作にミュージカル《いち》があり、これまでに5回の再演を重ねている。プロの舞台で培った技術や経験を地域社会に還元すべく、子どもの教育や生涯学習を目的としたアマチュア舞台芸術の発展に力を注ぐ。教育委員会等で講演を精力的に行い、芸術文化による地方創生の実践を伝えている。NPO法人ミュージカルかぞ総監督。ハーモニーかぞ常任指揮者。加須市観光大使。地元の酒をこよなく愛する四児の父。 関連リンク ・【Fゼミ】私の仕事 #1--デジタルマーケティングとオンライン販売 基礎・実践・【Fゼミ】私の仕事 #2--私が在籍してきた企業におけるマーケティング・【Fゼミ】私の仕事 #3--自分を活かす 人を活かす 原稿井坂 康志(いさか・やすし)教養教育センター教授
-

【Fゼミ】私の仕事 #3--自分を活かす 人を活かす
1年次のFゼミは、新入生が大学生活を円滑に進められるように、基本的な心構えや、ものづくりを担う人材としての基礎的素養を修得する授業です。このFゼミにおいて各界で活躍するプロフェッショナルを招へいし、「現場に宿る教養」とその迫力を体感し、自身の生き方やキャリアに役立ててもらうことを目的として、プロゼミ(プロフェッショナル・ゼミ)を実施しました。今回は、OL時代、自身の体調不良が玄米で改善した経緯から大阪で玄米カフェ実身美(サンミ)を創業し、顧客の健康改善事例に多く立ち合ってきた大塚三紀子氏を講師に迎えたプロゼミの内容をお届けします。 学生時代から就職まで 私は現在、㈱実身美を経営しています。本日は「自分を活かす 人を活かす」というテーマで私の経験をお話ししたいと思います。 最初に私の学生時代から始めたいと思います。私は法学部の出身なのですが、大学時代は正直なところやりたいことがありませんでした。何をしようかわからなかったというのが実感でした。法学部に在籍したことから、税理士事務所に就職はしてみたものの、やりがいは感じられませんでした。そのようなこともあり、しばらくして体調を崩してしまったのですね。 そんなとき、玄米食に切り替えたところ、めきめきと回復したのです。この経験は私にとって鮮烈なものがありました。そのとき思いました。体調不良の悩みを持つ人はきっと日本全国にいるはず。ならば、同じような方法で体調が回復することで喜びを共有することはできるだろうと。私自身が苦労したことをもとに、世の中の問題を解決できるのではないかと考えたわけです。そこで、事業を始めることにしました。これが私が経営者になったきっかけでした。 起業の経緯 実身美(サンミ)は、名前がコンセプトになっています。「実」があって「身」体に良くて「美」しい。すべて「み」と読みますから、3つで「サンミ」と呼ぶわけです。実身美は2002年に大阪市阿倍野区にて創業しています。現在は、玄米を主食とした健康食を提供しており、年間40万人以上のお客様にお届けしています。大阪阿倍野区、都島区、中央区、東京都、那覇市に5店舗を展開しています。 通信販売にも力を入れておりまして、独自開発の酵素ドレッシングは、全国お取り寄せグランプリ3年連続日本一(2017年全国4,400商品中1位、2018年全国4,730商品中1位、2019年全国5,131商品中1位)の評価をいただいております。現在でこそこのような高評価をいただいているものの、起業の時からすべてがうまくいったかというとまったくそうではありません。これから少しそのお話をしたいと思います。もともと食には興味があったのですが、起業となると何もわかりません。私はその分野にはまったくの素人でしたので、創業支援制度を利用して相談してみると、まずは「事業計画書を作成するように」と言われたのですね。ここで私は、コンセプトと数字の大切さを徹底的に学ぶことになりました。起業にあたって思いや志は何にもまして大切なものです。しかし一方で、現実に事業を成り立たせていくためいには、実にたくさんの具体的な行動が必要になってきます。 そこで大切なのは、仕組みづくりであり、数字をきちんと計算することです。たとえば、私は起業にあたって、公的金融機関からしかるべき融資をいただいたわけですが、それは言い換えれば借金をしたということです。借金をしたら、期限までに返さなければならないのは当然です。そこで、経営というものの責任を実感させられました。一度責任を引き受けた以上、何としてでもやらなければならないと決意しました。 そうなると、必要な費用を賄うのに、いくら必要か。これは痛いくらいの現実で、従業員やアルバイトさんの時給など掛け算すれば経費が出てきます。何で稼いで経費を払っていくか。これを計算しました。一日に必要な収入を割り出すと、ご来店54人という数字が出ました。これより少なかったら、店を成り立たせていくことはできないし、従業員にお給料も払えないわけです。 今にして思うのですが、「1日54人」の数字が出たから、私は成功できたのだと考えています。もちろん、お金だけではありません。店舗を展開していく中で、どうしても自分だけでは限界があります。人に働いてもらわなければなりません。自分がわかっているだけでは回らないのです。そのときはたと気づきました。どう人に動いてもらうかがわからなかったのです。そんなときに出合ったのが、「マネジメントの父」と言われているピーター・ドラッカーでした。 ドラッカー『仕事の哲学』との出合い 行き詰っていた時に出合ったのが、『仕事の哲学』というドラッカーの名言集です。2003年夏のことでした。まず感銘を受けたのが、「帯」の言葉です。 「不得手なことに時間を使ってはならない。自らの強みに集中すべきである」。 これは本当に救いになりました。その人にできることを生かさなければならない。生かせないならそれはマネジメントの責任ということです。この時期にビジネス界にも影響力を持つ人と出会えたのは幸福だったと思います。翌年2004年からはソーシャルネットワークで「ドラッカーに学ぶ」コミュニティも運営しはじめました。2007年には、翻訳者の上田惇生先生(ものつくり大学名誉教授)に勧めていただき、ドラッカー学会に入会して現在に至っています。 念のため、ここでドラッカーについて説明しておきます。1909年にウィーン生まれ。2005年にアメリカで没しています。「ビジネス界に最も影響力をもつ思想家」として知られる方で、東西冷戦の終結、転換期の到来、社会の高齢化をいちはやく知らせるとともに、「分権化」「目標管理」「経営戦略」「民営化」「顧客第一」「情報化」「知識労働者」「ABC会計」「ベンチマーキング」「コア・コンピタンス」など、マネジメントの理論と手法の多くを考案し、「マネジメントの父」と呼ばれています。今当たり前に通用している経営戦略とか目標管理などはドラッカーが発案したものです。 強みを生かすには 私がドラッカーから学んだ最大のものは、「強み」の考え方です。たとえば、ドラッカーは強みについて次のように述べています。 「何事かを成し遂げられることは強みによってである。弱みによって何かを行うことはできない」(『明日を支配するもの』) できないところに目を向けていてもしかたがありません。強みを集めて成果を上げるところまでもっていくことが大切だというのです。たとえば、経理の人はきちんと計算できれば、人付き合いできなくても成果をあげる上では問題ありません。むしろできることを卓越したレベルにまでもっていける。「強みを生かし、弱みを無意味にする」というのは、言うのは簡単なのですが、自己流だとうまくいきません。だんだんいらいらしてきます。人はなかなか見えないものだからです。 ではどう実践したか。実身美では、次の質問を投げかけています。「2人以上にほめられたことは何か」「2人以上に改善を求められたことは何か」一つ目については、「とても丁寧ですね。早いですね」といったささやかなことでよいのです。自分は大したことないと思っていても、強みは人が意外に知っているものです。スタッフ勉強会を開催して、隣の人のいいところを書いています。これを行うと、自分の気づいていないところがどんどん蓄積されて、新しい強みにも気づけたりする。「強みノート」を作成して、お互いの強みを理解し合えるように工夫しています。改善を求められたことについても同様に共有していきます。 強みに応じた人事としては、次のようなものがあります。社交性→百貨店担当学習欲→共同研究、HACCP取得、新規事業の把握責任感→マネジメント達成欲→成果が目に見える業務公平性→ルール作りのご意見番慎重さ→会社の危機を聞く、用意周到な準備が必要な案件コミュニケーション、共感性→お客様対応、広報指令性→プロジェクトリーダーポジティブ→ハードな現場収集心→リサーチ系の仕事(レシピ、店舗情報)着想→アイデアがないか聞く戦略性→成果へのプロセスを聞く さらに、気質や価値観も大切です。人には生まれ持っているものがあり、理由はわからないのにできてしまうことがあります。逆に、どんなに努力してもうまくできないこともあります。ドラッカーは次のように述べています。 「われわれは気質と個性を軽んじがちである。だがそれらのものは訓練によって容易に変えられるものではないだけに、重視し、明確に理解することが重要である」 人には教わっていないのにできてしまうことがあるのです。そういうものを生かしていきたいと考えています。なるべく人の持つ本質を大きく変えないようにすることで、生かしていきたいと考えています。 20年間存続するには--会社の文化づくり 最後になりますが、文化づくりについてお話したいと思います。私は文化の力はとても大きいと常々感じています。文化になれば言葉はいらなくなります。たとえば、日本では公共交通機関などでみんな並んで待つ文化がありますね。これは海外からすれば驚かれることです。それが文化の力であり、誰もが当たり前のようにやっていることです。 今日ものつくり大学に来て、みんなが気持ちよく挨拶してくれるのに感動いたしました。授業にもかなり前から教室に来ている。それはものつくり大学では普通のことかもしれませんが、立派な文化と言ってよいものです。文化になると人から言われなくてもできてしまう。これは、その文化の中にいる人を見れば伝わってくるものですし、本物の力だと思います。 なぜ実身美は20年継続できたのかを時々考えます。起業した企業が20年後に生き残っているのは0.3%と言われています。昔からあてにならないことを千三つと言いますが、まさに1000分の3の確率なのです。続けるのは難しいものです。ポイントは、学ぶこと、強みを生かすこと、そして「新しくしていくこと」です。続かないとは変われなかったということだからです。これは会社の文化といってよいと思います。 実身美では、継続学習とたゆまぬ改善活動を行っています。「丘の上の木を見ながら、手元の臼を引く」、すなわち、長期と短期をバランスさせる視点を大切にしています。ビジョンと現実の両方を見ながら、行くべき方向へかじ取りするのです。 最後に--マーケティングとイノベーション ドラッカーが言うのは、マーケティングとイノベーションです。ドラッカーは、「マーケティングとは販売を不要にすること」という有名な言葉を残しています。「買ってください」と言わなくても、お客様から「ほしい」と思っていただけることです。私は、自分が不便だと感じて、こんなのがあったらいいと思うことを大切にすることでした。自分も一人の顧客だからです。知人の本の編集者が教えてくれたのですが、「誰かにぴったり合うということは、その後ろに同じ感じ方をする人が30万人いる」という。それが独りよがりではなく、役に立ち、喜ばれるものになるのです。 イノベーションは新しくしていくことです。お店だったらいろんなメニューがありますね。消費者として、ほっとできるお店へのニーズがあるのに、それをベースにしているお店が少なかった。実身美の創業にはこのような思いもありました。そこで大切なのが顧客目線によるイノベーションです。お店の側は、自分が学んだイタリアンとか中華とかで勝負しようとしてしまいがちですね。果たしてそこに顧客目線はあるのかが疑問でした。自分の発想だけで出すと顧客からずれてしまいます。 自分が消費者だったらどうか。たとえば実身美では、冬に白湯を出すようにしています。というのも、通常の飲食店では、冬でも氷の入った水が出てくるところがあるからです。家ではありえないことですね。プロがそのようなことをしている。寒い時は常温の方がありがたいはずで、それだけでも感動してくれる人がいます。以前ジャーマンオムレツをメニューにしたいという意見があって、私はそこにトマトとかいろいろな野菜を入れたら魅力的ではと提案したことがあります。即座に「それではジャーマンオムレツにならない」という反論がありました。けれども、それは偶然私たちの知るジャーマンオムレツが、昔の人の保存がきくもの、じゃがいもとかしか使えなかった時代の遺物だったに過ぎない。それはものが不足していた時代に誰かが考えた苦肉の策なのに、今まったく違う現在でも踏襲してしまうのです。今はなすもトマトも入れられる。自分だったらこうするという具合に作り直していいのです。酵素ドレッシングもそうです。以前は、茶色で調味料というのが大半でした。生の良さを生かす「食べるドレッシング」という発想がなかった。それを顧客目線で開発した。 本日は「自分を活かす 人を活かす」というテーマで私の経験をお話しました。ものつくり大学の学生の皆さんに少しでも役に立てれば嬉しいです。ありがとうございました。 Profile 大塚 三紀子(おおつか・みきこ)㈱実身美 代表取締役関西大学法学部卒。OL時代、自身の体調不良が玄米で改善した経緯から2002年大阪で玄米カフェ実身美(サンミ)創業。20年間で玄米食を約500万食提供し、顧客の健康改善事例に多く立ち合う。玄米の機能性に感銘を受け、2017年度より、琉球大学医学部第二内科益崎教授研究室と玄米の機能性食品の共同研究開発を開始。働く女性を対象にした臨床試験を通じ、玄米の機能性成分がアルコール依存を軽減させる効果を認める。2019年~2023年 沖縄科学技術イノベーションシステム構築事業委託共同研究採択2022年 『特許庁 社会課題解決×知財 IOPEN プロジェクト~脳のデトックス効果のある玄米食を通じて社会ストレスを解消させる挑戦~令和3年度IOPENER』。ドラッカー学会会員。著書に『実身美のごはん』『実身美の養生ごはん』ワニブックス社がある。(累計2万9000部)『実があって身体に良く美味しい』をコンセプトにした商品開発を得意とする。酵素ドレッシングはベストお取り寄せ大賞3年連続総合大賞受賞(2019年度5,131商品中1位)他受賞多数。 関連リンク 【Fゼミ】私の仕事 #1--デジタルマーケティングとオンライン販売 基礎・実践 【Fゼミ】私の仕事 #2--私が在籍してきた企業におけるマーケティング 【Fゼミ】私の仕事 #4--歌手としての歩みとライフワーク 原稿井坂 康志(いさか・やすし)ものつくり大学教養教育センター教授
-

【Fゼミ】私の仕事 #2--私が在籍してきた企業におけるマーケティング
1年次のFゼミは、新入生が大学生活を円滑に進められるように、基本的心構えや、ものづくりを担う人材としての基礎的素養を修得する授業です。このFゼミにおいて各界で活躍するプロフェッショナルを招へいし、「現場に宿る教養」とその迫力を体感し、自身の生き方やキャリアに役立ててもらうことを目的として、プロゼミ(プロフェッショナル・ゼミ)を実施しました。今回は、外資系企業を中心に7社の在籍経験があり、約23年にわたってマーケティングに従事している平賀敦巳氏を講師に迎えたプロゼミの内容をお届けします。 マーケティングとは何か 本日の話の流れとして、まず初めに、「マーケティング」とは何を意味する言葉なのかを説明して、全体像をつかみ、その上で「マーケティング」に含まれる具体的な仕事の種類を説明します。そして、より個別具体的に、私が在籍してきた企業でどんな仕事に実際に取り組んで来たのか、事例を紹介しながら説明します。 現在、担当している商品、当日学生に配布された まず、大家と言われる3名の方が、「マーケティング」をどのように定義しているか?ハーバード大学教授のレビットは、マーケティングとは「顧客の創造」だと言いました。「マーケティングの父」の異名をとるコトラーは、「個人や集団が、製品および価値の創造と交換を通じて、そのニーズやウォンツを満たす社会的・管理的プロセス」という、大変緻密な定義を行っています。そして、有名な経営学者であるドラッカーは、マーケティングとは「セリング(販売)を不要にすること」だと語りました。では、私は、マーケティングをどのように定義しているか。二つの○と、それを結び付ける両向きの矢印を使って、図で説明をすると分かりやすいのです。片方の○は、生活していく中で様々な課題なり欲求を抱える消費者、生活者。もう片方の○は、そういった課題を解決し、欲求を満たすリソースを持つ事業者。これら二つの○を結び付けてあげると、そこに取引が生まれ、市場が生まれます。この、市場をつくるために両者を結び付けてあげることがマーケティングなのですね。 MarketingというのはMarketにingが付いていることから分かる通り、「Marketすること」という意味。要は、「市場を作ること」がマーケティング、市場をつくり、より大きくするために、色々な働きかけることが全てマーケティング活動と言えます。こう定義すると、マーケティングというのはとても広い概念で、ほぼ「経営」と同じ意味合いになります。とはいえ、経営活動の中には、人事、経理・財務、IT等々、確かにマーケティングとは言いにくいものも含まれるので、私は以下のように整理しています。経営=直接お客様に働きかけて市場を作る広義のマーケティング+間接業務広義のマーケティング=狭義のマーケティング+セリングコトラーは、このマーケティングの全体像を、「R-STP-MM-I-Cモデル」という枠組みで整理しました。R=Research(リサーチ・調査や情報収集)STP=Segmentation(セグメンテーション・市場を分類すること)、Targeting(ターゲティング・お客様を絞ること)、Positioning(ポジショニング・お客様の頭の中での居場所、位置付けを決めること)、これらの頭文字で、マーケティングの戦略部分。MM=Marketing Mixの略でいわゆる「4P」と言われるものと同じ意味。4Pとは、Product(商品)、Price(価格)、Place(販路)、Promotion(販促)の4つのPから始まる要素を指し、マーケティングの戦術部分。I=Implementation(実行)の頭文字。頭の中で考えた戦略や戦術は、実際に実行に移されないことには現実が変化しないので、実行はとても大切です。C=Control(改善)の頭文字。俗にいう「PDCA」。実行したら必ず結果を評価して、上手くいった点は維持し、上手くいかなかったことは改善する。そのプロセスを繰り返すことが重要です。 「お客様」を知ること ビジネスをする場合、通常何らかの目的を持って始めます。その目的を達成するために、様々な商品を取り扱い、その商品を市場で売れるようにするために、先程の「R-STP-MM-I-Cモデル」に沿って、戦略を考え、戦術を練り、それらを実行に移していきます。マーケティング戦略を考える上では、まず何よりも先に、市場の一方当事者である「お客様」を知ることが重要です。お客様は、何かしらモノを買うまでに、様々な段階を経て意思決定しますが、この時の心の流れを「パーチェスファネル」などと呼びます。ファネルとは、漏斗(じょうご/ろうと)で、必ず上が広く、下に行くに従って細くなります。基本的に、認知、興味、行動、比較、購入という段階を踏んで、ようやくモノを買ってくれることになるわけで、段階を進むごとに離脱する人も出て来るため、必ず下へ行くほど細い。このパーチェスファネルを、出来るだけ横に広げていくことで、市場がつくられ、大きくなる。また、下の方をより太らせて逆三角形から台形に近付けていくことで、更に市場が大きくなる。なので、各段階の間口を広げること、そして次の段階へと進む確率を上げること、それを実現することがマーケティングの仕事のイメージとなります。お客様が持っている顕在ニーズと潜在ニーズ(ホンネ)を、質的調査(ヒアリングや観察)や量的調査(アンケート、データ分析)を通じて調べ上げたら、そのニーズを満たすことを考えなければなりません。そのために、「コンセプト」を練り上げます。コンセプトの要素は、よくABCで整理されます。A:Audience・お客様B:Benefit・便益、嬉しさC:Compelling Reason Why・お客様がその嬉しさを得られると信じるに足る理由お客様に選ばれる商品をつくるには、Aの誰を相手にするのか、Bの相手が喜んでくれそうな何を提供するのか、そしてCのそれがいかに良い商品だと分かるような根拠をどうやって伝えるか、これらABCをワンセットで提供しなくてはなりません。3つ目の、お客様に提供する「根拠」については、3つの「差別化軸」(①手軽軸、②品質軸、③密着軸)を活用します。 私が在籍してきた企業の具体例 ①女性用カミソリのポジショニング圧倒的なシェアを持っていた競合の商品が、ハッキリとしたポジショニングを持っていない点に気付き、消費者のニーズに基づいた明確なポジショニングで「挟み込み」を行った結果、多くの売場を獲得し、シェアの逆転につなげることができました。②商品をラッピングしてギフト化し、価値を高めて価格を上げる一つだと安価なキャンディを、沢山集めてお花のブーケのようなラッピング仕立てにすることで、単価を上げて発売しています。キャンディだけで比較すると割高ですが、ギフトとしての価値を創り出すことで多くの方に買い求めていただいています。 ③商品カテゴリによるコスト構造の違いと値付け化粧品や日用雑貨で様々な商品を扱ってきた中で、売価と原価の関係はカテゴリによってバラバラであることを見て来ました。より多くの粗利を稼げるカテゴリでは、その粗利を原資にして、広告や販促を展開し、逆に粗利が低いカテゴリでは、ギリギリ安値でとにかく数をさばくというやり方になっています。④小売店のバイヤーとの「棚割」商談における資料作成小売店では半年に一度、「棚割」といって棚に並べる商品の入れ替えを実施しています。消費者に商品を買ってもらう機会を確保するために、棚割で自分のところの商品がなぜ必要なのか、ロジックを組み立て、説得を試みます。⑤TVCM制作広告代理店に依頼をして、誰にどんなメッセージを伝えたいのかを説明し、目的に応じたクリエイティブを制作してきました。⑥店頭販促消費者は、「期間限定」だったり「お買い得」といったメッセージ、見た目に反応することが多いので、店頭でより多くの人に、より頻度高く買っていただくための工夫を様々に行ってきました。⑦DMを用いた店頭への集客化粧品会社で、愛用顧客の方に再び店頭へと足を運んでもらうために、凝りに凝ったDMを送付していました。頻繁に新商品を出し、常に店頭を新鮮に保って、DMによる集客でにぎわいを創り出していました。 Profile 平賀 敦巳(ひらが・あつみ) 1972年東京都出身、横浜市在住1996年慶應義塾大学大学院法学研究科修了(法学修士)外資系企業を中心に7社の在籍経験。27年強のキャリアのうち、約23年マーケティングに一貫して従事。これまでに取り扱ってきた商品は、主に日用雑貨と化粧品を中心に、洗剤や家庭紙(トイレットペーパーやティッシュペーパーなど)、スキンケアやヘアケアやボディケア、カミソリ、香水、キャンドル、保険などが挙げられる。マーケティング戦略の立案から、商品・コンセプトの調査や開発、値決め、チャネル開拓、広告宣伝・PR、販売促進に至るまで、幅広い経験を積んで来た。現在は、ベルフェッティ・ヴァン・メレ・ジャパン・サービス株式会社に勤務、カテゴリーマネージャーとしてメントスとチュッパチャップスの二つのブランドを管掌。 関連リンク 【Fゼミ】私の仕事 #1--デジタルマーケティングとオンライン販売 基礎・実践 【Fゼミ】私の仕事 #3--自分を活かす 人を活かす 【Fゼミ】私の仕事 #4--歌手としての歩みとライフワーク 原稿井坂 康志(いさか・やすし)ものつくり大学教養教育センター教授
-

【Fゼミ】私の仕事 #1--デジタルマーケティングとオンライン販売 基礎・実践
1年次の「Fゼミ」は、新入生が大学生活を円滑に進められるように、基本的心構えや、ものづくりを担う人材としての基礎的素養を修得する授業です。このFゼミにおいて各界で活躍するプロフェッショナルを招聘し、「現場に宿る教養」とその迫力を体感し、自身の生き方やキャリアに役立ててもらうことを目的として、プロゼミ(プロフェッショナル・ゼミ)を実施しました。大企業勤務、起業、コンサルティングなど多様な活動をし、現在は日本工芸株式会社 代表取締役を務める松澤斉之氏を講師に迎えたプロゼミの内容をお届けします。 とにかくいろんな仕事をしてきた この27年を振り返ると、私は大企業に勤めたこともありますし、第三者としてコンサルをしたこともあります。自分で会社を立ち上げて経営してきたこともあります。とにかくいろいろな活動に携わってきた自負はあるのですね。 現在も、自分の会社を経営していますが、SBI大学院大学のMBAコースで講師も務めていますし、企業の研修を行ったり新規事業のコンサルティングもしています。早稲田大学、広島大学などで「デジタルマーケティングとオンライン販売の実践」について講義をしたり、福岡県物産振興会、東京都中小企業振興公社、新宿区立高田馬場創業支援センターなどで「企画発想力人材」の育成・活用、EC活用などについて相談に乗ったりもしています。その他企業内では事業開発、EC加速、越境EC立上げ、など様々なテーマでレクチャー+立上げ支援を実施しています。 こういう生き方は、学生時代、すなわち皆さんと同じころのつまり二十歳あたりの頃のある思いに遡れると思っていますが、それについては最後にお話ししたいと思います。 新卒で就職した会社の倒産 私は東京理科大学の出身です。とにかく旅行が好きで、バックパックを背負って世界中を旅行して回っていました。在学中は中国の四川大学に1年間の短期留学もしました。これには元来の『三国志』好きが大いに関係していたと思います。 1996年に大学を卒業してから、ヤオハンジャパン社に入社しました。大学時代中国に留学したこともあり、アジア展開に注力する会社で働きたいと考えたからです。ヤオハンは小売業で、1990年代の前半までは飛ぶ鳥を落とす勢いの躍進を続けていました。ところが、この巨大な一部上場企業が、私が入社した翌年に倒産してしまいます。これは日本の企業史に残る巨大な倒産としても知られています。これはなかなかショックな出来事でありましたが、就職先の倒産を機に私の人生が本格的に始まったと言ってもよいかもしれません。その後、しばらくの間、東南アジアなどからの輸入水産商社にて製品開発・輸入及び国内販売に従事していました。やはりアジア諸国との仕事をしたくてヤオハンに入ったわけですから、その思いはずっと心にとどまっていたからです。日々とても忙しかったけれども、充実していました。 たいてい人は何かに一生懸命打ち込んでいれば、必要な出会いは向こうからやってきてくれるものです。私の場合、勤め先の倒産から数年してからでした。それは日本を代表するコンサルタント・大前研一氏との出会いです。このご縁から、1999年、大前氏の起業家育成学校(㈱ビジネス・ブレークスルー)の立ち上げに参画する幸運に恵まれました。私が従事したのは国内最大規模の起業家育成プログラムを提供するスクールです。これを機に、同スクールの企画運営に関する統括責任者となり事業戦略・マーケティングを立案・実行してきました。社内新規事業として、企業内アントレプレナー育成サポート事業を立ち上げ、リクルート、三井不動産、NTTドコモなどの大手クライアントを獲得することに成功し、マザーズ上場にも貢献できました。 ビジネス・ブレークスルーから約7年がたち、自分自身もいつか起業することを考えていましたので、2006年、新規事業開発支援のコンサルティング会社フロイデの設立に参画し、役員に就任しています。これは、事業規模に関わりなく、新規事業をスタートしたいという企業は実に多いものの、そのための人員もリソースも不足していて、なかなか着手できずにいる状況を機会と考えたためです。新規事業の専門家は世の中にさほど多くなかったのも理由の一つです。実際に着手してみると、相談件数も着々と伸びて、ホンダ、日経新聞、パナソニック、NEC、東京電力などかなり大手企業の事業開発事案に携わることができました。このフロイデという会社は現在も関わりを持っており、私の複数の活動の一つとして、現在も新規事業のコンサルティングを続けています。 40歳を目前にAmazonへの転職 その間世の中は大きく変化を続けており、私としても、ネットによる世の変化を直接目で見て、学び取りたいという思いがふつふつと湧き上がってきました。そんなときに、Amazonジャパンの求人があることを知り、すでに40歳を目前としていたにもかかわらず応募したら合格してしまいました。ここから、私の大企業との関わりが再度始まったことになります。就職して翌年で倒産したヤオハン以来です。 私がAmazonに入ったのは2012年6月でした。このAmazon体験は、私にとってとても大きなものをもたらしてくれたと思います。まずはインターネット通販 Amazonジャパンホーム&キッチン事業部に配属され、バイイングマネージャーとして販売戦略の立案と実行を任されました。これはかなり重要なポジションで、会社としても私のこれまでの経験やスキルを十分に生かせるように配慮してくれたのだろうと思います。 Amazonで得たことは実に多いのですが、私は三つあると考えています。一つはEC、すなわちネットビジネスの基本が理解できたことです。ECとは何のことかといえば、6つの要素、商品、物流、集客、販売、決済、顧客からなっています。これらへの対応、作戦計画を行うのがバイヤーの仕事です。AmazonのECは世界最高と言ってよく、仕入れはもちろんのこと、マーケティングやアフターサービスまで、多くを学ぶことができました。この体験は独立している現在、とても役に立っています。 第二が世界最高レベルの組織です。Amazonの構築した組織は、巨大でありながら実に柔軟であり、機能的でした。Amazonの組織の一員であることによって、特に大きな組織を動かすためのエッセンスのようなものが会得できたと思っています。 最後がビジネス・パートナーです。仕事をしていると仲間ができます。その仲間がいろいろな情報をもたらしてくれますし、私もいろいろな情報をシェアしたりします。そのような人間関係は、会社を辞めた後も続きます。「人脈」という言い方もしますが、これは仕事の醍醐味だと思います。 Amazonは今あげた三つの要素のどれをとっても一流であったのは間違いありません。その恵まれた環境の中で、とにかく日々の商談を行いました。結果として2,000社以上のEC化サポートの経験を積み上げることができました。 日本工芸㈱を設立--想いをつなぐ工芸ギフトショップ 私がAmazonに在籍したのは約4年です。いつかは独立しようと考えていましたから、退職は当初より織り込み済みでした。私が再び事業を立ち上げたのは、2016年12月のことです。Amazonを退職し、工芸品の越境EC運営を生業とする日本工芸株式会社を設立しました。「想いをつなぐ工芸ギフトショップ」をキャッチコピーにしています。仕事内容は伝統工芸領域のプロデュース・販売事業です。日本の伝統工芸のすばらしさを世界に知っていただきたいと思い、スタートしました。 詳しくはHPをご覧ください。https://japanesecrafts.com/ それ以前から、新規事業開発アドバイザーは長く従事しており、専門領域は、新規事業案策定、実行支援、事業創出の仕組みづくり、人材育成、EC戦略立案、集客支援など多様に展開させていただいています。 私は日本工芸㈱のビジョンを「日本の工芸、職人の技と精神性・製法・技法に宿るこだわりやプロセスを理解し、商品流通・教育など通して製品を愛する日本内外の人、世の中に広げていく」としました。日本ではたくさんの優れた職人がおられ、日々逸品の製作に励んでいます。しかし、伝統工芸品は1983年の5,410億円をピークに、2015年は1,020億円と5分の1にまで減少しています。売上減少に伴い、人手の不足、新商品開発への対応不足なども加わって産地の生産・流通は構造的に疲弊してきているのが現状です。これには、昨今の百均などに見られるように、消費者動向に添う効率よい商品調達・流通が大きく関係しています。所得・消費も減少していますので、「安くてそこそこの」ものに消費者がどんどん吸い寄せられているのでしょう。それに対して、専門店やECなどが十分に対応できていないのではないかということも、日本工芸㈱立ち上げの原動力になっています。 そのために、選定したブランド、産地、工芸品を不易流行なブランドとして発掘するところから始めます。職人さんとじっくり語り合い、文章と画像で語り、販売するようにしています。こうすることによって、国内でハンドメイドによる工芸品をセレクトしてお客様に提供する、目利き役も務めています。それぞれの職人は小規模ですから、広告や大規模なプロモーションを打つことはできませんし、その知識も乏しいのが実情です。日本工芸㈱が行いたいと考えるのは、職人さんに職人さんらしい仕事をしてもらうことです。そのほかの面倒なことは引き受ける。その価値を理解してくれる全国のお客さんをインターネットによって仲介・プロデュースしています。最近では法人による購入も増えてきました。 死ぬまで挑戦したい 私は現在で50歳です。今までいろいろな事業に携わってきました。大企業勤務、企業、コンサルティングなどなかなか経験できない多様な活動ができたのは本当にありがたかったと思います。 事業の形態は実にいろいろあるのですが、私は一番大事なのは「人」だと思うのですね。経営学者のドラッカーも、経営的問題は結局は人の問題に帰着すると語っていたかと思います。私にとっては、仕事そのものの大切さもさることながら、その仕事が社会的に意味を持つためには、やはり人との関係を創生するものがなくてはならないと考えています。新規事業のコンサルを始めたときも、Amazonでの開発業務も、日本工芸㈱の企業もつまるところは、人の力になりたいし、私自身もそこから力を得たいという思いがあったためだと思います。早いうちに海外に出たことで、いろいろな人に会うことができましたし、多くの体験をすることができました。社会人になってからも、ずいぶんたくさんの国を旅行やビジネスで訪れました。これは私が職場を始め居場所をどんどん変えてきたことも関係していると思うのですが、それによって変化していくことが恐くなくなってきたということは言えると思います。世の中は何もしなくても変わっていくものです。むしろ変わっていくことがこの世の本来の姿です。変化していくことを後ろ向きにではなく、積極的に活用していくような生き方を結果としてしてきたように思います。 私は社会人になって27年目になります。その意味では私は一社に就職して長く勤め上げる人生を送ってきたわけではありません。現在もなお複数の仕事を同時に行っています。おそらく現在学生の皆さんも、一社で勤め上げるのではなく、適宜ふさわしい仕事や会社で働いていく人生になると思います。 思い起こせば、学生時代、私はあることを考えるようになりました。それは人はいつか死ぬということです。それはいつかの問題であり、避けることのできないことです。そうであるならば、私は死ぬときに100名の友人がいる状態を理想と思うようになりました。死ぬときに100名。これを実現するためにこれから生きていこうと思ったのです。私の人生ビジョンは「挑戦する精神とともに成長する」です。死ぬまで挑戦して生きたいと日々考えています。挑戦するとは、いつでも生き方を変える準備があるということです。 大学生の皆さんは、現在基礎を築く大事な時期にいるのですから、ぜひ日々を大切に送っていただきたいと思います。技能や技術を担うテクノロジストの皆さんにとって本日のお話が何らかの参考になればと願っております。 Profile 松澤 斉之(まつざわ・なりゆき)1996年 東京理科大学卒業、在学中に中国四川大学に留学同年、ヤオハンジャパンに入社するも翌年倒産1999~2006年 大前研一氏のベンチャー(現㈱ビジネス・ブレークスルー)に参画、マザーズ上場2006年~現在 新規事業開発会社(㈱フロイデ)に参画2012~2016年 アマゾンジャパン ホーム&キッチン事業部シニアバイイングマネージャー2016年~現在 日本工芸㈱ 代表取締役、国内外EC事業、プロデュース事業(卸)、販路開拓支援事業を実施2017年~ SBI大学院大学講師(事業計画演習)2019年~ 独立行政法人中小企業基盤整備機構 中小企業支援アドバイザー 関連リンク 【Fゼミ】私の仕事 #2--私が在籍してきた企業におけるマーケティング 【Fゼミ】私の仕事 #3--自分を活かす 人を活かす 【Fゼミ】私の仕事 #4--歌手としての歩みとライフワーク
-

【学生による授業レポート】ジジジジッ、バチバチッ…五感で学ぶ溶接技術
今回は、学生の目線から授業を紹介します。建設学科1年の佐々木望さん(上記写真左)、小林優芽さん(上記写真右)が「構造基礎および実習Ⅳ」のアーク溶接実習についてレポートします。実習を通じて、学生たちは何を感じ、何を学んでいるのか。リアルな声をお届けします。(学年は記事執筆当時) ものつくり大学の授業について ものつくり大学の特色…それは何といっても実習授業の多さです。なんと授業のおよそ6割が実習であり、実践を通して知識と技術の両方を身に着けることができます。科目ごとに基礎実習から始まり、使用する道具の名称や使い方などを一から学ぶことができます。 本学は4学期制でそれぞれを1クォータ、2クォータと呼び、1クォータにつき全7回の授業と最終試験を一区切りとして履修していきます。今回は、そんな授業の中で建設学科1年次の4クォータで履修する「構造基礎および実習Ⅳ」のアーク溶接実習について紹介します。 アーク溶接の実習とは まず、アーク溶接について簡単に説明すると「アーク放電」という電気的現象を利用して金属同士をつなぎ合わせる溶接方法の一種です。アーク溶接の中にも被覆、ガスシールド、サブマージ、セルフシールドなど様々な種類がありますが、この実習では一般的に広く使用されている被覆アーク溶接を行いました。 アーク溶接の様子 この授業は、講義の中で溶接の基礎知識や安全管理等の法令を学び、実技を通してアーク溶接の技術を身に付けることを目的としています。また、6回目の授業で突合せ板継ぎ溶接の実技試験、7回目の授業で「アーク溶接等作業の安全」をテキストとした試験を行います。その試験に合格した学生には特別教育修了証が発行され、アーク溶接業務を行えるようになります。 実技試験の課題 突合せ溶接 実習では平板ストリンガー溶接、T型すみ肉溶接、丸棒フレア溶接、突合せ板継ぎ溶接といった、数種類の継手の面やコーナー部を溶接する練習を行いました。また、講義では鋼材に関する知識、溶接方法の原理、作業における安全管理、品質における溶接不良の原因や構造物への影響等について学び、試験に臨みました。 実習の流れとしては、まず作業の前に溶接方法の説明を受けます。その後、皮手袋やエプロン、防じんマスク、保護面等の保護具を着用して、3~4人で一班になり、各ブースに分かれて順番に練習を行います。作業中は、実際に現場で活躍されている非常勤講師の先生が学生の間を回り、精度の高い溶接ができるようアドバイスや注意をしてくれます。溶接金属やその周囲は非常に高温になるため、他の実習よりも危険なポイントが多いので作業中だけでなく、準備・片付けもケガ無く安全に行えるよう毎回KY(危険予知)活動をしてから実習に臨みました。 実習を行ってみて 説明ばかりでは授業の様子を想像するのも難しいですよね…。ということで、実際に授業を受けた建設学科1年、小林と佐々木の感想をお届けしたいと思います! ・何を学ぶことができたか 【小林】アーク溶接とは何かを学ぶことができました。もっとも、それを教わるための講義なので何を言ってるんだと思われてしまいそうですが、そもそも私は溶接と無縁の生活を送ってきたので、アーク溶接ってなに?というか溶接ってなんだよ。というところから入りました。1回目の講義の際、どのようなものが溶接で作られているのか紹介していただいたのですが、ほとんどが知らなかったことだったので、とても面白かったのを覚えています。 【佐々木】溶接というのは非常に優れた接合方法だということを学びました。溶接は継ぎ手効率が高く、大型の構造物を作るのに適しています。あの東京スカイツリーはなんと37,000ものパーツを全て溶接することで作られていると知り、世界一高い塔を作る溶接という技術がこんなに小さな機械で、こんなに簡単にできるものなのだと驚きました。また、一口に溶接といっても用途によって材料や溶接方法、継ぎ手の種類などが様々で、その違いを興味深く学ぶことができました。 ・楽しかったこと 【小林】アーク溶接を実技として教わったことがすごく楽しかったです。非常勤の先生方がとても優しく、どのようにすればいいか、どのくらい浮かすのか、どの音で進めていくのかなど一緒に動かしたり、その都度「今離れたよ。もう少し近付けて。そう、その音」と声をかけてくれたりして理解できるようにしてくださったので、すごく分かりやすかったです。そのおかげで綺麗に溶接ができるようになり、すごく褒めてくださることもあって、とても楽しく実習をすることができました。先生が「初めてでここまでできる人は初めて見た」とまで言ってくださったので、とても嬉しく、褒められればやる気が出る単純なタイプなので、やる気もすごく出ました。 【佐々木】練習を重ねて、アドバイスを実践していく度に溶接の精度が上がり、目に見える形でできるようになっていくのが楽しかったです。溶接は五感がとても大切で、保護面越しで見るアーク放電の光だけでなく、ジジジジッ、バチバチッといった音の違いや溶接棒越し感触を頼りに集中し、真っすぐに溶接できた時にはとても達成感を感じました。班の中でも上手な学生から感覚を教えてもらったり、説明を受けながら溶接の様子を見学することで、より学びを深めることができたと思います。講義では、先生から現場での実体験を交えてお話いただいたおかげで楽しく知識を身に着けることができたので、苦にすることなく試験勉強に取り組めました。 実習中の様子 ・苦労したこと 【小林】T字の材料に溶接するところがすごく苦労しました。平面とはまた違った角度をつけて溶接しなければならず、どうにもそれが難しかったです。1層目の溶接は擦りつけながら溶接すると言われ、この前までは浮かせるって言ってたのに?と混乱している中、追い打ちで「この前とは違う角度で溶接する」と言われてしまい、思考が停止したのをよく覚えています。さらに、そのことに気を取られ、前回できていた適切な距離を維持することができなくなり、手が震えて作業している場所が分からず、ズレてガタガタになることを経験して、やっぱり一筋縄ではいかないんだと痛感しました。 T型すみ肉溶接 【佐々木】被覆アーク溶接というのは、細長い溶接棒と溶接金属の母材を溶かし合わせてつなぎ合わせる方法で、溶接を進めるほど溶接棒が溶けていくので、母材と溶接棒の距離を保つのが難しく、溶接の後が上下にずれてしまい大変でした。アークの光が明るすぎて目視では距離の確認ができずに困っていたら、「正しい距離を保てば見えるようになる」と教えてもらい、それからは以前より真っすぐに溶接できるようになりました。また、溶接不良を何か所も発生させてしまい、溶接不良が原因で鉄橋が崩落した大事故についても学んでいたため、仕事としての難しさや、構造物を作っている技術の高さを改めて感じました。 最後に 私たちの授業紹介はいかがでしたでしょうか?建設学科では、今回紹介した構造基礎の授業だけでなく、設計製図や木造、仕上げといった幅広い分野について実習を通して学び、知識と技術を身に着けることができます。 この記事を通して「ものつくり大学って面白そう!」「他にどんな授業をしているのかな」と少しでも興味を持っていただけたらとても嬉しいです。 最後までお読みいただきありがとうございました。 原稿建設学科1年 佐々木 望(ささき のぞみ) 小林 優芽(こばやし ゆめ) 関連リンク ・【学生による授業レポート #2】受講後もSA(スチューデント・アシスタント)を通じて深める学び・建設学科WEBページ
-

先輩たちへの感謝を胸に大会へ ~第18回若年者ものづくり競技大会②~
2023年8月1日から2日にかけて静岡県で第18回若年者ものづくり競技大会が開催されました。本学では建設学科から2名(建築大工職種1名、木材加工職種1名)の学生が出場し、建築大工職種で金賞、木材加工職種で銀賞という好成績を残すことができました。今回は木材加工職種で銀賞を受賞した入江 蛍さん(建設学科1年・静岡 科学技術高等学校出身)に、大会に出場した感想を伺いました。※木材加工職種の競技は、「小いす」を製作します。原寸図の作成、ホゾ(木材を接合する部分の突起)、ダボ(部材をつなぎ合わせる小片)による接合の加工、接合部の組み立てなどを行います。 慣れない作業に苦戦する毎日 入学当初から技能五輪全国大会に出たいと思っていました。友人から若年者ものづくり競技大会には1年生から出場できる事を聞き、早速、学内の掲示板を探しました。ものづくりに興味を持ったきっかけは、手先が器用な祖父が趣味で水車や離れを作っているのを見てきたからです。その後、大工仕事を学んでみたいと思って、高校で建築大工の技能検定を受けたり、高校生ものづくりコンテストの木材加工部門に出場しました。大工や家具、左官など色々なことに興味があって、ものつくり大学に入学したので、若年者ものづくり競技大会ではどの職種に挑戦するか迷いましたが、やったことがなかった家具に挑戦したいという思いから出場しました。練習は入学してすぐに始めました。大会出場を目指している新入生5人で先輩方に教えてもらいながら、毎日毎日練習をしました。先輩方は、日付が変わるくらいの時間まで常に教えてくださったのでびっくりしました。「まだ23時だからこれからノコやろう」とか日付をまたぐこともあったりして、時間の感覚がおかしくなっていました(笑)。授業もあって大変でしたが、昼夜を問わず練習できるのは良かったなって思います。それに、高校ではいつも一人で練習していたので、予選を受ける友人たちと一緒に、先輩方の指導を受けることができ、頑張ることができる環境はありがたいと思いましたし、だからこそ成長できたのかなって思います。 先輩との練習の様子 大工と家具では木材の大きさも道具も違いますが、少しは大工の経験があるから上手くできるかと思っていました。でも、予想以上に違いがありました。最初は、木材を切るにしても縦引き横引きが真っすぐできなくて、ぴったり合いませんでした。また、家具では白柿(しらがき)という罫書き線を引くための道具を使います。大工では墨差しや差し金を使って墨付けをするので、白柿を使ったことがありませんでした。持ち方もコツが必要で、垂直に線を引くのも難しかったので持ち方から慣れる必要がありました。家具の作業は考えることがすごく多かったです。刃には、しのぎ面という斜めになっているところがあって、そこが加工する側にくるようにとか、線を引くのもどの向きにとかスコヤをどこに当てるのかなど、ただの墨付けではあるんですけど、考えながらやる必要がありました。上手くできるようになったのは5月の学内予選の頃です。予選の時に、縦引きも横引きも最初に比べて真っすぐ切れるようになりましたし、ノミでの作業も綺麗にできるようになってきました。 わずかな隙間 高校生の時は、検定を受ける時も大会に出る時も自信を持てるまでずっと練習をしていたので、あまりプレッシャーを感じることはありませんでした。だけど今回は、本番一週間前までは何回やっても標準時間内に完成できませんでした。やればやるほど課題が見つかって、上手くいかないことがどんどん増えて焦っていました。練習で最後の最後まで納得がいく作品を作れなかったので、緊張していました。それに、本当に多くの方に教えていただいたので、期待に応えたいという気持ちがあったけど不安でした。練習では、標準時間にプラス30分程度かかって完成していましたが、それでは減点になってしまいます。金賞を狙うからには、時間内に作って減点を抑えようと思って大会に臨みました。午前中は思いのほかペースが良くて予定外のところまで作業が進んでしまいました。残りの5分は何をしたらいいのかというくらい余裕が出てしまい、掃除などをしていました(笑)。今にして思えば、ここでもうちょっと考えて進めておけば良かったなと思います。午前は驚くほど調子が良かったのですが、午後になり、最後の一番大事なところを綺麗に切れなかったことを後悔しています。練習の時も上手くいかなくて改善策を見つけて挑みましたが、今一つ上手くいかず隙間がわずかにできてしまいました。仕上げの時に、やすりをかけたり、ボンドで埋めたりして隙間を少しでも埋めるために調整して何とか仕上げました。不安だった作業時間は、標準時間よりプラス10分かかりました。プラス5分ごとに1点減点されてしまうので、出来栄えと減点を秤にかけて作業を終了することを目安にしていました。 完成した課題は、1か所隙間があり納得のいくものではなかったので「金賞は難しいかな」と思いました。でも、やってきたことに後悔はないのでその時の最大限の作品は作れたと思っています。今回、銀賞を受賞することができましたが、「やっぱり金賞取りたかったなぁ」って残念な思いです。でも、作品の出来栄えからすると入賞できて、先輩方の期待に少しは応えることができてほっとしています。先輩方には本当に毎晩遅くまでたくさん教えていただいたので感謝の気持ちでいっぱいです。 やりたい事がいっぱい 色々興味はありますが、建築士になりたいという目標があります。設計する上で、大工や左官のことも分かっていたほうが良いと思うので、まずは、1年生2年生のうちに左官や設計、資格取得など色々なことを経験したいと思います。実習が豊富だから仕上げや木造の実習も頑張りたいです。もうすぐインターンシップ先を決める時期ですが、どの分野に行くかすごく迷っています。本当は、これと決めた分野を究めていったほうがいいとは思っているんですけど、やっぱり色々なことに挑戦して経験を積んでいきたいです。 関連リンク ・練習で磨いた100%の技術を ~第18回若年者ものづくり競技大会①~・若年者ものづくり競技大会 大会後インタビュー・若年者ものづくり競技大会実績WEBページ・建設学科WEBページ
-
.jpg)
【Fゼミ】私の仕事 #4--歌手としての歩みとライフワーク
1年次のFゼミは、新入生が大学生活を円滑に進められるように、基本的な心構えや、ものづくりを担う人材としての基礎的素養を修得する授業です。このFゼミにおいて各界で活躍するプロフェッショナルを招へいし、「現場に宿る教養」とその迫力を体感し、自身の生き方やキャリアに役立ててもらうことを目的として、プロゼミ(プロフェッショナル・ゼミ)を実施しました。今回は、歌手として都内のオペラ劇場を中心に活躍する他、作曲家、台本作家、指揮者、演出家の顔を持つ舞台の総合クリエイター、阿瀬見貴光氏を講師に迎えたプロゼミをお届けします。 肉声の魅力-声楽とは 私の職業は歌手です。声楽家です。主にオペラや舞台のクラシックコンサートに出演します。それと同時に故郷の加須市で市民ミュージカルのプロデュースも行っています。まずは歌手としての仕事についてお話したいと思います。 声楽家と現代的な歌手の大きな違いは何でしょう? そうです、マイクを使うか否かです。2,000人規模の大ホールでも60人以上のオーケストラと共演する場合も、基本的に声楽家はマイクを使いません。すなわち、肉声の魅力で音楽を表現します。肉声だからといって声はただ大きければよいというわけではありません。特にオペラは「声の芸術」とも言われていて、大事なのはよく響いて遠くまで通る声です。たとえば、「ストラディバリウス」というヴァイオリンの名器をご存知の方はいますか? ストラディバリウスの音色は実に繊細で密度が高い。そして近くで聴いているとそれほど大きな音に聞こえないのに、不思議と遠くの方まで響きが飛んでいくという特性があります。声楽家はそのような魅力的な音色をお手本にして技を身につけます。楽器である身体を鍛えたり、音声学を学びます。日々の発声練習も欠かしません。世界にはたくさんの種類の楽器がありますが、人間の声こそが最も美しく表現力豊かな楽器であると私は考えています。皆さんにはアコースティックサウンド、生の響きの醍醐味を感じていただきたいですし、そのようなコンサートに是非とも足を運んで欲しいと思います。 さて、ここで実演の意味も込めて歌ってみたいと思います。オペラ発祥の国イタリアから「オー ソレ ミーオ」というナポリの民謡です。高校1年の教科書に載っていますからご存知の方も多いかもしれませんね。私はイタリアに勉強に行ったことがあるのですが、イタリア南部の方の気質はとにかく陽気でおおらかです。この曲もまたそのような気質が現れていて、活きていることが素晴らしいと感じさせてくれます。 『オー ソレ ミーオ』 新国立劇場オペラの13年間 私は渋谷区初台にあるオペラ専用劇場を有する新国立劇場に所属し、約13年間インターナショナルな活動をしてまいりました。この劇場は、オペラのほか、舞踊と劇場の部門がありまして、どれも大変クオリティの高い公演が行われています。とくにオペラ部門は『ニューヨーク・タイムズ』のオペラ番付でも上位にランキングする実力があり、世界中のトップレベルの演奏家や演出家を招へいしています。 私はこの劇場の13年間オペラ公演で、延べ156演目、780のステージに立ちました。世界トップレベルの芸術家と一緒に舞台を創ること、それが私にとって何より刺激の源になりました。彼らとの日々のリハーサルや公演を通して、彼らの美の根底にある感性、思考、宗教観に触れることができたからです。近年ではウェブ上に舞台の情報が溢れる時代になりましたが、現場でしか味わえない貴重な経験をさせていただきました。日本にいながらにして、まるで海外留学をしているかのような気分です。 さて、オペラと言えばイタリア、ドイツ、フランス、イギリスなどヨーロッパを中心とした国々の芸術家との交流が多いのですが、「オペラ界のアジア」という視点で世界を見たとき、生涯忘れられないエピソードが2つありますのでご紹介したいと思います。 日中共同プロジェクト「アイーダ」と韓国人テノール ひとつ目は2012年の日中共同制作公演『アイーダ』です。日中国交正常化40周年の節目に日中の友好の象徴として共同制作されました。この前代未聞のプロダクションは、歌手およそ100名を新国立劇場と中国国家大劇院から集め、東京と北京で公演するというものです。国家大劇院は北京の中心部にありまして、国の威厳をかけて創設された大変立派な建築物です。近くには人民大会堂(日本の国会議事堂に相当する)があります。当時、中国の反日教育はよく知られていたので、劇場内でも日本人スタッフへのあたりが厳しいのではと心配したものでしたが、まったくの杞憂でした。むしろ国家大劇院の皆さんはとても友好的で、日本の音楽事情に興味津々といった様子でした。休日には関係者が北京市内を案内してくれもしました。リハーサルの後に、若いテノール歌手に食事に誘われ「遠くから来た要人には徹底的にもてなすのが中国人の流儀だ」と言って、約一カ月分のお給料に相当する額のご馳走を用意してくれたこともありました。そして肝心のオペラ公演も大成功を収めました。隣国同士の東洋人が心をひとつにして、西洋文化の象徴であるオペラに挑戦する。満席6,000人の巨大オペラ劇場が大いに湧きました。国家間の歴史認識の違いはあれど、芸術の世界に酔いしれるとき、国境が存在しないのだと感じました。しかし大変残念なことに、東京公演の一週間後、日中両国の外交関係が急速に悪化していきました。もし、このプロジェクトがあとひと月も遅ければ公演中止となっていたでしょう。 ふたつ目のエピソードは韓国です。皆さんは韓国アイドルの「推し」はありますか? 現在ではK-pop が大人気ですし、化粧品、美容グッズ、ファッションなど韓国のトレンドには力があります。若い皆さんは驚くかもしれませんが、2013年頃の日本では韓国に対する嫌悪感、いわゆる「嫌韓」の風潮が非常に高まっていました。その年の流行語のひとつは「ヘイト・スピーチ」でした。新宿区大久保などではデモがあり、激しいバッシングも見られました。そんな社会状況の中、新国立劇場ではオペラ『リゴレット』が公演されました。主役は韓国人の若手テノール歌手、ウーキュン・キム。それまで新国立劇場で韓国人が主役を張ることはほとんどなかったこともあり、過激な世論の中で彼がどんな評価をされるのか、私は興味深く見守っていました。彼の歌声は実に素晴らしいもので、客席は大きな拍手で彼を称えました。「日本の聴衆よ、よく公平な目で評価した!」隔たりを越えた美の世界を感じ、私はステージ上で静かに胸を熱くしました。 インターナショナルな活動の中で私がいつも思うことは、舞台製作の環境は常に政治の影響を受けていますが、政治に侵されない自由な領域を持つのもまた芸術の世界であるということです。だからこそ我々芸術家は、人間の普遍的な価値観や幅広い視点をもって世界の平和に貢献すべきだと考えています。 テクノロジーと古典芸能の融合-オペラ劇場の構造 今日は建設学科の講義ですので、オペラ劇場の構造について少し触れてみたいと思います。まず特徴的なのはステージと客席に挟まれた大きな窪みです。これは「オーケストラ・ピット」と言います。 ここにオーケストラ団員最大100名と指揮者が入り演奏します。ピットの床は上下に動きます。床が下がってピットが深くなるとオーケストラの音量が小さくなり、逆に床が上がると音量は大きくなります。これによって歌手の声量とバランスを取りながら、深さを調節するわけです。ピットの上には大きな反響板があります。オペラやクラシック音楽においては、いかに生の響きを客席に届けるかが大切ですから、音響工学の専門家が材質や形状にこだわり抜いてホール全体を設計しています。 これは劇場平面図です。客席から見える本舞台の左右と奥に同じ面積のスペースがありまして、これを四面舞台と言います。大きな床ごとスライドさせることができます。これによって、巨大な舞台セットを伴う場面転換がスムーズにできますし、場合によってはふたつの演目を日替わりで公演することも可能です。この機構をもつオペラ劇場は日本ではほんのいくつかしかありません。次は劇場断面図を見てみましょう。舞台の上には大きな空間がありまして、これは照明機材や舞台美術などを吊るためのものです。下側はというと「セリ」といって、舞台面の一部もしくは全体を昇降させることができます。そして、これらの機構の多くはコンピューターによって制御されています。最新のテクノロジーは古典芸能であるオペラ(400年の歴史)に新たな表現方法をもたらし続けているのです。 私のライフワーク-ミュージカルかぞ総監督として 「多世代交流の温かい心の居場所をつくろう」と思いついたのは約30年前のことです。私が大学3年生の夏に読んだ新聞記事がきっかけとなりました。若者の意思伝達能力の低下や家庭内暴力は、家庭問題というより社会の歪みに原因があるだろうと考えていました。「自分にできること、自分にしかできないこと」音楽や舞台表現を手段として、人間が人間に興味をもって、大いに笑い、平和を謳う。そんなコミュニティをつくろう!自分がオペラ歌手になるための勉強と並行して、文化団体の運営のイメージを実践方法を温め続けました。 2012年の夏に故郷である加須市で、市民劇団「ミュージカルかぞ」を立ち上げました。ありがたいことに、市長、教育長をはじめ、地元の実力派有志たちが私の掲げる活動理念に賛同、協力してくださいました。さらに嬉しいことに、一年目からすべての年代がバランスよく揃った『三世代ミュージカル』を実現したのです。また、ダンス講師、ピアニスト、照明家などプロの第一線で活躍する業界の仲間も加須に駆けつけてくれました。市民が主役の劇団ですから入団資格は『プロの舞台人でないこと』、以上。技と魂を兼ね備えたプロの舞台スタッフが環境を整え、地元のアマチュア俳優をステージで輝かせるのが私の手法です。団員たちが燃えるような魂で舞台に立つとき、キャラクター描写の奥に個々の圧倒的な生き様が放たれます。そこには見る者の魂を震えさせるほどの「人間の美しさ」があるのです。 しかし、そこにたどり着くまでには膨大な時間と労力、技術を要します。ほとんどの団員は演技や歌唱の経験がないからです。舞台での身体表現、呼吸法、発声法、楽曲分析、台本の読解法、そして舞台創りの精神など、私が日々舞台で実践していることを43名の団員たちに解りやすく愉快に伝えています。 ミュージカルかぞは年に2演目を10年間公演し続け(コロナ禍の中止はありましたが)、着実にレベルアップしています。いつも満員御礼の客席からは割れんばかりの拍手と「ブラボー!」が飛び交います。涙を流しながら客席を立つお客様の姿が増えました。県外からのファンや、教育や文化に携わる方も多くいらっしゃるようになりました。 『大人が笑えば子供も笑う』…劇団の稽古場は笑い声が絶えません。しかし、団員個々の心の事情には静かに話を聞いて、一緒に考えます。不登校、引きこもり、健康上の悩みなど事情は様々ですが、そこから社会の歪みが見えることは少なくないです。しかし、舞台表現を磨き続け、少しずつ自分の声と言葉で素直な自分を語れるようになった団員を見たとき、私も生きていて良かったと感じます。特に子どもや若者には、人と繋がって喜びを感じる『真実の時間』を過ごしてほしいと考えています。それは誰かを愛するための心の糧になると思うからです。 時空を超えるメッセージ-ミュージカル『いち』 さて皆さん、「愛」って何でしょうね? こういった漠然とした質問が一番困るんですよね。そのような抽象的なイメージを閃きに導かれながら具象化できるのが芸術文化のいいところです。愛をいかに表現するか、私も日々悩み続けています。 私の劇作家としての代表作にミュージカル『いち』があります。作品のもととなった加須古来からの伝承『いちっ子地蔵』を読んだ瞬間、作品のインスピレーションが稲妻のように降りてきました。眠るのを忘れるくらい無我夢中で台本と楽曲を書き留めました。全2幕8景、26曲、公演2時間と、なかなかのボリュームです。ドラマの舞台は天明6年(1786年)の加須です。水害などの度重なる困難に屈することなく、助け合って前を向いて生きるお百姓さんたちの姿を描いています。現代のような科学技術はなく、物質も情報も豊かではない村落共同体の人々は何に価値を感じて生きていたのか? 現代人が忘れかけた大切な「何か」を思い起こさせてくれるのです。そして、いつも忘れはならないのは「土地に生きた先人たちの努力、犠牲、愛があったからこそ、現在の我々がある」をいうことです。脈々とつながる命、先人からの愛に感謝することが、光ある未来を導くと『いち』は教えてくれます。 「大きな社会は変えられない、まずは小さな社会から」-。土壌づくりに20年。故郷で愛の種を蒔き始めて約10年。それらが今、芽吹きはじめました。埼玉の小さな街から田畑を越えて、時空を超えて、これから新たな愛の連鎖が広がっていくのだと思います。 『野菊』 『翼をください』 『帰れソレントへ』 Profile 阿瀬見 貴光(あせみ・たかみつ)昭和音楽大学声楽科卒業。日本オペラ振興会オペラ歌手育成部18期修了。声楽を峰茂樹、L.Bertagnollio の各氏に師事。歌手としては都内のオペラ劇場を中心に活躍し、定期的なトークコンサート《あせみんシリーズ》では客席を笑いと涙の渦に巻く。その他、作曲家、台本作家、指揮者、演出家の顔を持つ部隊の総合クリエイター。完全オリジナル作品の代表作にミュージカル《いち》があり、これまでに5回の再演を重ねている。プロの舞台で培った技術や経験を地域社会に還元すべく、子どもの教育や生涯学習を目的としたアマチュア舞台芸術の発展に力を注ぐ。教育委員会等で講演を精力的に行い、芸術文化による地方創生の実践を伝えている。NPO法人ミュージカルかぞ総監督。ハーモニーかぞ常任指揮者。加須市観光大使。地元の酒をこよなく愛する四児の父。 関連リンク ・【Fゼミ】私の仕事 #1--デジタルマーケティングとオンライン販売 基礎・実践・【Fゼミ】私の仕事 #2--私が在籍してきた企業におけるマーケティング・【Fゼミ】私の仕事 #3--自分を活かす 人を活かす 原稿井坂 康志(いさか・やすし)教養教育センター教授
-

【Fゼミ】私の仕事 #3--自分を活かす 人を活かす
1年次のFゼミは、新入生が大学生活を円滑に進められるように、基本的な心構えや、ものづくりを担う人材としての基礎的素養を修得する授業です。このFゼミにおいて各界で活躍するプロフェッショナルを招へいし、「現場に宿る教養」とその迫力を体感し、自身の生き方やキャリアに役立ててもらうことを目的として、プロゼミ(プロフェッショナル・ゼミ)を実施しました。今回は、OL時代、自身の体調不良が玄米で改善した経緯から大阪で玄米カフェ実身美(サンミ)を創業し、顧客の健康改善事例に多く立ち合ってきた大塚三紀子氏を講師に迎えたプロゼミの内容をお届けします。 学生時代から就職まで 私は現在、㈱実身美を経営しています。本日は「自分を活かす 人を活かす」というテーマで私の経験をお話ししたいと思います。 最初に私の学生時代から始めたいと思います。私は法学部の出身なのですが、大学時代は正直なところやりたいことがありませんでした。何をしようかわからなかったというのが実感でした。法学部に在籍したことから、税理士事務所に就職はしてみたものの、やりがいは感じられませんでした。そのようなこともあり、しばらくして体調を崩してしまったのですね。 そんなとき、玄米食に切り替えたところ、めきめきと回復したのです。この経験は私にとって鮮烈なものがありました。そのとき思いました。体調不良の悩みを持つ人はきっと日本全国にいるはず。ならば、同じような方法で体調が回復することで喜びを共有することはできるだろうと。私自身が苦労したことをもとに、世の中の問題を解決できるのではないかと考えたわけです。そこで、事業を始めることにしました。これが私が経営者になったきっかけでした。 起業の経緯 実身美(サンミ)は、名前がコンセプトになっています。「実」があって「身」体に良くて「美」しい。すべて「み」と読みますから、3つで「サンミ」と呼ぶわけです。実身美は2002年に大阪市阿倍野区にて創業しています。現在は、玄米を主食とした健康食を提供しており、年間40万人以上のお客様にお届けしています。大阪阿倍野区、都島区、中央区、東京都、那覇市に5店舗を展開しています。 通信販売にも力を入れておりまして、独自開発の酵素ドレッシングは、全国お取り寄せグランプリ3年連続日本一(2017年全国4,400商品中1位、2018年全国4,730商品中1位、2019年全国5,131商品中1位)の評価をいただいております。現在でこそこのような高評価をいただいているものの、起業の時からすべてがうまくいったかというとまったくそうではありません。これから少しそのお話をしたいと思います。もともと食には興味があったのですが、起業となると何もわかりません。私はその分野にはまったくの素人でしたので、創業支援制度を利用して相談してみると、まずは「事業計画書を作成するように」と言われたのですね。ここで私は、コンセプトと数字の大切さを徹底的に学ぶことになりました。起業にあたって思いや志は何にもまして大切なものです。しかし一方で、現実に事業を成り立たせていくためいには、実にたくさんの具体的な行動が必要になってきます。 そこで大切なのは、仕組みづくりであり、数字をきちんと計算することです。たとえば、私は起業にあたって、公的金融機関からしかるべき融資をいただいたわけですが、それは言い換えれば借金をしたということです。借金をしたら、期限までに返さなければならないのは当然です。そこで、経営というものの責任を実感させられました。一度責任を引き受けた以上、何としてでもやらなければならないと決意しました。 そうなると、必要な費用を賄うのに、いくら必要か。これは痛いくらいの現実で、従業員やアルバイトさんの時給など掛け算すれば経費が出てきます。何で稼いで経費を払っていくか。これを計算しました。一日に必要な収入を割り出すと、ご来店54人という数字が出ました。これより少なかったら、店を成り立たせていくことはできないし、従業員にお給料も払えないわけです。 今にして思うのですが、「1日54人」の数字が出たから、私は成功できたのだと考えています。もちろん、お金だけではありません。店舗を展開していく中で、どうしても自分だけでは限界があります。人に働いてもらわなければなりません。自分がわかっているだけでは回らないのです。そのときはたと気づきました。どう人に動いてもらうかがわからなかったのです。そんなときに出合ったのが、「マネジメントの父」と言われているピーター・ドラッカーでした。 ドラッカー『仕事の哲学』との出合い 行き詰っていた時に出合ったのが、『仕事の哲学』というドラッカーの名言集です。2003年夏のことでした。まず感銘を受けたのが、「帯」の言葉です。 「不得手なことに時間を使ってはならない。自らの強みに集中すべきである」。 これは本当に救いになりました。その人にできることを生かさなければならない。生かせないならそれはマネジメントの責任ということです。この時期にビジネス界にも影響力を持つ人と出会えたのは幸福だったと思います。翌年2004年からはソーシャルネットワークで「ドラッカーに学ぶ」コミュニティも運営しはじめました。2007年には、翻訳者の上田惇生先生(ものつくり大学名誉教授)に勧めていただき、ドラッカー学会に入会して現在に至っています。 念のため、ここでドラッカーについて説明しておきます。1909年にウィーン生まれ。2005年にアメリカで没しています。「ビジネス界に最も影響力をもつ思想家」として知られる方で、東西冷戦の終結、転換期の到来、社会の高齢化をいちはやく知らせるとともに、「分権化」「目標管理」「経営戦略」「民営化」「顧客第一」「情報化」「知識労働者」「ABC会計」「ベンチマーキング」「コア・コンピタンス」など、マネジメントの理論と手法の多くを考案し、「マネジメントの父」と呼ばれています。今当たり前に通用している経営戦略とか目標管理などはドラッカーが発案したものです。 強みを生かすには 私がドラッカーから学んだ最大のものは、「強み」の考え方です。たとえば、ドラッカーは強みについて次のように述べています。 「何事かを成し遂げられることは強みによってである。弱みによって何かを行うことはできない」(『明日を支配するもの』) できないところに目を向けていてもしかたがありません。強みを集めて成果を上げるところまでもっていくことが大切だというのです。たとえば、経理の人はきちんと計算できれば、人付き合いできなくても成果をあげる上では問題ありません。むしろできることを卓越したレベルにまでもっていける。「強みを生かし、弱みを無意味にする」というのは、言うのは簡単なのですが、自己流だとうまくいきません。だんだんいらいらしてきます。人はなかなか見えないものだからです。 ではどう実践したか。実身美では、次の質問を投げかけています。「2人以上にほめられたことは何か」「2人以上に改善を求められたことは何か」一つ目については、「とても丁寧ですね。早いですね」といったささやかなことでよいのです。自分は大したことないと思っていても、強みは人が意外に知っているものです。スタッフ勉強会を開催して、隣の人のいいところを書いています。これを行うと、自分の気づいていないところがどんどん蓄積されて、新しい強みにも気づけたりする。「強みノート」を作成して、お互いの強みを理解し合えるように工夫しています。改善を求められたことについても同様に共有していきます。 強みに応じた人事としては、次のようなものがあります。社交性→百貨店担当学習欲→共同研究、HACCP取得、新規事業の把握責任感→マネジメント達成欲→成果が目に見える業務公平性→ルール作りのご意見番慎重さ→会社の危機を聞く、用意周到な準備が必要な案件コミュニケーション、共感性→お客様対応、広報指令性→プロジェクトリーダーポジティブ→ハードな現場収集心→リサーチ系の仕事(レシピ、店舗情報)着想→アイデアがないか聞く戦略性→成果へのプロセスを聞く さらに、気質や価値観も大切です。人には生まれ持っているものがあり、理由はわからないのにできてしまうことがあります。逆に、どんなに努力してもうまくできないこともあります。ドラッカーは次のように述べています。 「われわれは気質と個性を軽んじがちである。だがそれらのものは訓練によって容易に変えられるものではないだけに、重視し、明確に理解することが重要である」 人には教わっていないのにできてしまうことがあるのです。そういうものを生かしていきたいと考えています。なるべく人の持つ本質を大きく変えないようにすることで、生かしていきたいと考えています。 20年間存続するには--会社の文化づくり 最後になりますが、文化づくりについてお話したいと思います。私は文化の力はとても大きいと常々感じています。文化になれば言葉はいらなくなります。たとえば、日本では公共交通機関などでみんな並んで待つ文化がありますね。これは海外からすれば驚かれることです。それが文化の力であり、誰もが当たり前のようにやっていることです。 今日ものつくり大学に来て、みんなが気持ちよく挨拶してくれるのに感動いたしました。授業にもかなり前から教室に来ている。それはものつくり大学では普通のことかもしれませんが、立派な文化と言ってよいものです。文化になると人から言われなくてもできてしまう。これは、その文化の中にいる人を見れば伝わってくるものですし、本物の力だと思います。 なぜ実身美は20年継続できたのかを時々考えます。起業した企業が20年後に生き残っているのは0.3%と言われています。昔からあてにならないことを千三つと言いますが、まさに1000分の3の確率なのです。続けるのは難しいものです。ポイントは、学ぶこと、強みを生かすこと、そして「新しくしていくこと」です。続かないとは変われなかったということだからです。これは会社の文化といってよいと思います。 実身美では、継続学習とたゆまぬ改善活動を行っています。「丘の上の木を見ながら、手元の臼を引く」、すなわち、長期と短期をバランスさせる視点を大切にしています。ビジョンと現実の両方を見ながら、行くべき方向へかじ取りするのです。 最後に--マーケティングとイノベーション ドラッカーが言うのは、マーケティングとイノベーションです。ドラッカーは、「マーケティングとは販売を不要にすること」という有名な言葉を残しています。「買ってください」と言わなくても、お客様から「ほしい」と思っていただけることです。私は、自分が不便だと感じて、こんなのがあったらいいと思うことを大切にすることでした。自分も一人の顧客だからです。知人の本の編集者が教えてくれたのですが、「誰かにぴったり合うということは、その後ろに同じ感じ方をする人が30万人いる」という。それが独りよがりではなく、役に立ち、喜ばれるものになるのです。 イノベーションは新しくしていくことです。お店だったらいろんなメニューがありますね。消費者として、ほっとできるお店へのニーズがあるのに、それをベースにしているお店が少なかった。実身美の創業にはこのような思いもありました。そこで大切なのが顧客目線によるイノベーションです。お店の側は、自分が学んだイタリアンとか中華とかで勝負しようとしてしまいがちですね。果たしてそこに顧客目線はあるのかが疑問でした。自分の発想だけで出すと顧客からずれてしまいます。 自分が消費者だったらどうか。たとえば実身美では、冬に白湯を出すようにしています。というのも、通常の飲食店では、冬でも氷の入った水が出てくるところがあるからです。家ではありえないことですね。プロがそのようなことをしている。寒い時は常温の方がありがたいはずで、それだけでも感動してくれる人がいます。以前ジャーマンオムレツをメニューにしたいという意見があって、私はそこにトマトとかいろいろな野菜を入れたら魅力的ではと提案したことがあります。即座に「それではジャーマンオムレツにならない」という反論がありました。けれども、それは偶然私たちの知るジャーマンオムレツが、昔の人の保存がきくもの、じゃがいもとかしか使えなかった時代の遺物だったに過ぎない。それはものが不足していた時代に誰かが考えた苦肉の策なのに、今まったく違う現在でも踏襲してしまうのです。今はなすもトマトも入れられる。自分だったらこうするという具合に作り直していいのです。酵素ドレッシングもそうです。以前は、茶色で調味料というのが大半でした。生の良さを生かす「食べるドレッシング」という発想がなかった。それを顧客目線で開発した。 本日は「自分を活かす 人を活かす」というテーマで私の経験をお話しました。ものつくり大学の学生の皆さんに少しでも役に立てれば嬉しいです。ありがとうございました。 Profile 大塚 三紀子(おおつか・みきこ)㈱実身美 代表取締役関西大学法学部卒。OL時代、自身の体調不良が玄米で改善した経緯から2002年大阪で玄米カフェ実身美(サンミ)創業。20年間で玄米食を約500万食提供し、顧客の健康改善事例に多く立ち合う。玄米の機能性に感銘を受け、2017年度より、琉球大学医学部第二内科益崎教授研究室と玄米の機能性食品の共同研究開発を開始。働く女性を対象にした臨床試験を通じ、玄米の機能性成分がアルコール依存を軽減させる効果を認める。2019年~2023年 沖縄科学技術イノベーションシステム構築事業委託共同研究採択2022年 『特許庁 社会課題解決×知財 IOPEN プロジェクト~脳のデトックス効果のある玄米食を通じて社会ストレスを解消させる挑戦~令和3年度IOPENER』。ドラッカー学会会員。著書に『実身美のごはん』『実身美の養生ごはん』ワニブックス社がある。(累計2万9000部)『実があって身体に良く美味しい』をコンセプトにした商品開発を得意とする。酵素ドレッシングはベストお取り寄せ大賞3年連続総合大賞受賞(2019年度5,131商品中1位)他受賞多数。 関連リンク 【Fゼミ】私の仕事 #1--デジタルマーケティングとオンライン販売 基礎・実践 【Fゼミ】私の仕事 #2--私が在籍してきた企業におけるマーケティング 【Fゼミ】私の仕事 #4--歌手としての歩みとライフワーク 原稿井坂 康志(いさか・やすし)ものつくり大学教養教育センター教授
-

【Fゼミ】私の仕事 #2--私が在籍してきた企業におけるマーケティング
1年次のFゼミは、新入生が大学生活を円滑に進められるように、基本的心構えや、ものづくりを担う人材としての基礎的素養を修得する授業です。このFゼミにおいて各界で活躍するプロフェッショナルを招へいし、「現場に宿る教養」とその迫力を体感し、自身の生き方やキャリアに役立ててもらうことを目的として、プロゼミ(プロフェッショナル・ゼミ)を実施しました。今回は、外資系企業を中心に7社の在籍経験があり、約23年にわたってマーケティングに従事している平賀敦巳氏を講師に迎えたプロゼミの内容をお届けします。 マーケティングとは何か 本日の話の流れとして、まず初めに、「マーケティング」とは何を意味する言葉なのかを説明して、全体像をつかみ、その上で「マーケティング」に含まれる具体的な仕事の種類を説明します。そして、より個別具体的に、私が在籍してきた企業でどんな仕事に実際に取り組んで来たのか、事例を紹介しながら説明します。 現在、担当している商品、当日学生に配布された まず、大家と言われる3名の方が、「マーケティング」をどのように定義しているか?ハーバード大学教授のレビットは、マーケティングとは「顧客の創造」だと言いました。「マーケティングの父」の異名をとるコトラーは、「個人や集団が、製品および価値の創造と交換を通じて、そのニーズやウォンツを満たす社会的・管理的プロセス」という、大変緻密な定義を行っています。そして、有名な経営学者であるドラッカーは、マーケティングとは「セリング(販売)を不要にすること」だと語りました。では、私は、マーケティングをどのように定義しているか。二つの○と、それを結び付ける両向きの矢印を使って、図で説明をすると分かりやすいのです。片方の○は、生活していく中で様々な課題なり欲求を抱える消費者、生活者。もう片方の○は、そういった課題を解決し、欲求を満たすリソースを持つ事業者。これら二つの○を結び付けてあげると、そこに取引が生まれ、市場が生まれます。この、市場をつくるために両者を結び付けてあげることがマーケティングなのですね。 MarketingというのはMarketにingが付いていることから分かる通り、「Marketすること」という意味。要は、「市場を作ること」がマーケティング、市場をつくり、より大きくするために、色々な働きかけることが全てマーケティング活動と言えます。こう定義すると、マーケティングというのはとても広い概念で、ほぼ「経営」と同じ意味合いになります。とはいえ、経営活動の中には、人事、経理・財務、IT等々、確かにマーケティングとは言いにくいものも含まれるので、私は以下のように整理しています。経営=直接お客様に働きかけて市場を作る広義のマーケティング+間接業務広義のマーケティング=狭義のマーケティング+セリングコトラーは、このマーケティングの全体像を、「R-STP-MM-I-Cモデル」という枠組みで整理しました。R=Research(リサーチ・調査や情報収集)STP=Segmentation(セグメンテーション・市場を分類すること)、Targeting(ターゲティング・お客様を絞ること)、Positioning(ポジショニング・お客様の頭の中での居場所、位置付けを決めること)、これらの頭文字で、マーケティングの戦略部分。MM=Marketing Mixの略でいわゆる「4P」と言われるものと同じ意味。4Pとは、Product(商品)、Price(価格)、Place(販路)、Promotion(販促)の4つのPから始まる要素を指し、マーケティングの戦術部分。I=Implementation(実行)の頭文字。頭の中で考えた戦略や戦術は、実際に実行に移されないことには現実が変化しないので、実行はとても大切です。C=Control(改善)の頭文字。俗にいう「PDCA」。実行したら必ず結果を評価して、上手くいった点は維持し、上手くいかなかったことは改善する。そのプロセスを繰り返すことが重要です。 「お客様」を知ること ビジネスをする場合、通常何らかの目的を持って始めます。その目的を達成するために、様々な商品を取り扱い、その商品を市場で売れるようにするために、先程の「R-STP-MM-I-Cモデル」に沿って、戦略を考え、戦術を練り、それらを実行に移していきます。マーケティング戦略を考える上では、まず何よりも先に、市場の一方当事者である「お客様」を知ることが重要です。お客様は、何かしらモノを買うまでに、様々な段階を経て意思決定しますが、この時の心の流れを「パーチェスファネル」などと呼びます。ファネルとは、漏斗(じょうご/ろうと)で、必ず上が広く、下に行くに従って細くなります。基本的に、認知、興味、行動、比較、購入という段階を踏んで、ようやくモノを買ってくれることになるわけで、段階を進むごとに離脱する人も出て来るため、必ず下へ行くほど細い。このパーチェスファネルを、出来るだけ横に広げていくことで、市場がつくられ、大きくなる。また、下の方をより太らせて逆三角形から台形に近付けていくことで、更に市場が大きくなる。なので、各段階の間口を広げること、そして次の段階へと進む確率を上げること、それを実現することがマーケティングの仕事のイメージとなります。お客様が持っている顕在ニーズと潜在ニーズ(ホンネ)を、質的調査(ヒアリングや観察)や量的調査(アンケート、データ分析)を通じて調べ上げたら、そのニーズを満たすことを考えなければなりません。そのために、「コンセプト」を練り上げます。コンセプトの要素は、よくABCで整理されます。A:Audience・お客様B:Benefit・便益、嬉しさC:Compelling Reason Why・お客様がその嬉しさを得られると信じるに足る理由お客様に選ばれる商品をつくるには、Aの誰を相手にするのか、Bの相手が喜んでくれそうな何を提供するのか、そしてCのそれがいかに良い商品だと分かるような根拠をどうやって伝えるか、これらABCをワンセットで提供しなくてはなりません。3つ目の、お客様に提供する「根拠」については、3つの「差別化軸」(①手軽軸、②品質軸、③密着軸)を活用します。 私が在籍してきた企業の具体例 ①女性用カミソリのポジショニング圧倒的なシェアを持っていた競合の商品が、ハッキリとしたポジショニングを持っていない点に気付き、消費者のニーズに基づいた明確なポジショニングで「挟み込み」を行った結果、多くの売場を獲得し、シェアの逆転につなげることができました。②商品をラッピングしてギフト化し、価値を高めて価格を上げる一つだと安価なキャンディを、沢山集めてお花のブーケのようなラッピング仕立てにすることで、単価を上げて発売しています。キャンディだけで比較すると割高ですが、ギフトとしての価値を創り出すことで多くの方に買い求めていただいています。 ③商品カテゴリによるコスト構造の違いと値付け化粧品や日用雑貨で様々な商品を扱ってきた中で、売価と原価の関係はカテゴリによってバラバラであることを見て来ました。より多くの粗利を稼げるカテゴリでは、その粗利を原資にして、広告や販促を展開し、逆に粗利が低いカテゴリでは、ギリギリ安値でとにかく数をさばくというやり方になっています。④小売店のバイヤーとの「棚割」商談における資料作成小売店では半年に一度、「棚割」といって棚に並べる商品の入れ替えを実施しています。消費者に商品を買ってもらう機会を確保するために、棚割で自分のところの商品がなぜ必要なのか、ロジックを組み立て、説得を試みます。⑤TVCM制作広告代理店に依頼をして、誰にどんなメッセージを伝えたいのかを説明し、目的に応じたクリエイティブを制作してきました。⑥店頭販促消費者は、「期間限定」だったり「お買い得」といったメッセージ、見た目に反応することが多いので、店頭でより多くの人に、より頻度高く買っていただくための工夫を様々に行ってきました。⑦DMを用いた店頭への集客化粧品会社で、愛用顧客の方に再び店頭へと足を運んでもらうために、凝りに凝ったDMを送付していました。頻繁に新商品を出し、常に店頭を新鮮に保って、DMによる集客でにぎわいを創り出していました。 Profile 平賀 敦巳(ひらが・あつみ) 1972年東京都出身、横浜市在住1996年慶應義塾大学大学院法学研究科修了(法学修士)外資系企業を中心に7社の在籍経験。27年強のキャリアのうち、約23年マーケティングに一貫して従事。これまでに取り扱ってきた商品は、主に日用雑貨と化粧品を中心に、洗剤や家庭紙(トイレットペーパーやティッシュペーパーなど)、スキンケアやヘアケアやボディケア、カミソリ、香水、キャンドル、保険などが挙げられる。マーケティング戦略の立案から、商品・コンセプトの調査や開発、値決め、チャネル開拓、広告宣伝・PR、販売促進に至るまで、幅広い経験を積んで来た。現在は、ベルフェッティ・ヴァン・メレ・ジャパン・サービス株式会社に勤務、カテゴリーマネージャーとしてメントスとチュッパチャップスの二つのブランドを管掌。 関連リンク 【Fゼミ】私の仕事 #1--デジタルマーケティングとオンライン販売 基礎・実践 【Fゼミ】私の仕事 #3--自分を活かす 人を活かす 【Fゼミ】私の仕事 #4--歌手としての歩みとライフワーク 原稿井坂 康志(いさか・やすし)ものつくり大学教養教育センター教授
-

【Fゼミ】私の仕事 #1--デジタルマーケティングとオンライン販売 基礎・実践
1年次の「Fゼミ」は、新入生が大学生活を円滑に進められるように、基本的心構えや、ものづくりを担う人材としての基礎的素養を修得する授業です。このFゼミにおいて各界で活躍するプロフェッショナルを招聘し、「現場に宿る教養」とその迫力を体感し、自身の生き方やキャリアに役立ててもらうことを目的として、プロゼミ(プロフェッショナル・ゼミ)を実施しました。大企業勤務、起業、コンサルティングなど多様な活動をし、現在は日本工芸株式会社 代表取締役を務める松澤斉之氏を講師に迎えたプロゼミの内容をお届けします。 とにかくいろんな仕事をしてきた この27年を振り返ると、私は大企業に勤めたこともありますし、第三者としてコンサルをしたこともあります。自分で会社を立ち上げて経営してきたこともあります。とにかくいろいろな活動に携わってきた自負はあるのですね。 現在も、自分の会社を経営していますが、SBI大学院大学のMBAコースで講師も務めていますし、企業の研修を行ったり新規事業のコンサルティングもしています。早稲田大学、広島大学などで「デジタルマーケティングとオンライン販売の実践」について講義をしたり、福岡県物産振興会、東京都中小企業振興公社、新宿区立高田馬場創業支援センターなどで「企画発想力人材」の育成・活用、EC活用などについて相談に乗ったりもしています。その他企業内では事業開発、EC加速、越境EC立上げ、など様々なテーマでレクチャー+立上げ支援を実施しています。 こういう生き方は、学生時代、すなわち皆さんと同じころのつまり二十歳あたりの頃のある思いに遡れると思っていますが、それについては最後にお話ししたいと思います。 新卒で就職した会社の倒産 私は東京理科大学の出身です。とにかく旅行が好きで、バックパックを背負って世界中を旅行して回っていました。在学中は中国の四川大学に1年間の短期留学もしました。これには元来の『三国志』好きが大いに関係していたと思います。 1996年に大学を卒業してから、ヤオハンジャパン社に入社しました。大学時代中国に留学したこともあり、アジア展開に注力する会社で働きたいと考えたからです。ヤオハンは小売業で、1990年代の前半までは飛ぶ鳥を落とす勢いの躍進を続けていました。ところが、この巨大な一部上場企業が、私が入社した翌年に倒産してしまいます。これは日本の企業史に残る巨大な倒産としても知られています。これはなかなかショックな出来事でありましたが、就職先の倒産を機に私の人生が本格的に始まったと言ってもよいかもしれません。その後、しばらくの間、東南アジアなどからの輸入水産商社にて製品開発・輸入及び国内販売に従事していました。やはりアジア諸国との仕事をしたくてヤオハンに入ったわけですから、その思いはずっと心にとどまっていたからです。日々とても忙しかったけれども、充実していました。 たいてい人は何かに一生懸命打ち込んでいれば、必要な出会いは向こうからやってきてくれるものです。私の場合、勤め先の倒産から数年してからでした。それは日本を代表するコンサルタント・大前研一氏との出会いです。このご縁から、1999年、大前氏の起業家育成学校(㈱ビジネス・ブレークスルー)の立ち上げに参画する幸運に恵まれました。私が従事したのは国内最大規模の起業家育成プログラムを提供するスクールです。これを機に、同スクールの企画運営に関する統括責任者となり事業戦略・マーケティングを立案・実行してきました。社内新規事業として、企業内アントレプレナー育成サポート事業を立ち上げ、リクルート、三井不動産、NTTドコモなどの大手クライアントを獲得することに成功し、マザーズ上場にも貢献できました。 ビジネス・ブレークスルーから約7年がたち、自分自身もいつか起業することを考えていましたので、2006年、新規事業開発支援のコンサルティング会社フロイデの設立に参画し、役員に就任しています。これは、事業規模に関わりなく、新規事業をスタートしたいという企業は実に多いものの、そのための人員もリソースも不足していて、なかなか着手できずにいる状況を機会と考えたためです。新規事業の専門家は世の中にさほど多くなかったのも理由の一つです。実際に着手してみると、相談件数も着々と伸びて、ホンダ、日経新聞、パナソニック、NEC、東京電力などかなり大手企業の事業開発事案に携わることができました。このフロイデという会社は現在も関わりを持っており、私の複数の活動の一つとして、現在も新規事業のコンサルティングを続けています。 40歳を目前にAmazonへの転職 その間世の中は大きく変化を続けており、私としても、ネットによる世の変化を直接目で見て、学び取りたいという思いがふつふつと湧き上がってきました。そんなときに、Amazonジャパンの求人があることを知り、すでに40歳を目前としていたにもかかわらず応募したら合格してしまいました。ここから、私の大企業との関わりが再度始まったことになります。就職して翌年で倒産したヤオハン以来です。 私がAmazonに入ったのは2012年6月でした。このAmazon体験は、私にとってとても大きなものをもたらしてくれたと思います。まずはインターネット通販 Amazonジャパンホーム&キッチン事業部に配属され、バイイングマネージャーとして販売戦略の立案と実行を任されました。これはかなり重要なポジションで、会社としても私のこれまでの経験やスキルを十分に生かせるように配慮してくれたのだろうと思います。 Amazonで得たことは実に多いのですが、私は三つあると考えています。一つはEC、すなわちネットビジネスの基本が理解できたことです。ECとは何のことかといえば、6つの要素、商品、物流、集客、販売、決済、顧客からなっています。これらへの対応、作戦計画を行うのがバイヤーの仕事です。AmazonのECは世界最高と言ってよく、仕入れはもちろんのこと、マーケティングやアフターサービスまで、多くを学ぶことができました。この体験は独立している現在、とても役に立っています。 第二が世界最高レベルの組織です。Amazonの構築した組織は、巨大でありながら実に柔軟であり、機能的でした。Amazonの組織の一員であることによって、特に大きな組織を動かすためのエッセンスのようなものが会得できたと思っています。 最後がビジネス・パートナーです。仕事をしていると仲間ができます。その仲間がいろいろな情報をもたらしてくれますし、私もいろいろな情報をシェアしたりします。そのような人間関係は、会社を辞めた後も続きます。「人脈」という言い方もしますが、これは仕事の醍醐味だと思います。 Amazonは今あげた三つの要素のどれをとっても一流であったのは間違いありません。その恵まれた環境の中で、とにかく日々の商談を行いました。結果として2,000社以上のEC化サポートの経験を積み上げることができました。 日本工芸㈱を設立--想いをつなぐ工芸ギフトショップ 私がAmazonに在籍したのは約4年です。いつかは独立しようと考えていましたから、退職は当初より織り込み済みでした。私が再び事業を立ち上げたのは、2016年12月のことです。Amazonを退職し、工芸品の越境EC運営を生業とする日本工芸株式会社を設立しました。「想いをつなぐ工芸ギフトショップ」をキャッチコピーにしています。仕事内容は伝統工芸領域のプロデュース・販売事業です。日本の伝統工芸のすばらしさを世界に知っていただきたいと思い、スタートしました。 詳しくはHPをご覧ください。https://japanesecrafts.com/ それ以前から、新規事業開発アドバイザーは長く従事しており、専門領域は、新規事業案策定、実行支援、事業創出の仕組みづくり、人材育成、EC戦略立案、集客支援など多様に展開させていただいています。 私は日本工芸㈱のビジョンを「日本の工芸、職人の技と精神性・製法・技法に宿るこだわりやプロセスを理解し、商品流通・教育など通して製品を愛する日本内外の人、世の中に広げていく」としました。日本ではたくさんの優れた職人がおられ、日々逸品の製作に励んでいます。しかし、伝統工芸品は1983年の5,410億円をピークに、2015年は1,020億円と5分の1にまで減少しています。売上減少に伴い、人手の不足、新商品開発への対応不足なども加わって産地の生産・流通は構造的に疲弊してきているのが現状です。これには、昨今の百均などに見られるように、消費者動向に添う効率よい商品調達・流通が大きく関係しています。所得・消費も減少していますので、「安くてそこそこの」ものに消費者がどんどん吸い寄せられているのでしょう。それに対して、専門店やECなどが十分に対応できていないのではないかということも、日本工芸㈱立ち上げの原動力になっています。 そのために、選定したブランド、産地、工芸品を不易流行なブランドとして発掘するところから始めます。職人さんとじっくり語り合い、文章と画像で語り、販売するようにしています。こうすることによって、国内でハンドメイドによる工芸品をセレクトしてお客様に提供する、目利き役も務めています。それぞれの職人は小規模ですから、広告や大規模なプロモーションを打つことはできませんし、その知識も乏しいのが実情です。日本工芸㈱が行いたいと考えるのは、職人さんに職人さんらしい仕事をしてもらうことです。そのほかの面倒なことは引き受ける。その価値を理解してくれる全国のお客さんをインターネットによって仲介・プロデュースしています。最近では法人による購入も増えてきました。 死ぬまで挑戦したい 私は現在で50歳です。今までいろいろな事業に携わってきました。大企業勤務、企業、コンサルティングなどなかなか経験できない多様な活動ができたのは本当にありがたかったと思います。 事業の形態は実にいろいろあるのですが、私は一番大事なのは「人」だと思うのですね。経営学者のドラッカーも、経営的問題は結局は人の問題に帰着すると語っていたかと思います。私にとっては、仕事そのものの大切さもさることながら、その仕事が社会的に意味を持つためには、やはり人との関係を創生するものがなくてはならないと考えています。新規事業のコンサルを始めたときも、Amazonでの開発業務も、日本工芸㈱の企業もつまるところは、人の力になりたいし、私自身もそこから力を得たいという思いがあったためだと思います。早いうちに海外に出たことで、いろいろな人に会うことができましたし、多くの体験をすることができました。社会人になってからも、ずいぶんたくさんの国を旅行やビジネスで訪れました。これは私が職場を始め居場所をどんどん変えてきたことも関係していると思うのですが、それによって変化していくことが恐くなくなってきたということは言えると思います。世の中は何もしなくても変わっていくものです。むしろ変わっていくことがこの世の本来の姿です。変化していくことを後ろ向きにではなく、積極的に活用していくような生き方を結果としてしてきたように思います。 私は社会人になって27年目になります。その意味では私は一社に就職して長く勤め上げる人生を送ってきたわけではありません。現在もなお複数の仕事を同時に行っています。おそらく現在学生の皆さんも、一社で勤め上げるのではなく、適宜ふさわしい仕事や会社で働いていく人生になると思います。 思い起こせば、学生時代、私はあることを考えるようになりました。それは人はいつか死ぬということです。それはいつかの問題であり、避けることのできないことです。そうであるならば、私は死ぬときに100名の友人がいる状態を理想と思うようになりました。死ぬときに100名。これを実現するためにこれから生きていこうと思ったのです。私の人生ビジョンは「挑戦する精神とともに成長する」です。死ぬまで挑戦して生きたいと日々考えています。挑戦するとは、いつでも生き方を変える準備があるということです。 大学生の皆さんは、現在基礎を築く大事な時期にいるのですから、ぜひ日々を大切に送っていただきたいと思います。技能や技術を担うテクノロジストの皆さんにとって本日のお話が何らかの参考になればと願っております。 Profile 松澤 斉之(まつざわ・なりゆき)1996年 東京理科大学卒業、在学中に中国四川大学に留学同年、ヤオハンジャパンに入社するも翌年倒産1999~2006年 大前研一氏のベンチャー(現㈱ビジネス・ブレークスルー)に参画、マザーズ上場2006年~現在 新規事業開発会社(㈱フロイデ)に参画2012~2016年 アマゾンジャパン ホーム&キッチン事業部シニアバイイングマネージャー2016年~現在 日本工芸㈱ 代表取締役、国内外EC事業、プロデュース事業(卸)、販路開拓支援事業を実施2017年~ SBI大学院大学講師(事業計画演習)2019年~ 独立行政法人中小企業基盤整備機構 中小企業支援アドバイザー 関連リンク 【Fゼミ】私の仕事 #2--私が在籍してきた企業におけるマーケティング 【Fゼミ】私の仕事 #3--自分を活かす 人を活かす 【Fゼミ】私の仕事 #4--歌手としての歩みとライフワーク
-

【学生による授業レポート】ジジジジッ、バチバチッ…五感で学ぶ溶接技術
今回は、学生の目線から授業を紹介します。建設学科1年の佐々木望さん(上記写真左)、小林優芽さん(上記写真右)が「構造基礎および実習Ⅳ」のアーク溶接実習についてレポートします。実習を通じて、学生たちは何を感じ、何を学んでいるのか。リアルな声をお届けします。(学年は記事執筆当時) ものつくり大学の授業について ものつくり大学の特色…それは何といっても実習授業の多さです。なんと授業のおよそ6割が実習であり、実践を通して知識と技術の両方を身に着けることができます。科目ごとに基礎実習から始まり、使用する道具の名称や使い方などを一から学ぶことができます。 本学は4学期制でそれぞれを1クォータ、2クォータと呼び、1クォータにつき全7回の授業と最終試験を一区切りとして履修していきます。今回は、そんな授業の中で建設学科1年次の4クォータで履修する「構造基礎および実習Ⅳ」のアーク溶接実習について紹介します。 アーク溶接の実習とは まず、アーク溶接について簡単に説明すると「アーク放電」という電気的現象を利用して金属同士をつなぎ合わせる溶接方法の一種です。アーク溶接の中にも被覆、ガスシールド、サブマージ、セルフシールドなど様々な種類がありますが、この実習では一般的に広く使用されている被覆アーク溶接を行いました。 アーク溶接の様子 この授業は、講義の中で溶接の基礎知識や安全管理等の法令を学び、実技を通してアーク溶接の技術を身に付けることを目的としています。また、6回目の授業で突合せ板継ぎ溶接の実技試験、7回目の授業で「アーク溶接等作業の安全」をテキストとした試験を行います。その試験に合格した学生には特別教育修了証が発行され、アーク溶接業務を行えるようになります。 実技試験の課題 突合せ溶接 実習では平板ストリンガー溶接、T型すみ肉溶接、丸棒フレア溶接、突合せ板継ぎ溶接といった、数種類の継手の面やコーナー部を溶接する練習を行いました。また、講義では鋼材に関する知識、溶接方法の原理、作業における安全管理、品質における溶接不良の原因や構造物への影響等について学び、試験に臨みました。 実習の流れとしては、まず作業の前に溶接方法の説明を受けます。その後、皮手袋やエプロン、防じんマスク、保護面等の保護具を着用して、3~4人で一班になり、各ブースに分かれて順番に練習を行います。作業中は、実際に現場で活躍されている非常勤講師の先生が学生の間を回り、精度の高い溶接ができるようアドバイスや注意をしてくれます。溶接金属やその周囲は非常に高温になるため、他の実習よりも危険なポイントが多いので作業中だけでなく、準備・片付けもケガ無く安全に行えるよう毎回KY(危険予知)活動をしてから実習に臨みました。 実習を行ってみて 説明ばかりでは授業の様子を想像するのも難しいですよね…。ということで、実際に授業を受けた建設学科1年、小林と佐々木の感想をお届けしたいと思います! ・何を学ぶことができたか 【小林】アーク溶接とは何かを学ぶことができました。もっとも、それを教わるための講義なので何を言ってるんだと思われてしまいそうですが、そもそも私は溶接と無縁の生活を送ってきたので、アーク溶接ってなに?というか溶接ってなんだよ。というところから入りました。1回目の講義の際、どのようなものが溶接で作られているのか紹介していただいたのですが、ほとんどが知らなかったことだったので、とても面白かったのを覚えています。 【佐々木】溶接というのは非常に優れた接合方法だということを学びました。溶接は継ぎ手効率が高く、大型の構造物を作るのに適しています。あの東京スカイツリーはなんと37,000ものパーツを全て溶接することで作られていると知り、世界一高い塔を作る溶接という技術がこんなに小さな機械で、こんなに簡単にできるものなのだと驚きました。また、一口に溶接といっても用途によって材料や溶接方法、継ぎ手の種類などが様々で、その違いを興味深く学ぶことができました。 ・楽しかったこと 【小林】アーク溶接を実技として教わったことがすごく楽しかったです。非常勤の先生方がとても優しく、どのようにすればいいか、どのくらい浮かすのか、どの音で進めていくのかなど一緒に動かしたり、その都度「今離れたよ。もう少し近付けて。そう、その音」と声をかけてくれたりして理解できるようにしてくださったので、すごく分かりやすかったです。そのおかげで綺麗に溶接ができるようになり、すごく褒めてくださることもあって、とても楽しく実習をすることができました。先生が「初めてでここまでできる人は初めて見た」とまで言ってくださったので、とても嬉しく、褒められればやる気が出る単純なタイプなので、やる気もすごく出ました。 【佐々木】練習を重ねて、アドバイスを実践していく度に溶接の精度が上がり、目に見える形でできるようになっていくのが楽しかったです。溶接は五感がとても大切で、保護面越しで見るアーク放電の光だけでなく、ジジジジッ、バチバチッといった音の違いや溶接棒越し感触を頼りに集中し、真っすぐに溶接できた時にはとても達成感を感じました。班の中でも上手な学生から感覚を教えてもらったり、説明を受けながら溶接の様子を見学することで、より学びを深めることができたと思います。講義では、先生から現場での実体験を交えてお話いただいたおかげで楽しく知識を身に着けることができたので、苦にすることなく試験勉強に取り組めました。 実習中の様子 ・苦労したこと 【小林】T字の材料に溶接するところがすごく苦労しました。平面とはまた違った角度をつけて溶接しなければならず、どうにもそれが難しかったです。1層目の溶接は擦りつけながら溶接すると言われ、この前までは浮かせるって言ってたのに?と混乱している中、追い打ちで「この前とは違う角度で溶接する」と言われてしまい、思考が停止したのをよく覚えています。さらに、そのことに気を取られ、前回できていた適切な距離を維持することができなくなり、手が震えて作業している場所が分からず、ズレてガタガタになることを経験して、やっぱり一筋縄ではいかないんだと痛感しました。 T型すみ肉溶接 【佐々木】被覆アーク溶接というのは、細長い溶接棒と溶接金属の母材を溶かし合わせてつなぎ合わせる方法で、溶接を進めるほど溶接棒が溶けていくので、母材と溶接棒の距離を保つのが難しく、溶接の後が上下にずれてしまい大変でした。アークの光が明るすぎて目視では距離の確認ができずに困っていたら、「正しい距離を保てば見えるようになる」と教えてもらい、それからは以前より真っすぐに溶接できるようになりました。また、溶接不良を何か所も発生させてしまい、溶接不良が原因で鉄橋が崩落した大事故についても学んでいたため、仕事としての難しさや、構造物を作っている技術の高さを改めて感じました。 最後に 私たちの授業紹介はいかがでしたでしょうか?建設学科では、今回紹介した構造基礎の授業だけでなく、設計製図や木造、仕上げといった幅広い分野について実習を通して学び、知識と技術を身に着けることができます。 この記事を通して「ものつくり大学って面白そう!」「他にどんな授業をしているのかな」と少しでも興味を持っていただけたらとても嬉しいです。 最後までお読みいただきありがとうございました。 原稿建設学科1年 佐々木 望(ささき のぞみ) 小林 優芽(こばやし ゆめ) 関連リンク ・【学生による授業レポート #2】受講後もSA(スチューデント・アシスタント)を通じて深める学び・建設学科WEBページ