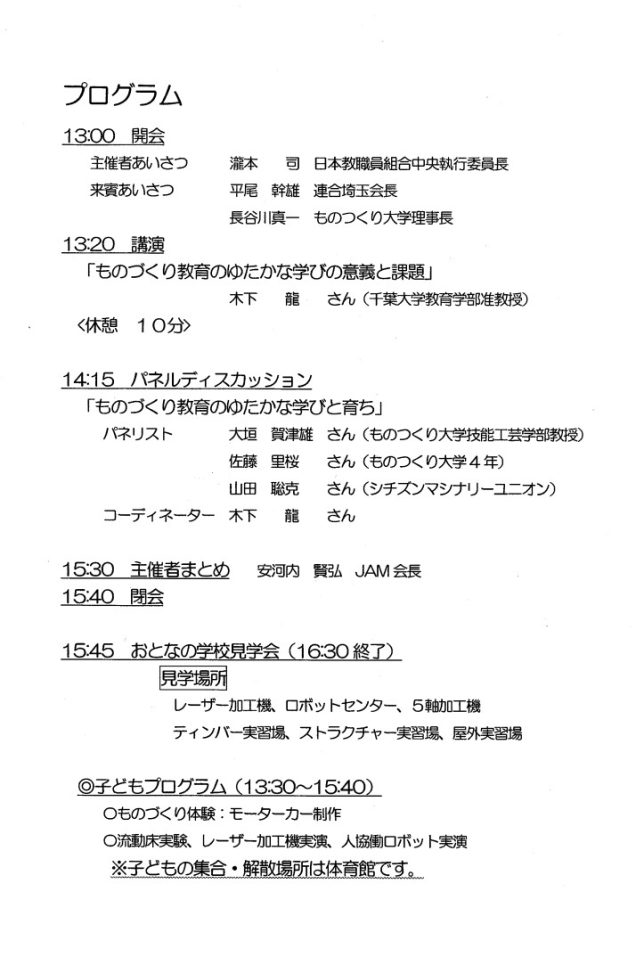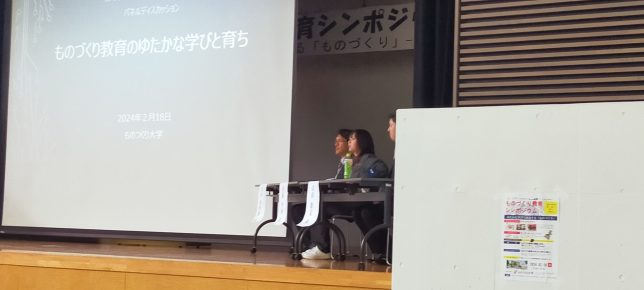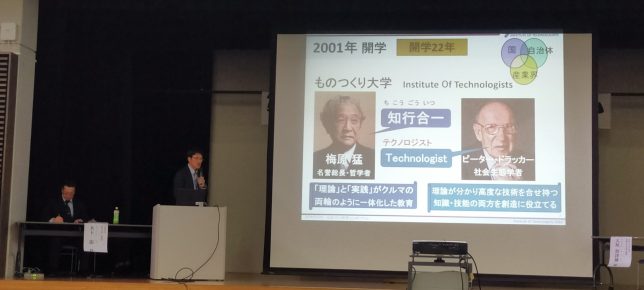1/24,研究室の卒業研究発表会が終わりました.今年発表会はコロナ前の状態に戻りまして,遠隔無しで会場による聴講となりました.研究室4年9名は素晴らしい発表をしてくれました.ただし,質問に対する回答が不十分な者もいましたが,私が学生の時にそのような状態になったのを覚えています.
研究室の関連発表は以下の通りです.同様の内容で土木学会年次講演会でも発表して頂きたく思っています.就職後9月に仙台に集まりましょう.今後の皆さんの活躍に期待しています.
風見優羽 H形断面長柱のCFRPシートによる補強に関する交番載荷実験
廣田雅人 H 形断面長柱のCFRP成形材による補強に関する交番載荷実験
松田和磨 矩形断面長柱のCFRP シートによる補強に関する圧縮載荷実験
平田桐也 鋼桁上フランジのCFRP成形材によるバイパス補強効果に関する実験研究
平岩アキ 横倒れ座屈した鋼桁のCFRPによる補強効果に関する実験研究
イスラムモフィズル 場所打ち床版を有する弾性合成桁の中間支点部挙動に関する実験研究
佐藤里桜 プレキャスト床版を有する弾性合成桁の中間支点部挙動に関する実験研究
宇津味泰成 CFRP成形材と軽量樹脂モルタルによる鋼床版下面補強施工と補強効果確認実験
小林駿 CFRP成形材と軽量樹脂モルタルにより下面補強した鋼床版の移動輪荷重走行実験

発表当日の集合写真

発表の様子1

発表の様子2

発表の様子3

発表の様子4

発表終了後の懇親会