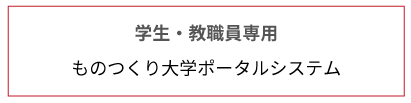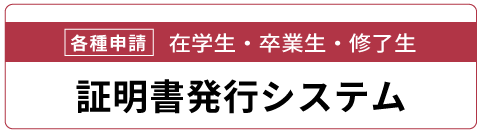建設学科 教員一覧

| 大垣 賀津雄 教授・学部長・研究科長・博士(工学) |  研究室ホームページへ 研究室ホームページへ |
||
|---|---|---|---|
| 主要経歴 | 大阪市立大学大学院前期博士課程修了、川崎重工業㈱MK本部市場開発部長 資格:技術士(建設部門,総合技術監理部門)、土木鋼構造診断士、1級土木施工管理技士、溶接施工管理技術者1級、コンクリート主任技士、プレストレストコンクリート技士、技術士補(経営工学部門) [研究実績・業績] ●レインボーブリッジの設計・施工 ●かつしかハープ橋の振動実験 ●鋼コンクリート合成桁の研究開発 ●橋梁の点検ツール開発 |
||
| 担当科目 | 構造・材料、構造物設計、鋼構造基礎、鋼構造施工、溶接実習など | ||
| メッセージ | 長大吊橋の設計・架設計算、鋼・コンクリート複合橋梁の開発および設計業務に従事した後、橋梁の点検や維持補修関連の技術研究を行ってきました。構造物の設計・施工のプロセスでは、将来のメンテナンスを考えておくことが重要です。このような広い視野を持った人材を育成していきたいと思います。これまでの経験を活かし、理論と実践の両面から、学生の皆さんと共に研究に取組みたいと思います。 | ||
| 知・技の創造(埼玉新聞掲載) | 2018 |
2022 |
2023 |

| 今井 弘 教授・学科長・博士(工学) |  研究室ホームページへ 研究室ホームページへ |
|
|---|---|---|
| 主要経歴 | 三重大学大大学院博士後期課程修了(工学研究科システム工学専攻)、一級建築士 アトリエ系建築設計事務所勤務後、NGOやJICA(国際協力機構)にて紛争地での難民キャンプの計画設営や自然災害の被災地での緊急支援から復興支援に従事 [研究実績・業績] ●緊急支援用大型シェルター「バルーンシェルター」の開発 ●インド、イラン、パキスタン、インドネシア、ネパールにおいて震災後の組積造の耐震性向上に向けた耐震補強工法の研究開発および普及方策 ●東日本大震災における緊急支援として仮設風呂の設計、建設 ●アフガニスタンやアフリカ・シエラレオーネでの難民・国内避難民キャンプの計画、設営 ●コソヴォ自治州にて帰還民支援としてのシェルターの建設および学校修復事業 ●アフリカマラウイ共和国にて青年海外協力隊(職種:建築設計) |
|
| 担当科目 | 建設製図Ⅰ、建設基礎設計Ⅱ、構造材料Ⅰ | |
| メッセージ | これまでの活動を通して、「Design for the other 90%」という言葉を強く意識しています。世界の10%に占めるにすぎない最も豊かな顧客向けではなく、世の中の「本当のニーズ」に目を向けて、建築という「ものづくり」を通して、そのニーズに応える解決策を一緒に考えていきたいと思います。例えば、災害時の使用を前提にした、身近で安価な材料を用いて、簡単に設営可能な「セルフビルトのシェルター」など一緒に作れたらと思っています。 | |
| 知・技の創造(埼玉新聞掲載) | 2020 |
2024 |

| 澤本 武博 教授・教養教育センター長・学長補佐(教育組織改革準備室長)・博士(工学) |  研究室ホームページへ 研究室ホームページへ |
||
|---|---|---|---|
| 主要経歴 | 東京理科大学大学院博士後期課程修了、若築建設(株)川崎工事事務所、東京理科大学理工学部土木工学科助手 資格:高等学校教諭 専修免許状(工業) [研究実績・業績] ●微破壊によるコンクリート強度推定 ●簡易塩化物イオン量試験の開発 ●透気・透水試験による耐久性評価 ●コンクリート構造物の補修・評価 ●子供たちによるものづくり教育 |
||
| 担当科目 | 構造基礎実習Ⅰ、構造基礎実習Ⅱ、仕上基礎実習Ⅲ、社会基盤、RC構造物実習、RC構造物診断実習 | ||
| メッセージ | コンクリート構造物の環境への負担軽減、特にリサイクルと構造物の長寿命化をテーマに研究を行っています。自らの手で物をつくり、その成果をまとめることができるような人材の育成の一助になれると幸いです。いっしょに体と頭を動かしましょう。 | ||
| 知・技の創造(埼玉新聞掲載) | 2018 |
2022 |
2023 |

| 田尻 要 教授・学長補佐(地域連携推進・渉外室長、自己点検評価室副室長)・博士(工学) |  研究室ホームページへ 研究室ホームページへ |
||
|---|---|---|---|
| 主要経歴 | 九州大学大学院博士課程、西松建設(株)技術研究所研究員、群馬工業高等専門学校助教授 [研究実績・業績] ●自治体における地域課題の解決 (市街地有効活用・公共交通の最適化・ワークショップの運営・観光資源活用 等) ●地域防災計画の立案 ●企業の顧客調査とブランディング |
||
| 担当科目 | 環境、環境調査、エネルギー、測量、建設技能工芸実習 | ||
| メッセージ | 私達の生活を豊かにしてくれる「ものつくり」は、ハード的な知識や技術に加えて、背景や環境を知ることも重要です。社会から何が求められているのか?なぜ必要なのか?進むべき方向性は? なかでも都市生活を支えるためには、地盤環境から水資源問題さらに都市計画まで様々な課題の解決が必要です。ものつくりを通して学生のみなさんと一緒に都市における生活環境の向上を目指した研究に取り組んでいきたいと考えています。 「ものつくり」で「まちづくり」してみませんか? | ||
| 知・技の創造(埼玉新聞掲載) | 2017 |
2021 |
2023 |

| 大塚 秀三 教授・理事長補佐(財務マネジメント室長)学長補佐(教育連携推進室長)・博士(工学) |  研究室ホームページへ 研究室ホームページへ |
||
|---|---|---|---|
| 主要経歴 | 川口通正建築研究所、日本大学大学院博士後期課程修了 [研究実績・業績] ●国土交通省・建築基準整備促進事業(3事業) ●小型容器を用いたコンクリートのブリーディングに関する試験方法の提案 ●コンクリート工事関連技能者団体との共同調査研究 ●コンクリート工事に用いる各種資器材の開発 |
||
| 担当科目 | 建築観察学,鉄筋コンクリート造基礎および実習,RC施工Ⅰ・Ⅱ,RC型枠施工基礎および実習,建設材料基礎および実習 ほか | ||
| メッセージ | アトリエ系の建築設計事務所で主に住宅の設計に従事した後、コンクリートを中心とした材料・施工分野の研究を行ってきました。ものをつくるプロセスには、多くの選択肢の中から最適解を導き出すことが求められます。その最適解を自ら思考し実践できる広い視野を持った人材を育成していきたいと思います。これまでの経験を活かし、理論と実践の両面から「ものつくり」の楽しさを学生の皆さんと共有していきたいと思います。 | ||
| 知・技の創造(埼玉新聞掲載) | 2015 |
2019 |
2022 |

| 三原 斉 教授・学長補佐(施設設備計画部会長)・博士(工学) |  研究室ホームページへ 研究室ホームページへ |
||
|---|---|---|---|
| 主要経歴 | 近畿大学理工学部建築学科卒業、工学院大学大学院工学研究科建築学専攻博士後期課程修了、村本建設(株)東京本社建築部・購買課長・建築工務課長、日本工業大学付属東京工業高等学校建築科教諭・建築生産の科目を主担当 資格:一級建築士、一級建築施工管理技士、一級土木施工管理技士、一級建築図面製作技能士(建築図面製作 建築製図手書き作業)、一級建築図面製作技能士(建築図面製作 建築製図CAD作業)、BSI プロジェクトマネージャー、生産専攻建築士、被災建築物応急危険度判定員(東京都) [研究実績・業績] ●施工管理技術者教育に関する研究 (2012、2013年度中国国際会議で2年連続論文賞) ●インターシップを中心とする建設現場人材教育に関する研究 (2011-13年度科研費基盤研究C) ●建築系大学を中心とする施工管理技術者教育に関する研究 (2014-16年度科研費基盤研究C) ●加須市古民家再生PJ16`日本漆喰協会作品賞 |
||
| 担当科目 | 実習(鉄筋コンクリート/型枠工事、左官/タイル工事、造園/外構工事、測量基礎実習、測量士補の資格取得のための測量実習2)、工程計画演習、建築生産、建築構法、造園施工管理技術 他 | ||
| メッセージ | 三原研究室では、将来、建設現場で活躍する施工管理技術者および基幹的な上級技能者を育成するための教育について研究しています。また、建築生産を担う施工管理技術者や基幹技能者を実践教育を通して育成しています。 | ||
| 知・技の創造(埼玉新聞掲載) | 2018 |
2022 |
2024 |

| 荒巻 卓見 講師・博士(工学) |  研究業績へ 研究業績へ |
|
|---|---|---|
| 主要経歴 | ものつくり大学大学院修士課程修了、日本大学大学院博士後期課程修了、日本大学生産工学部ポスト・ドクトラル・フェロー、日本大学理工学部助手 [研究実績・業績] ●コンクリートの物理的・力学的性質の調査 ●鉄筋コンクリート工事の施工に関する研究 ●建設現場の実態調査 |
|
| 担当科目 | 構造・材料、建設材料基礎および実習、鉄筋コンクリート構造基礎および実習、RC構造物総合および実習 | |
| メッセージ | コンクリートを中心とした構造材料の性質や耐久性に関する研究に加え、鉄筋コンクリート工事の施工技術に関する研究を行ってきました。良質な構造物をつくるためには、構造の特徴と材料の性質を理解し、適切な施工方法により「ものづくり」を行うことが求められます。これを実現できる人材の育成を目標とし、理論と実践に基づく専門知識および技術・技能について学ぶ場を提供するとともに、研究を通して未知の課題を解決するプロセスを学生の皆さんと共有していきたいと思います。 | |
| 知・技の創造(埼玉新聞掲載) | 2024 |
|
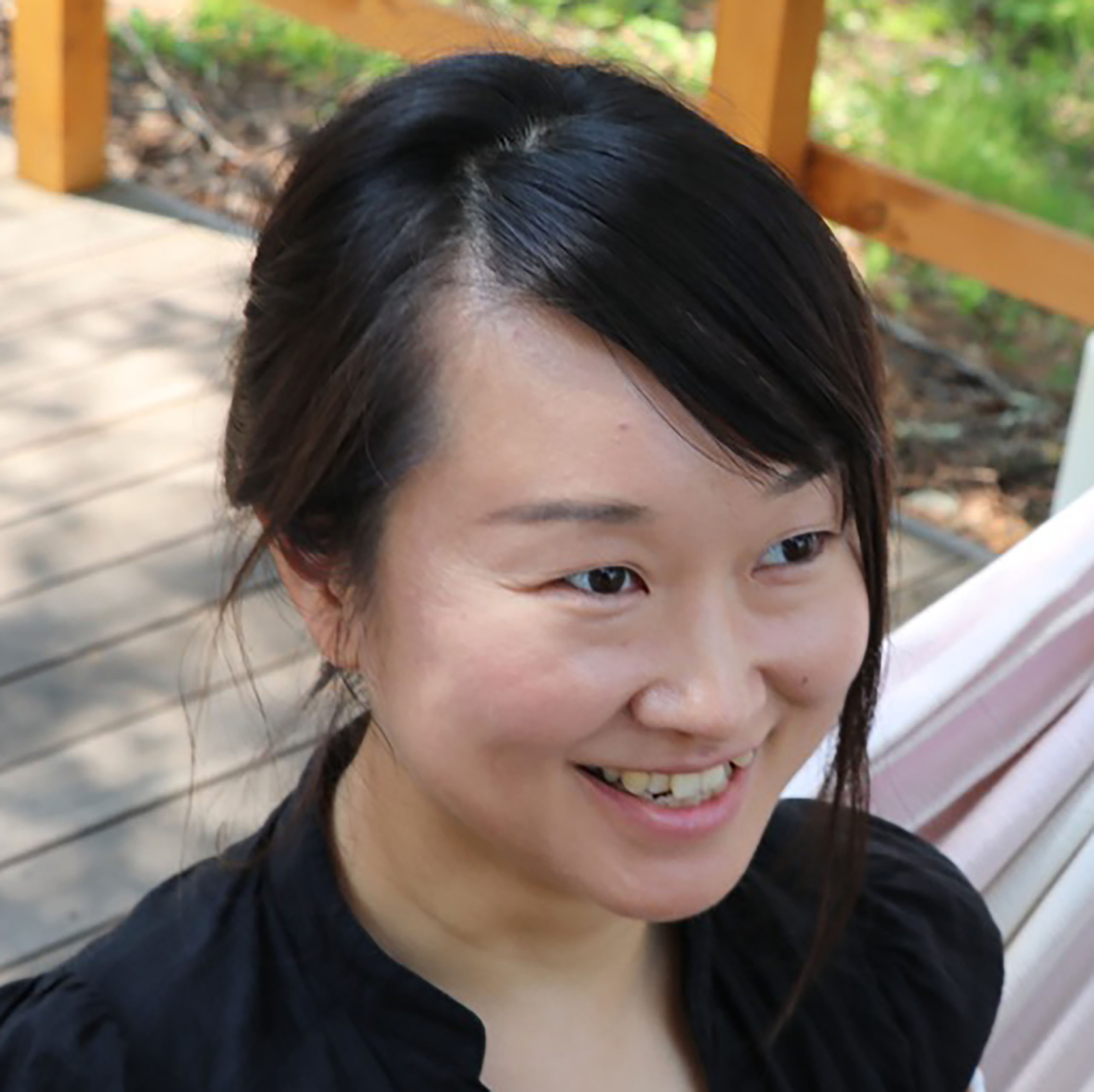
| 大竹 由夏 講師・博士(デザイン学) |  研究室ホームページへ 研究室ホームページへ |
|
|---|---|---|
| 主要経歴 | 筑波大学博士後期課程修了 資格:一級建築士 [研究実績・業績] ●景観計画・要網の調査 ●都市空間におけるランドマークの見え方の調査 ●メディアに表現された建造物・都市空間の調査 ●展示空間および展示ブースの制作 |
|
| 担当科目 | 建設製図、建設基礎設計、建設応用設計、建設CADおよび実習、仕上技能工芸および実習など | |
| メッセージ | 道を歩いていると、ランドマークは常に見えている気がします。しかし、実際にはビルや木々によりそのランドマークの全体は見えないことがほとんどです。街路や展望台など都市の様々な場所から実際に眺められる東京タワーの見え方や、漫画や映画のようなメディアを通じ仮想的に眺められる東京タワーの見え方を調査しています。一緒に、ランドマークを眺めて、都市景観への理解を深めましょう。 | |
| 知・技の創造(埼玉新聞掲載) | 2019 |
2022 |

| 岡田 公彦 教授 |  研究室ホームページへ 研究室ホームページへ |
|
|---|---|---|
| 主要経歴 | 中央大学理工学部管理工学科、明治大学理工学部建築学科卒(学士)。西沢立衛建築設計事務所を経て、岡田公彦建築設計事務所 代表。東京電機大学、明治大学、日本女子大学、多摩美術大学、東海大学非常勤講師 歴任 資格:一級建築士 [研究実績・業績] ●戸建住宅、集合住宅、商業施設、各種建築物の設計・現場監理 ●店舗、住宅等のインテリアに関する空間設計 ●展覧会会場構成やアートインスタレーションなどの仮設会場・構築物デザイン及び制作 |
|
| 担当科目 | 建設総合設計、建設応用設計、建設基礎設計、建築製図、建築計画 他 | |
| メッセージ | 建築設計やインテリアデザイン、アートインスタレーションなど、空間にまつわる様々な設計を体験し、時には自ら制作に関わってきました。その経験をもとに、学生の皆さんがこれから迎える新しい時代にふさわしい空間を、一緒に手や足を動かしながら実践的に考えていきたいと思います。そして歴史や環境、人に対する考察をふまえた幅広い視野を持って、建築やデザインの可能性を広げていくような活動をしていきます。 | |
| 知・技の創造(埼玉新聞掲載) | 2018 |
2022 |

| 奥崎 優 助教・博士(工学) |  研究実績へ 研究実績へ |
|
|---|---|---|
| 主要経歴 | 芝浦工業大学大学院修士課程修了、岩瀬建築有限会社、奥崎工業株式会社、芝浦工業大学大学院博士後期課程修了 [研究実績・業績] ●田沼町(栃木県佐野市)の一瓶塚稲荷神社社殿再建と大工三村正利の役割について 日本建築学会技術報告集第27巻第65号 ●野木町(栃木県下都賀郡)の野木神社社殿再建と三村家の役割および生産体制について 日本建築学会計画系論文集第86巻第780号 ●花野井(千葉県柏市)の香取神社本殿再建と大工棟梁および彫物師の職域について 日本建築学会計画系論文集第85巻第768号 |
|
| 担当科目 | 木造基礎および実習、木造応用および実習 | |
| メッセージ | 近世から近代にかけて活動していた大工家の建築生産の実態に関する研究を行っています。現代にいたるまでの日本の建設業の発展は、近世以来、建築生産の直接的な担い手である大工によって築き上げられてきた基盤があってなされたといえます。建築生産の在り方は、近世から近代、現代へと連続性の中で構築されてきました。その歴史の流れを学ぶことは、これからの建築生産の在り方を探究する上で重要になります。これからの建設業の担い手になる皆さんには過去のことにも目を向けて、広い視野をもって未来に突き進んでもらいたいと思います。 | |
| 知・技の創造(埼玉新聞掲載) | 2024 |
|

| 佐々木 昌孝 教授・博士(工学) |  研究室ホームページへ 研究室ホームページへ |
||
|---|---|---|---|
| 主要経歴 | 早稲田大学大学院博士後期課程修了、内田橋住宅(株)、早稲田大学理工学部建築学科助手 資格:宅地建物取引士 [研究実績・業績] ●秩父夜祭り屋台模型の製作 ●木製店舗什器の製作 ●木製家具の実測調査 ●NCルータを活用した木材加工 |
||
| 担当科目 | 木造基礎および実習Ⅰ、木造応用および実習AⅡ、木造応用および実習B | ||
| メッセージ | 江戸時代の大工組織、主に江戸幕府役職にあった大工棟梁家の系譜をテーマに研究を行っています。伝統的なつくり手の技と心にふれながら、日本の建築文化が進むべき、ものつくりが進むべき姿をみなさんと一緒に探求していきたいと思います。 | ||
| 知・技の創造(埼玉新聞掲載) | 2015 |
2019 |
2023 |

| 芝沼 健太 講師・修士(工学) |  研究業績 研究業績 |
|
|---|---|---|
| 主要経歴 | 工学院大学卒業、宇都宮大学大学院修士取得、(有)設計工房佐久間、国立大学法人 千葉大学 非常勤講師 [研究実績・業績] ●木造建物の耐震診断・耐震補強設計・補強工事 ●木造建物の振動台実験 ●木造建物の構造設計 |
|
| 担当科目 | 材料力学、構造力学、木造基礎および実習、木質構造設計演習、木質構造および実験 | |
| メッセージ | 木造建物の耐震性能に関する研究を行ってきました。特に木造建物の耐震診断・耐震補強設計・補強工事に力を入れております。現在、建っている建物は、年代により地震により倒壊する恐れがあります。それを耐震診断し、倒壊のおそれがある場合には補強設計を行い、補強工事により安全性を確保します。耐震診断が必要な建物はたくさんありますので今後も地震の際の被害を少なくするためにも学生の皆さんと一緒に積極的に研究を進めていきたいと思います。 | |
| 知・技の創造(埼玉新聞掲載) | 2024 |
|
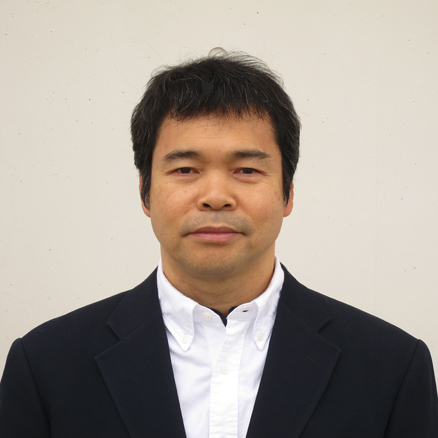
| 高橋 宏樹 教授・博士(工学) |  研究室ホームページへ 研究室ホームページへ |
||
|---|---|---|---|
| 主要経歴 | 順天堂大学大学院修士修了、順天堂大学嘱託(体育学部生理学研究室)、東京工業大学助手 [研究実績・業績] ●床のすべりの評価における床表面介在物の標準化に関する研究:日本建築学会構造系論文報告集第450号 ●足元の安定性からみた床および路面のかたさと凹凸の相対的評価方法の提示:日本建築学会構造系論文集第496号 ●左官のモルタル塗り動作時の塗面にかかる荷重および筋電位に関する基礎的検討、日本建築学会構造系論文集第717号 |
||
| 担当科目 | 仕上実習、仕上材料、コミュニケーション学、救命法・衛生、人間工学他 | ||
| メッセージ | 大学で床や壁の使用感について研究しています。ものをつくるのは人です。ものを使うのもまた人です。「コミュニケーション」や「人間工学」などの授業を通して、人への理解を深めて欲しいと思います。 | ||
| 知・技の創造(埼玉新聞掲載) | 2017 |
2021 |
2023 |

| 土居 浩 教授・博士(学術)・教養教育センター兼担 |  研究室ホームページへ 研究室ホームページへ |
||
|---|---|---|---|
| 主要経歴 | 京都教育大学教育学部・学士(教養)、同大学院・修士(教育学)。総合研究大学院大学博士課程(国際日本研究専攻)修了。国際日本文化研究センターCOE講師、ものつくり大学専任講師、同准教授を経て現職。荒川区文化財保護審議会委員。 [研究実績・業績] ●葬墓制史研究 ●日常生活を維持・改善する諸実践の調査研究 ●文化財保護行政とくに伝統工芸技術の調査協力 ●長期的居住環境の調査研究(千年村プロジェクト) |
||
| 担当科目 | ものつくり・ひとつくり総合講義、SDGs、日本文化論、梅原猛で学ぶ学問と世界 | ||
| メッセージ | 日本語には「ものになる」との表現があります。一人前の人物(者/腕前)になる、習い覚えた技が身につく、等々の意味です。「ものになる」ためには、社会の中で学ぶ姿勢を、身につけなければなりません。私自身、まがりなりにも教員として「ものになる」ことができているとすれば、これまで対面した学生諸君から様々に学んだ結果です。これから対面する学生諸君にも「ものづくり」を通して「ものになる」ように、ともに学びたいと願ってます。 | ||
| 知・技の創造(埼玉新聞掲載) | 2016 |
2021 |
2024 |

| 戸田 都生男 教授・博士(学術)・地域木材・森林共生研究センター長 |  研究室ホームページへ 研究室ホームページへ |
|
|---|---|---|
| 主要経歴 | 大阪芸術大学建築学科卒業、京都府立大学大学院博士後期課程生命環境科学研究科単位取得認定、ゼネコン、Ms建築設計事務所(建築家:三澤康彦・文子に師事)、木匠塾事務局、京都造形芸術大学環境デザイン学科副手、(財)啓明社特別研究員、近畿大学工業高等専門学校非常勤講師、麻生建築&デザイン専門学校専任講師 資格:一級建築士、木材加工用機械作業主任者、環境カウンセラー(環境省登録) [研究実績・作品実績] ●木のものづくり教育を活かした木造空き家活用モデルの構築(2019~2024 年度 文部科学省 科研費若手 代表者) ●木造住宅診断・改修における新たな多能工育成のための創意工夫と学びのプロセスの探索(2024~2027 年度 文部科学省 科研費基盤C 代表者) ●行田市への来訪者の意識・足袋蔵経路探索に関する研究 ●木質空間が「賑わい」に及ぼす影響 ● 2019年度 日本建築学会教育賞(教育貢献)受賞 川上村木匠塾・奈良県川上村(共同) ●第1回・第4回ウッドデザイン賞受賞 林野庁後援 |
|
| 担当科目 | 建設概論、住宅論、木造住宅設計、建築応用設計実習、建設製図、木造基礎実習、木造応用実習、デジタルファブリケーション特論、SDGs特論 他 | |
| メッセージ | 阪神淡路大震災で瓦礫や廃木材等を目の当りにして建築を志しました。木材の背景である森林は日本の国土の約7割を占めます。長い年月をかけて生育した樹木が木造建築として在るとすれば、私たち人間は樹齢に劣らない「ものつくり」を心得るべきではないでしょうか。未来を担う学生皆さんに、ハードな技術の修得に加えてソフトな人間関係の構築や多様な条件や意見をまとめる総合力を身につけてほしいと思っています。一日一日に感謝して一緒に励みましょう。 | |
| 知・技の創造(埼玉新聞掲載) | 2017 |
2021 |

| 松岡 大介 教授 博士(工学) |  研究室ホームページへ 研究室ホームページへ |
|
|---|---|---|
| 主要経歴 | 東洋大学大学院博士前期課程修了、(株)ポラス暮し科学研究所、東洋大学非常勤講師、京都大学大学院博士後期課程修了 資格:一級建築士、応急危険度判定士(埼玉県)、CASBEE戸建評価員 [研究実績・業績] ●吹抜け空間などの温熱環境 ●給湯・暖冷房エネルギー調査 ●小屋裏・壁体内などの結露防止 ●住宅断熱工法、空調システムの開発 ●第2回サステブル住宅賞受賞・埼玉県環境建築住宅賞「最優秀賞」受賞 |
|
| 担当科目 | 建設設備、環境・設備総合実習 他 | |
| メッセージ | 主に住宅の省エネ、快適性、耐久性(湿害の抑制)の向上について研究と開発を行ってきました。住宅生産の現場で痛感したことは、建築環境工学や設備工学を活かした設計や施工のできる人が極端に少ないということです。これからの建築は、環境工学の知識を最大限に活かし、使用エネルギーを最小にする「ものつくり」が重要になります。学生の皆さんとは実際の環境の体感・体験を基にした研究を行って、知識と実践力を備えたテクノロジストを多く輩出していきたいと思っています。 | |
| 知・技の創造(埼玉新聞掲載) | 2018 |
2022 |

| 間藤 早太 教授 | ||
|---|---|---|
| 主要経歴 | 日本大学理工学部建築学科卒業(学士)、金箱構造設計事務所、間藤構造設計事務所 資格:一級建築士、構造設計一級建築士 [研究実績・業績] ●第41回東京建築賞最優秀賞 ●2015年度グッドデザイン賞(UTH(個人住宅):構造担当) ●いばらきデザインセレクション選定(ハコフネ:構造担当) |
|
| 担当科目 | 木造基礎および実習、木造応用および実習、木造総合および実習、構造力学、木造軸組工法 | |
| メッセージ | アトリエ系の構造設計事務所で25年間にわたり木造、RC造、S造と種別を問わず建築物の構造設計から現場監理までを一貫してやってきました。実務で体験してきた多岐に渡る構造計画を踏まえて、学生の皆さんと新しい構造デザインを一緒に考えていく事で従来の技術力はもとより応用力を備えた柔軟な思考を養って頂きたいと思っています。また実務に即した研究を目指し、新しい技術を実際の建物に反映していく事で関わってきた研究が本物のものづくりの一部になっているという喜びを共有できればと思います。 | |
| 知・技の創造(埼玉新聞掲載) | 2023 |
|

| 横山 晋一 教授・博士(工学) |  研究室ホームページへ 研究室ホームページへ |
||
|---|---|---|---|
| 主要経歴 | 横浜国立大学大学院博士課程後期修了、財団法人文化財建造物保存技術協会、学校法人立教学院立教大学 資格:文化財建造物修理技術者、博物館学芸員、建築・設備総合管理技術者 [研究実績・業績] ●深谷商業高校記念館の復原考察 ●箭弓稲荷神社社殿の調査・修復設計 ●常光院本堂の調査研究 ●鴻巣御殿再現模型制作監修 |
||
| 担当科目 | 日本建築史、近現代建築史、保存修復学 他 | ||
| メッセージ | 国内に所在する歴史的建造物の修復設計監理並びに、調査研究に携わってきました。我国古来よりの建築は、風土に適した木造建築が主でありますが、この構工法等を実習や設計を通じて学び、第一線で即座に活躍できる建築技術・技能者の育成に努めて参りたいと思います。また、地域に根付く歴史的建造物の保全にも研究室を挙げて参画し、研究活動を学生と共に推進させたいと考えております。 | ||
| 知・技の創造(埼玉新聞掲載) | 2017 |
2021 |
2025 |
建設学科 客員教授
特別客員教授 朽木 宏
特別客員教授 鈴木 光
特別客員教授 長谷川 正幸
特別客員教授 八代 克彦
特別客員教授 小野 泰
特別客員教授 北條 哲男
客員教授 山崎 健二
客員教授 渡邉 進
-
 048-564-3200(代表)
048-564-3200(代表)【受付時間】月~金曜日 9:00~17:30
〒361-0038
埼玉県行田市前谷333番地 アクセス
アクセス
- 資料請求
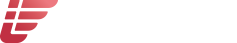

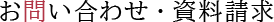
 お問い合わせページ
お問い合わせページ