木造小屋に取り付ける,建具の制作です。
建具とは,窓などの開口部につける扉や戸,サッシュです。
日本建築でいえば,引き違いに動く,障子や襖(ふすま)もそうですね。




木製ベンチの脚と背もたれの受け材,座面になる部分は製材(角材)で組み立て,
背もたれと脚を繋ぐ部材は丸太を利用します。丸太は転がるので墨打ちや加工には滑り止めとなる冶具を置く等して工夫が必要です。


現場での建て方(敷地に建築を建てること)にむけて,
加工場で木材を加工し,仮組みを進めていきます。



1本1本の土台や柱,梁などの線状の木材をノコギリやノミなどで刻み,連結してゆくのです。 Continue reading
あっという間に師走,12月半ばです。
11月下旬には,ものつくり大学も積雪しました。


暖冬と思いつつ,寒くなり,埼玉県北のこの辺りの気候を少しずつ体感して耐寒?する最近です。 Continue reading
2年生の木造実習では,3Qと4Q(クォータ)で木造応用実習のそれぞれⅠ,Ⅱとして,
チームで木造の小屋を制作します。
小規模な木造住宅といってもよいでしょう。
下の写真のとおり過去の制作物が学内に残っています。
11月下旬から12月に入り,4Q(クォータ)の授業も半分を終えようとしています。
年間を4分割にして各期間8回の授業のため展開が早いですが,豊富な実習が体験できます。
1年生の最後の木造基礎実習は,下の模型写真の木製ベンチを実物で制作します。
3Q(クォータ)は11月下旬で終わり,1年生の木造実習ではプランター(朝顔鉢)が完成しました。
四方転びといって,プランターの枠の板の角度が微妙に傾いており,
ぴったり合わす作業は難航しましたが,粘り強い加工の技術と技能の体験ができたことでしょう。
夏休み明け,9月末から10月末の約1ヶ月間は,毎週火曜の夕方,2時間から2.5時間程度,研究室のゼミを行いました。
現在,3年生だけのため比較的,多くの時間が取れますが,10名なのでそこそこ時間がかかります。
夏休みの課題の一つである研究室必読書10冊のうち1冊を選び,考えたことを発表すること等を行いました。
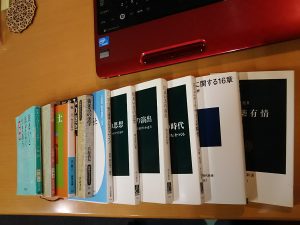
実習の4回目から8回目(週目)までは,
四方転びプランター(朝顔鉢) の制作を行います。
四方転びとは,傾きを持たせながら接合強度を上げる組み方といったところでしょうか。
これも先ず原寸図を描いて墨付け,刻み(加工),組み立ての手順で制作します。
見本となる完成形はこのような感じです。